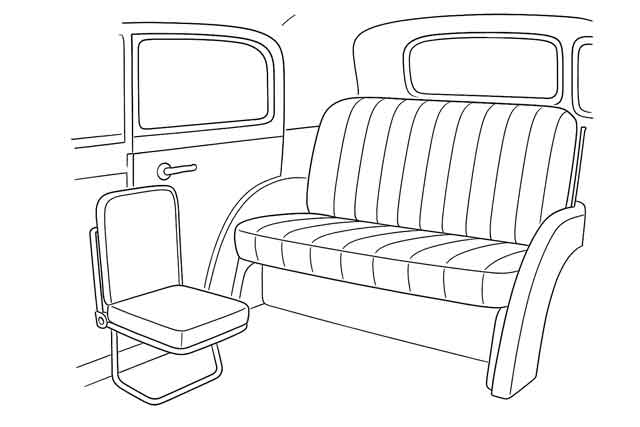「お前さんの知ったことじゃない。お前さんは、そんなことは、一切考えないで、気を落着けているのだ。いゝか。いゝか。」
「いゝえ! いゝえ!
妾を打ったために、あの方が
牢へ行かれるようなことが、ございましたら、
妾は生きては、おりません。お父様! どうぞ、どうぞ、内済にして下さいませ。」
美奈子は、息を切らしながら、とぎれ/\に言った。
傲岸不屈な
荘田も、
遉に黙ってしまった。
直也の二つの眼には、あつい湯のような涙が、
湧くように
溢れていた。初めて、顔を見たばかりの少女の、厚い
情に対する感激の涙だった。
心の武装
一
記憶のよい人々は、
或は覚えているかも知れない。大正六年の九月の末に、東京大阪の各新聞紙が筆を
揃えて報道した
唐沢男爵の愛嬢
瑠璃子の結婚を。それは近年にない
大評判な結婚であった。
此の結婚が、一世の人心を
湧かし、
姦しい【そうぞうしい】世評を生んだ第一の原因は、その新郎新婦の年齢が恐ろしいほど隔っていた
為であった。二三の新聞は、第二の小森幸子事件であると称して、世道人心に及ぼす悪影響を嘆いた。小森幸子事件とは、ついその六七年前、時の
宮内大臣
田中伯が、還暦を過ぎた老体を
以て、まだ
二十を過ぎたばかりの
処女――爵位と権勢に
憧るゝ虚栄の女と、婚約をした為に一世の
烈しい指弾と抗議とを招いた事件だった。
無論、新郎の
荘田勝平は、当時の
田中伯よりも若かった。が、それと同時に、新婦の唐沢
瑠璃子は小森幸子などとは比較にならないほど美しく、比較にならないほど名門の娘であり、比較にならないほど若かった。
新聞紙に並べられた新郎新婦の写真を見た者は、男性も女性も、等しく
眉を
顰めた。が、
此の結婚が姦しい世評を産んだ原因は、たゞ新郎新婦の年齢の相違ばかりではなかった。もう一つの原因は、成金、荘田
勝平が、
唐沢家の娘を金で買ったと言う
噂だった。
146/390
或新聞紙は貴族院第一の硬骨を以て、称せらるゝ
唐沢男爵に、そうした
卑しい事のあるべき
筈はないと、打消した。他の新聞紙は
宛も事件の真相を伝える
如くに言った、
曰く『荘田
勝平は
唐沢男爵に
私淑しているのだ。彼は数十万円を投じて
唐沢家の財政上の窮状を救ったのだ。
唐沢男が、娘を与えたのは、その恩義に感じたからである。』と。他の新聞紙は、またこんな記事を載せた。結婚の動機は、唐沢
瑠璃子の強い虚栄からである。彼女は学習院の女子部にいた頃から、同窓の人々の眉を
顰めさせるほど、虚栄心に富んだ女であった、と。そうした記事に伴って女子教育家や社会批評家の意見が紙面を
賑わした。或者は、成金の金に
委せての横暴が、世の
良風美俗【美しく素晴らしい風習や習慣】を破ると言って憤慨した。或者は、米国の富豪の娘達が、
欧洲の貴族と結婚して、富と爵位との交換を計るように、日本でも貧乏な華族と富豪が
頻々として縁組を始めたことを指摘して、面白からぬ傾向である、華族の堕落であると結論した。
が、そうした
轟々たる世論を
外に、
荘田は結婚の準備をした。春の園遊会に、十万円を投じて惜しまなかった彼は、晴の結婚式場には、黄金の花を敷くばかりの意気込であった。彼は、自分の結婚に対して非難攻撃が高くなればなるほど、反抗的に
公然に華美に
豪奢に、式を挙げようと決心していた。
彼は、あらゆる手段で、朝野の名流【社会の上層に属する名のある人々】を、その
披露の式場に
蒐めようとした。彼は、あらゆる縁故を
辿って、貴族
顕官【高官】の列席を、頼み回った。
九月二十九日の
夕であった。
日比谷公園の
樹の間に、薄紫のアーク
灯が、ほのめき始めた頃から幾台も幾台もの自動車が、北から南から、西から東から、軽快な車台で夕暮の空気を切りながら、山下門の帝国ホテルを目指して集まって来た。
147/390
最新輸入の新しい型の自動車と交っては、昔ゆかしい
定紋の付いた箱馬車に、
栗毛の
駿足を並べて、優雅に上品に、
軋せて来る
堂上華族も見えた。
遉に広いホテルの玄関先も、後から/\
蒐まって来る馬車や自動車を、収め切れないではみ出された自動車や馬車は往来に沿うて一町ばかりも並んでいた。
祝宴が始まる前の
控場の大広間には、余興の舞台が設けられていて、今しがた帝劇の
嘉久子と
浪子とが、
二人道成寺を踊り始めたところだった。
二
新郎の
勝平は、控室の入口に、新婦の
瑠璃子と並び立って、次ぎ次ぎに到着する人々を迎えていた。
彼は
嘘から出た
真と言う言葉を心の
裡で思い起していた。本当に、彼の結婚は嘘から出た真であった。彼は、妙にこじれてしまった意地から、相手を苦しめる
為に、申込んだ結婚が、相手が思いの外に、
脆かった為、手軽に実現したことが少し くすぐったいようにも思った。それと同時に、名門のたった一人の令嬢をさえ、自分の金の力で、
到頭買い得たかと思うと、心の底からむら/\と
湧く得意の情を押えることが出来なかった。
が、結婚の式場に
列るまで、彼は
瑠璃子を
高価で
購った装飾品のようにしか思っていなかった。五万円に近い大金を投じて、
落藉した
愛妓【囲った芸者】に対するほどの感情をも持っていなかった。『
此のお嬢さん
屹度むずがるに違いない。なに、むずかったって、高の知れた子供だ。ふゝん。』と言ったような気持で神聖なるべき式場に
列った。
が、雪のように白い白紋
綸子の
振袖の上に目も
覚むるような唐織
錦の
裲襠を
被た
瑠璃子の姿を見ると、彼は生れて初めて感じたような気高さと美しさに、打たれてしまって、神官が朗々と唱え上げる
祝詞の言葉なども耳に入らぬほど、じっと
瑠璃子の姿に、魅せられていた。
148/390
その輪郭の正しい顔は
凄いほど澄みわたって、
神々しいと言ってもいゝような美しさが、
勝平の不純な心持ちをさえ、
浄めるようだった。
式が、無事に終って、大神宮から帝国ホテルまでの目と鼻の距離を、初めて自動車に同乗したときに言い知れぬ
嬉しさが、
勝平の胸の中に、こみ上げて来た。彼は、どうかして、最初の言葉を掛けたかった。が、日頃
傲岸不遜な、人を人とも思わない
勝平であるにも
拘わらず、話しかけようとする言葉が、一つ/\
咽喉にからんでしまって、小娘か何かのように、その四十男の
巨きい顔が、ほんの少しではあるが、赤らんだ。彼は、
唐沢家をあんなにまで、迫害したことが、後悔された。
瑠璃子が、自分のことを一体
何う思っているだろうと、言うことが一番心配になり始めた。
式服を着換えて、今
勝平の横に立っている
瑠璃子は、前よりもっと美しかった。
御所解模様を胸高に総縫にした黒
縮緬の振袖が、そのスラリとした
白皙の
身体に、しっくりと似合っていた。
勝平は、こうして若い美しい妻を得たことが、自分の生涯を
彩る第一の幸福であるようにさえ思われた。今までは、彼の
唯一つの誇は、金力であった。が、今はそれよりも、もっと誇っていゝものが、得られたようにさえ思った。
大臣を初め、政府の高官達が来る。実業家が来る。軍人が来る。
唐沢家の関係から、貴族院に籍を置く、
伯爵や子爵が
殊に多かった。大抵は、夫人を同伴していた。美人の妻を持っているので、有名な
小早川伯爵が来たとき、
勝平は同伴した伯爵夫人を、自分の
新妻と比べて見た。伯爵夫妻が、
会釈して去った時、
勝平の顔には、得意な微笑が浮んだ。
虎の
門第一の美人として、
謳われたことのある勧業銀行の総裁吉村氏の令嬢が、その父に伴われて、その美しい姿を現わしたとき、
勝平はまた思わず、自分の新妻と比べて見ずにはいられなかった。無論、この令嬢も美しいことは美しかった。
149/390
が、その美しさは、華美な陽気な美しさで、
瑠璃子のそれに見るような澄んだ神々しさはなかった。
『やっぱり、育ちが育ちだから。』
勝平は、口の中で、こんな風に、新しい妻を
賛美しながら、日本中で、一番得意な人間として、後から後からと続いて来る客に、
平素に似ない
愛嬌を振り
蒔いていた。
来客の足が、やゝ薄らいだ頃だった。
此の結婚を
纏めた殊勲者である
木下が新調のフロックコートを着ながら、ニコニコと入って来た。
「やあ! お目出度うございます。お目出度うございます!」
彼は
勝平に、ペコ/\と頭を下げてから、その傍の新夫人に、丁寧に頭を下げたが、
今迄は
凡ての来客の祝賀を、神妙に受けていた
瑠璃子は
木下の顔を見ると、その高島田に結った頭を、
昂然と高く持したまゝ、
一寸は愚か一分も動かさなかった。勝手が違って、
狼狽する
木下に、
一瞥も与えずに、彼女は怒れる女王の
如き、冷然たる儀容を崩さなかった。
三
祝宴が開かれたのは、午後七時を回っていた時分だった。
集合電灯の華やかな昼のような光の下に五百人を越す紳士とその半分に近い婦人とが
淑かに席に着いた。紳士は、大抵フロックコートか、
五つ紋の
紋付であったが、婦人達は今日を晴と銘々きらびやかな盛装を
競っていた。
花嫁と言ったような心持は、少しも持たず、戦場にでも出るような心で、
身体には
錦繍を
纏っているものの、心には
甲冑を
装うている
瑠璃子ではあったが、こうして沢山の紳士淑女の前に、花嫁として
晒されると、必死な覚悟をしている彼女にも、恥しさが一杯だった。列席の人々は、結婚が非常な
評判を起した
丈、それ
丈、花嫁の顔を、ジロ/\と見ているように、
瑠璃子には思われた。
金で
操を左右されたものと思われているかも知れないことが、
瑠璃子には――勝気な
瑠璃子には、死に
勝る恥のようにも思われた。が、彼女は全力を振って、そうした恥しさと戦った。
150/390
人は何とも思え、自分は正しい勇ましい道を
辿っているのだと、彼女は心の中で、ともすれば
撓みがちな勇気を振い起した。
が、苦しんでいるものは、
瑠璃子丈ではなかった。新郎の
勝平と、一尺も離れないで、黙々と席に就いている父の顔を見ると、
瑠璃子は自分の苦しみなどは、父の十分の一にも足りないように思った。自分は、自分から進んで、こうした苦痛を買っているのだ。が、父は最愛の娘を敵に与えようとしている。
縦令、それが娘自身の発意であるにしろ、男子として、
殊に硬骨な父として、どんなに苦しい無念なことであろうかと思った。
が、苦しんでいる者は、外にもあった。それは
今宵の
月下氷人【仲人】を勤めている
杉野子爵だった。子爵は、
瑠璃子が自分の息子の恋人であることを知ってから、どれほど苦しんでいるか分らなかった。
瑠璃子に対する
荘田の求婚が、本当は自分の息子に対する、
復讐であったことを知ってから、彼はその復讐の手先になっていた、自分のあさましさが、しみ/″\と感ぜられた。殊に、そのために、息子が殺傷の罪を犯したことを考えると、彼は立っても
座っても、いられないような良心の
苛責を受けた。
日比谷大神宮の神前でも、彼は
瑠璃子の顔を、仰ぎ見ることさえなし得なかった。彼は、
瑠璃子親子の前には、罪を待つ罪人のように、
悄然と【元気がなく】その頭を垂れていた。
今宵の祝賀の
的であるべき花嫁を初め、親や
仲人が、銘々の苦しみに
悶えているにも
拘わらず、祝賀の宴は、飽くまでも華やかだった。
価高い洋酒が、次ぎから次ぎへと抜かれた。料理人が、懸命の腕を振った珍しい料理が後から後から運ばれた。低くはあるが、華やかな
さゞめきが卓から卓へ流れた。
デザートコースになってから、貴族院議長のT
公爵が立ち上った。
151/390
公爵は、貴族院の議場の名物である、その
荘重【おごそかで重々しい】な態度を、いつもよりも、もっと荘重にして言った。
「私は、
茲に御列席になった皆様を代表して、
荘田唐沢両家の万歳を祈り、新郎新婦の前途を祝したいと思います。
何うか皆様新郎新婦の前途を
祝うて御乾杯を願います。」
公爵は、そう言いながら、そのなみ/\と、つがれた
三鞭酒の
盃を、自分と相対して立っている
逓相の
近藤男爵の盃に、カチリと触れさせた。
それと同時に、公爵の
音頭で、
荘田唐沢両家の万歳が、一斉に三唱された。
丁度その時であった。その祝辞を受くるべく立ち上ろうとした
唐沢男爵の顔が、急に
蒼ざめたかと思うと、ヒョロ/\とその長身の身体が後に二三歩よろめいたまゝ、枯木の倒れるように、力なく床の上に崩れ落ちた。
四
唐沢男爵の突然な卒倒は、晴の盛宴を
滅茶苦茶にしてしまった。
遉に、心の
利いた給仕人は、手早く一室に
担ぎ込んだが、列席の人々の動揺は、どうともすることが出来なかった。
瑠璃子は、花嫁である身分も忘れて、父の
傍に
馳け付けたまゝ、晴着の
振袖を気にしながら、懸命に介抱した。
給仕人が、必死になって最後のコーヒを運ぶのを待ち兼ねて、仲人の
杉野子爵は立って来客達に、列席の労を謝した。それを機会に、今まで浮腰になっていた来客は、潮の引くように、一時に流れ出てしまって、
煌々たる
電灯の光の流れている大広間には、
勝平を初めとし四五人の人々が寂しく取り残された
丈だった。
瑠璃子の父は、
幸に軽い脳貧血であった。呼びにやった医者が来ない前に、もう、常態に復していた。が、彼は黙々として自分を取り囲んでいる
杉野や
勝平には、一言も言葉をかけなかった。
152/390
父が、用意された自動車に、やっと回復した身体を乗せて、
今宵からは、最愛の娘と離れて、たゞ一人住むべき家へ帰って行く後姿を見ると、鉄のように冷くつぼんでいる
瑠璃子の心も、底から
掻き回わされるような痛みを感ぜずにはいられなかった。
瑠璃子は、父の自動車に身体をピッタリと附けながら、小声で言った。
「お父様
暫らく御辛抱して下さいませ。直きにお父様の
許へ帰って行きます。どうぞ、
妾を信じて待っていて下さいませ。」
遉に彼女の眼にも、湯のような涙が、ほたほたと
溢れた。
父は、
瑠璃子の言葉を聴くと大きく
肯きながら、
「お前の決心を忘れるな。お父さんが、今宵受けた恥を忘れるな。」
父が低く
然し、力強くこう
呟いた時、自動車は軽く滑り出していた。
父を乗せた自動車が、
出で去った後の車寄に附けられた自動車は、
荘田がつい
此間、
伊太利から求めた華麗な
フィヤット型の大自動車であった。新郎新婦を、その幾久しき
合衾の床に送るべき
目出度き乗物だった。
瑠璃子は、夫――それに違いはなかった――に招かるゝまゝ、相並んで腰を降した。が、その美しい唇は
彫像のそれのように、堅く/\結ばれていた。
勝平は、
何うにかして、
瑠璃子と言葉を交えたかった。彼は、
瑠璃子の美しさがしみ/″\と、感ぜられゝば感ぜられる
丈、たゞ黙って、並んでいることが、
愈苦痛になり出した。
彼は、
瑠璃子の顔色を
窺いながら、オズ/\口を開いた。
「大変沈んでおられるようじゃが、そう心配せいでもようござんすよ。
俺だって
貴女が思っているほど、無情な人間じゃありません。
貴女のお父様を、
苛めて済まんと思っているのです。罪滅ぼしに、出来る
丈のことはしようと思っているのです。
貴女も、俺を
敵のように思わんでな。これも縁じゃからな。」
153/390
勝平は、誰に対しても、使ったことのないような、丁寧な
訛のある言葉で、哀願するような口調でしみ/″\と話し出した。が、
瑠璃子は、黙々として言葉を出さなかった。二人の間に重苦しい沈黙が暫らく続いた。
「実は恥を言わねばならないのだが、今年の春、
俺の家の園遊会で、
貴女を見てから、
年甲斐もなく、はゝゝゝゝ。それで、つい、心にもなく
貴女のお父様までも、苦しめて、どうも何とも済まないことをしました。」
勝平は、
瑠璃子の心を解こうとして心にもない
嘘を言いながら、大きく頭を下げて見せた。
その
刹那に、美しい
瑠璃子の顔に、皮肉な微笑が動いたかと思うと、彼女の
容子は、一瞬の
裡に変っていた。
「そんなに言って下さると
妾の方が
却って痛み入りますわ。
妾のような者を、それほどまでして、望んで下さったかと思うと、ほゝゝゝゝ。」
と、車内の
薄暗の
裡でもハッキリと
判るほど、
瑠璃子は
勝平の方を向いて、
嫣然と笑って見せた。
勝平は、その一笑を投げられると、魂を奪われた人間のように、フラ/\としてしまった。
五
瑠璃子の
嫣然たる微笑を浴びると、
勝平は
三鞭酒の
酔が、だん/\回って来たその
巨きい顔の
相好を、たわいもなく崩してしまいながら、
「あゝ、そうでがすか。
貴女の心持はそうですか、それを知らんもんですから、心配したわい。」
彼は余りのうれしさに、生れ故郷の
訛りを、スッカリ丸出しにしながら、
身体に似合わない優しい声を出した。
「
貴女が心の中から、私のところへ、
欣んで来て下さる。こんな
嬉しいことはない。
貴女のためなら
俺の財産をみんな投げ出しても惜しみはせん。あはゝゝゝゝ。」
荘田は、恥しそうに顔を
俯している
瑠璃子の、薄暗の中でも、くっきりと白い襟足を、
貪るように見詰めながら、有頂天になって言った。
154/390
「
貴女が来て下されば、
俺も
今迄の三倍も五倍もの精力で、働きますぞ。うんと金を
儲けて、
貴女の身体をダイヤモンドで
埋めて上げますよ。あはゝゝゝゝゝ。」
荘田は、
何うかして、
瑠璃子の微笑と歓心とを
贏ちえようと、懸命になって話しかけた。
十時を過ぎたお
濠端の
闇を、
瑠璃子を乗せた自動車を先頭に、
美奈子を乗せた自動車を中に、召使達の乗った自動車を最後に、三台の自動車は、
瞬く
裡に、
日比谷から
三宅坂へ、三宅坂から五番町へと
殆ど三分もかゝらなかった。
瑠璃子が、夫に
扶けられて、自動車から
広壮な車寄に、降り立った時、
遉にその覚悟した胸が、
烈しくときめくのを感じた。単身敵の本城へ乗り込んで行く、刺客のような緊張と不安とを感じた。
勝平に
扶けられている手が、かすかに
顫えるのを、彼女は必死に制しようとした。
瑠璃子が、
勝平に従って、玄関へ上がろうとした時だった。
其処に出迎えている、多数の召使の前に、ヌッとつッ立っている若者が、急に
勝平に
縋り付くようにして言った。
「お父さん! お
土産だい! お土産だい!」
勝平は、
縋り付かれようとする手を、
瑠璃子の手前、きまり悪そうに、払い
退けながら、
「あゝ分っている、分っている。後で、沢山やるからな。さあ!
此方へおいで。お前の新しいお母様が出来たのだからな。
挨拶をするのだよ。」
勝平は、その若者を
拉しながら先に立った。若者は、振り向き/\
瑠璃子の顔をジロ/\と珍らしそうに見詰めていた。
勝平は先きに立って、自分の居間に通った。
「
美奈子も、
茲へおいで。」
彼は、娘を呼び寄せてから、改めて
瑠璃子に挨拶させた後、
勝平はその見るからに
傲岸な顔に、恥しそうな表情を浮べながら、自分の息子を紹介した。
「これが
俺の息子ですよ。
155/390
御覧の
通の人間で、
貴女にさぞ、御面倒をかけるだろうと思いますが、ゼヒ、面倒を見てやっていたゞきたいのです。少し足りない人間ですが、悪気はありませんよ。極く単純で、
此方の言うことは可なり聴くのです。おい
勝彦! これが、お前のお母様だよ。さあ/\挨拶するのだ。」
勝彦は、
瑠璃子の顔を、ジロ/\と見詰めていたが、父にそう
促されると急に気が付いたように、
「お母様じゃないや。お母様は死んでしまったよ。お母様は、もっと
汚い
婆あだったよ。
此人は
綺麗だよ。
此人は美奈ちゃんと同じように、綺麗だよ。お母様じゃないや、ねえそうだろう、美奈ちゃん。」彼は妹に同意を求めるように言った。妹は顔を、火のように赤くしながら、兄を制するように言った。
「お母様と申上げるのでございますよ。お父様のお嫁になって下さるのでございますよ。」
「何んだ、お父様のお嫁! お父様は、ずるいや。
俺に、お嫁を取って
呉れると言っていながら、取って呉れないんだもの。」
彼は、約束した菓子を
貰えなかった子供のように、
すねて見せた。
瑠璃子は、その白痴な息子の不平を聞くと、
勝平が中途から、世間体を
憚って、自分を息子の嫁にと、言い出したことを、思い出した。金で
以て、こんな白痴の妻――
否弄び物に、自分をしようとしたのだと思うと、
勝平に対する
憎悪が又新しく心の中に蒸し返された。
六
勝彦と
美奈子とが、彼等自身の部屋へ去った頃には、夜は十一時に近く、新郎新婦が新婚の床に入るべき時刻は、刻々に迫っていた。
勝平は、
先刻から全力を尽くして、
瑠璃子の
歓心を買おうとしていた。彼は、急に思い出したように、
「おゝそう/\、
貴女に、
結婚進物として、差し上げるものがありましたっけ。」
そう言いながら、彼は自分の背後に据え付けてある小形の金庫から、一束の証書を取り出した。
156/390
「
貴女のお父様に対する債権の証文は、みんな
蒐めた
筈です。さあ、これを
今貴女に進上しますよ。」
彼は、その十五万円に近い証書の金額に、何の執着もないように、無造作に、
瑠璃子の前に押しやった。
瑠璃子は、その一束を、チラリと見たが、
遉にその白い頬に、興奮の色が動いた。彼女は、二三分の間、それを見るともなく見詰めていた。
「あのマッチは、ございますまいか。」彼女は、突如そう
訊いた。
「マッチ?」
勝平は、
瑠璃子の突然な言葉を解し得なかった。
「あのマッチでございますの。」
「あゝマッチ! マッチなら、
幾何でもありますよ。」彼は、そう言いながら、身を
反らして、
其処の
炉棚の上から、マッチの小箱を取って、
瑠璃子の前へ置いた。
「マッチで、何をするのです。」
勝平は不安らしく
訊ねた。
瑠璃子は、その問を無視したように、黙って
椅子から立ち上ると、鉄盤で
掩うてあるストーヴの前に先刻三度目に着替えた
江戸紫の
金紗縮緬の
袖を気にしながら、
蹲まった。
「
貴君、
瓦斯が出ますかしら。」彼女は、
其処で突然
勝平を、見上げながら、
馴々しげな微笑を浴びせた。
初めて、
貴君と呼ばれた
嬉しさに、
勝平は又
相好を崩しながら、
「出るとも、出るとも。
瓦斯は止めてはない筈ですよ。」
勝平が、そう答え
了らない
裡に、
瑠璃子の
華奢な白い手の中に
燐寸は燃えて、
迸り始めた
瓦斯に、軽い爆音を立てゝ、移っていた。
瑠璃子は、その
火影に白い顔をほてらせて、
暫らく立っていたが、ふと身体を
翻すと、卓の上にあった証書を、軽く無造作に、
薪をでも投げるように、
漸く燃え
盛りかけた火の中に投じてしまった。
呆気に取られている
勝平を、
嫣然と振り向きながら、
瑠璃子は言った。
「水に流すと言うことがございますね。
157/390
妾達は、
此の証文を火で焼いたように、これまでのいろいろな感情の行き違いを、火に焼いてしまおうと思いますの……ほゝゝゝ、火に焼く! その方がよろしゅうございますわ。」
「あゝそう/\、火に焼く、そうだ、後へ何も残さないと言うことだな。そりゃ結構だ。今までの事は、スッカリ無いものにして、お互に信頼し愛し合って行く。
貴女が、その気でいて
呉れゝば、こんな嬉しいことはない。」
そう言いながら、
勝平は
瑠璃子に最初の
接吻をでも与えようとするように、その
眸を異常に、輝かしながら、彼女の傍へ近よって来た。
そう言う相手の
気勢を見ると、
瑠璃子は何気ないように、元の椅子に帰りながら、
端然たる【きちんとした】様子に帰ってしまった。
その時に、
扉が開いた。
「
彼方の御用意が出来ましたから。」
女中は、
淑やかにそう言った。
絶体絶命の時が迫って来たのだ。
「じゃ、瑠璃さん!
彼方へ行きましょう。古風に
盃事をやるそうですから、はゝゝゝゝゝ。」
勝平が、
卑しい肉に飢えた
獣のように笑ったとき、
遉に
瑠璃子の顔は
蒼ざめた。
が、彼女の態度は少しも乱れなかった。
「あの、
一寸電話をかけたいと思いますの。父のその後の容体が気になりますから。」
それは、
此の場合突然ではあるが、
尤もな希望だった。
七
「電話なら、女中にかけさせるがいゝ。おい
唐沢さんへ……」
と、
勝平が早くも、女中に命じようとするのを、
瑠璃子は制した。
「いゝえ!
妾が自身で掛けたいと思いますの。」
「自身で、うむ、それなら、
其処に卓上電話がある。」
と、言いながら、
勝平は
瑠璃子の
背後を指し示した。
いかにも、
今迄気が付かなかったが、
其処の小さい
桃花心木の卓の上に、卓上電話が置かれていた。
158/390
瑠璃子は、
淑やかに
椅子から、身を起したとき、彼女の
眉宇の間には、
凄じい決心の色が、アリアリと浮んでいた。
「あのう。番町の二八九一番!」
瑠璃子は、送話器にその紅の色の美しい唇を、間近く寄せながら、低く
呟くように言った。
「番町の二八九一番!」
そう繰り返しながら、送話器を持っている
瑠璃子の白い手は、かすかに/\
顫えていた。彼女は
暫くの間、耳を傾けながら待っていた。やっと相手が出たようだった。
「あゝ
唐沢ですか。
妾瑠璃子なのよ、
貴女は
婆や。」
相手の言葉に聞き入るように、彼女は受話器にじっと、耳を押し付けた。
「そう。あなたの方から、電話を掛けるところだったの。それは、丁度よかったのね。それでお父様の御容体は。」
そういい捨てると、彼女は又じっと聞き入った。
「そう!……それで……入沢さんが、入らしったの!……それで、なるほど……」
彼女は、短い言葉で受け答をしながらも、その白い
面は、だん/\深い
憂慮に包まれて行った。
「えぃ! 重体! 今夜中が……もっと、ハッキリと言って下さい! 聞えないから。なに、なに、お父様は帰って来てはいけないって! でもお医者は何と
仰しゃるの? えぃ! 呼んだ方がいゝって!
妾!
何うしようかしら。あゝあゝ。」
彼女は、もうスッカリ取り
擾してしまったように、身を
悶えた。
「
何うしたのだ。
何うしたのだ。」
勝平は、
遉に色を変えながら、
瑠璃子の傍に、近づいた。
「あのう、お父様が、宅の玄関で二度目の卒倒を致しましてから、容体が急変してしまったようでございますの。
妾こうしてはおられませんわ。ねえ!
一寸帰って来ましてもようございましょう。お願いでございますわ。ねえ
貴方!」
瑠璃子は、涙に
濡れた頬に、
淋しい
哀願の微笑を
湛えた。
「あゝいゝとも、いゝとも。お父様の大事には代えられない。
159/390
直ぐ自動車で行って、しっかり介抱して上げるのだ。」
「そう言って下さると、
妾本当に
嬉しゅうございますわ。」
そう言いながら、
瑠璃子は
勝平に近づいて、
肥った胸に、その美しい顔を
埋めるような
容子をした。
勝平は、心の底から感激してしまった。
「ゆっくりと行っておいで、向うへ行ったら、電話で容体を知らして
呉れるのだよ。」
「直ぐお知らせしますわ。でも、
此方から
訊ねて下さると困りますのよ。父は、
荘田へは決して知らせてはならない。大切な結婚の当夜だから、死んでも知らしてはならないと申しているそうでございますから。」
「うむよし/\。じゃ、よく介抱して上げるのだよ。出来る
丈の手当をして上げるのだよ。」
自動車の用意は、直ぐ整った。
「容体がよろしかったら、今晩中に帰って参りますわ。悪かったら、明日になりましても御免あそばしませ。」
瑠璃子は、自動車の窓から、親しそうに
勝平を見返った。
「もう遅いから、今宵は帰って来なくってもいゝよ。明日は、
俺が容子を見に行って上げるから。」
勝平は、もういつの間にか、親切な
溺愛する夫になり切ってしまっていた。
「そう。それは有難うございますわ。」
彼女は、
爽かな声を残しながら、戸外の
闇に滑り入った。が、自動車が英国大使館前の桜
並樹の
樹下闇を縫うている時だった。彼女の
面には、父の
危篤を
憂うるような表情は、
痕も
止めていなかった。人を思う
通に、
弄んだ
妖女の顔に見るような、必死な薄笑いが、その高貴な面に宿っていた。
護りの騎士
一
名ばかりの妻、これは
瑠璃子が最初考えていたように、
生易しいことではなかった。彼女は、自分の
操を守るために、あらゆる手段と謀計とを
回らさねばならなかった。
結婚後
暫らくは、父の容体を口実に、
瑠璃子は
荘田の家に帰って行かなかった。
160/390
勝平は毎日のように、
瑠璃子を訪れた。日に
依っては、午前午後の二回に、
此の花嫁の顔を見ねば気が済まぬらしかった。
彼は訪問の度
毎に、
瑠璃子の歓心を買うために、高価な
贈物を用意することを、忘れなかった。
それが、ある時は
金剛石入りの指輪だった。ある時は、
白金の腕時計だった。ある時は、真珠の
頸飾だった。
瑠璃子は、そうした贈物を、子供が
玩具を
貰うときのように、無邪気に何の感謝なしに受取った。
が、父の容体を口実に、いつまでも、実家に
止まることは、許されなかった。それは、事情が許さないばかりでなく、彼女の自尊心が許さなかった。敵を避けていることが、勝気な彼女に心苦しかった。もっと、身体を危険に
晒して勇ましく戦わなければならぬと思った。形式的にでも、結婚した以上、形の上
丈では飽くまでも、妻らしくしなければならないと思った。敵の
卑怯に
報いるに卑怯を
以てしてはならない。
此方は、飽くまでも、正々堂々と戦って勝たねばならない。そう思いながら、彼女は
勝平が迎えの自動車に同乗した。
久しぶりに、
瑠璃子と同乗した
嬉しさに、
勝平は訳もなく笑い崩れながら、
「あはゝゝゝゝ。そんなに、
実家を恋しがらなくてもいゝよ。親一人子一人のお父様に別れるのは
淋しいだろう。が、何も心配することはないよ。
俺を
恐がらなくってもいゝよ。
俺だって、こんな顔をしているが、お前さんを取って喰おうと言うのじゃないよ。娘! そうだ、
美奈子に新しい姉が出来たと思って、
可愛がって上げようと思うのだ。あはゝゝゝゝ。」と、
勝平は
何うかして、
瑠璃子の警戒を解こうとして、心にもないことを言った。
勝平の言葉を聴くと、
今迄捗々しい返事もしなかった
瑠璃子は、
甦えったように、快活な調子で言った。
「おほゝゝ、ほんとうに、娘にして下さるの、
妾のお父様になって下さるの!
妾本当にそうお願いしたいのよ。
161/390
ほんとうのお父様になっていたゞきたいのよ。」
そう言いながら、彼女はこぼるゝような
嬌羞を、その
しなやかな
身体一面に
湛えた。
「あゝ、いゝとも、いゝとも。」
勝平は、人の
好い本当の
父親のように
肯いて見せた。
「ほゝゝゝ、それは嬉しゅうございますわ、本当に、
妾を娘にして下さいませ。それも、ほんの少しの間ですの。お約束しますわ。半年、本当に半年でいゝのよ。でも、そうじゃございませんか。
妾、まだ年弱の十八でございましょう。学校を出てから、まだ半年にしかなりませんのですもの。それに、今度の話でございましょう、それに、いろ/\な事件で、興奮して、まだその興奮が続いているのでございましょう。結婚生活に対する何の準備も出来なかったのでございますもの。
貴君の本当の妻になるのには、もう少し心の準備が欲しいと思いますの。
貴君に対する愛情と信頼とを、もっと心の中で、準備したいと思いますの。だから、暫らくの間、本当に
美奈子さんの姉にして置いて下さいませ。『源氏物語』に、
末摘花と言うのがございましょう。あれでございますの。」
そう言いながら、
瑠璃子は
嫣然と笑った。
勝平は、
妖術にでもかゝったように、ぼんやりと相手の美しい唇を見詰めていた。
瑠璃子は相手を人とも思わないように
傍若無人だった。
「ねえ! お父様!
妾の可愛いお父様! そうして下さいませ。」
そう言いながら、彼女はそのスラリとした身体を、
勝平にしなだれるように、寄せかけながら、その白い手を、
勝平の
膝の上に置いて
静に軽く
叩いた。
瑠璃子の
処女の
如く
慎しく
娼婦の如く大胆な
媚態に、心を奪われてしまった
勝平は、自分の答が
何う言うことを約束しているかも考えずに答えた。
「あゝいゝとも、いゝとも。」
二
勝平は心の
裡で思った。どうせ
籠の中に入れた鳥である。その
中には、自分の強い男性としての力で征服して見せる。
162/390
男性の強い腕の力には、
凡ての女性は、
何時の間にか、
掴み
潰されているのだ。彼女も、しばらくの間、自分の
掌中で、小鳥らしい自由を楽しむがいゝ。その
裡に、男性の腕の力がどんなに信頼すべきかが、だん/\分って来るだろう。
勝平はそうした余裕のある心持で、
瑠璃子の
請を
容れた。
が、それが
勝平の違算であったことが、
直ぐ
判った。十日
経ち二十日経つ
裡に、
瑠璃子の美くしさは
勝平の心を、日に夜についで悩した。若い新鮮な女性の肉体から出る
香が
勝平の
旺盛な肉体の、あらゆる感覚を
刺激せずにはいなかった。
その夜も、
勝平は若い妻を、帝劇に伴った。彼はボックスの中に
瑠璃子と並んで、席を占めながら眼は舞台の方から、しば/\帰って来て、愛妻の白い美しい
襟足から、そのほっそりとした
撫肩を伝うて、
膝の上に、
慎しやかに置かれた手や、その手を載せているふくよかな、両膝を、
貪るように見詰めていた。彼は、こうして妻と並んでいると、身も心も溶けてしまうような陶酔を感じた。そうした陶酔の
醒め
際に、彼の
烈しい情火が、ムラ/\と彼の
身体全体を、
嵐のように包むのだった。
瑠璃子は、
勝平のそうした悩みなどを、少しも気が付かないように、
雲雀のように快活だった。彼女は、
勝平との感情の
経緯を、もうスッカリ忘れてしまったように、ほんとうの娘にでも、なりきったように、
勝平に甘えるように
纏わっていた。
「おい瑠璃さん。もう、お父様ごっこも大抵にしてよそうじゃないか、
貴女も、少しは私が判っただろう。はゝゝゝゝ。約束の半年を一月とか二月とかに、縮めて
貰えないものかねえ!」
勝平は、その夜自動車での帰途、冗談のように、妻の
柔かい肩を軽く
叩きながら、
囁いた。
「まあ!
貴君も、
性急ですのねえ。
妾達には約婚時代というものが、なかったのですもの。もっと、こうして楽しみたいと思いますもの。
163/390
何かが来ると言うことの方が、何かが来たと言うことよりも、どんなに楽しいか。それに
妾本当はもっと
処女でいたいのよ。ねえ、いいでしょう。
妾のわがままを、許して下さってもいゝでしょう!」
そう言う言葉と容子とには、
溢れるような
媚びがあった。そうした言葉を、聴いていると、
勝平は、タジ/\となってしまって、一言でも逆うことは出来なかった。
が、その夜、
勝平は自分一人寝室に入ってからも、若い妻のすべてが、彼の眼にも、鼻にも、耳にもこびり付いて離れなかった。眼の中には、彼女の柔い白い肉体が、人魚のように、
艶めかしい
媚態を作って、何時までも何時までも、浮んでいた。鼻には、彼女の肉体の持っている
芳香が、ほのぼのと何時までも、漂っていた。耳には、そうだ! 彼女の快活な
湿りのある声や、
機知に富んだ言葉などが、何時までも何時までも消えなかった。
彼は、そうした
妄想を去って、
何うかして、眠りを得ようとした。が、彼が努力すれば努力するほど、眼も耳も
冴えてしまった。おしまいには、見上げて居る
天井に、幾つも/\妻の顔が、現れて、
媚びのある微笑を送った。
『彼女は、たゞ恥かしがっているのだ。
処女としての恥かしさに過ぎないのだ。それは、
此方から取り去ってやればそれでいゝのだ!』
彼は、そう思い出すと、一刻も自分の寝台にじっと、身体を落ち着けていることが出来なかった。子供らしい
処女らしい恥らいを、そのままに受け入れていた自分が、あまりにお
人好しのように思われ始めた。
彼は、フラ/\として、寝台を離れて、
夜更けの廊下へ出た。
三
廊下へ出て見ると、家人達はみんな寝静まっていた。まだ十月の
半ではあったが、広い洋館の内部には、深夜の冷気が、ひや/\と、流れていた。が、
烈しい情火に狂っている
勝平の
身体には、夜の冷たさも感じられなかった。
164/390
彼は、自分の家の中を、
盗人のように、忍びやかに、夢遊病者のように
覚束なく、
瑠璃子の部屋の方向へ歩いた。
彼女の部屋は、階下に在った。廊下の
灯火は、大抵消されていたが、階段に取り付けられている電灯が、階上にも階下にも、ほのかな光を送っていた。
勝平は、彼女に与えた約束を男らしくもなく、取り消すことが心苦しかった。彼女に示すべき自分の美点は、男らしいと言う事より、外には何もない。彼女の信頼を得るように、男らしく強く堂々と、行動しなければならない。それが、彼女の愛を得る
唯一の方法だと
勝平は心の中で思っていた。それだのに、彼女に
一旦与えた約束を、取り消す。男らしくもなく破約する。が、そうした心苦しさも、
勝平の身体全体に、今潮のように
漲って来る
烈しい欲望を、
何うすることも出来なかった。
階段を下りて、左へ行くと応接室があった。右へ行くと
美奈子の部屋があり、その部屋と並んで
瑠璃子に与えた部屋があった。
瑠璃子の部屋に近づくに従って、
勝平の心には
烈しい動揺があった。それは、年若い少年が初めて恋人の唇を知ろうとする
刹那のような、
烈しい興奮だった。彼は、そうした興奮を抑えて、じっと
瑠璃子の部屋へ忍び寄ろうとした。
丁度、その時に、
勝平は我を忘れて『アッ』と叫び声を挙げようとした。それは、今彼が近づこうとしたその
扉に、一人の人間が紛れもない一人の男性が、ピッタリと身体を寄せていたからである。冷たい
悪寒が、
勝平の身体を流れて、
爪の先までをも
顫わせた。彼は、電気に掛けられたように廊下の真中へ立ち
竦んでしまった。
が、相手は
勝平の近づくのを知っている
筈だのに、ピクリとも身体を動かさなかった。
扉に彫り付けられている木像か何かのように、
闇の中にじっと立ち尽しているようだった。
165/390
『
盗賊!』最初
勝平は、そう叫ぼうかとさえ思ったが、彼の四十男に相当した冷静が彼の口を制したが、その次ぎに、ムラ/\と彼の心を閉したものは、漠然たる
嫉妬だった。一人の男性が、妻の寝室の
扉の前に立っている。それだけで、
勝平の心を狂わすのに十分だった。
彼は、握りしめた
拳を、
顫わしながら、必死になって、一歩々々
扉に近づいた。が、相手は気味の悪いほど、冷静にピクリとも動かない。
勝平が、最後の勇気を鼓して、相手の胸倉を
掴みながら、低く、
「誰だ!」と、
叱した時、相手は
勝平の顔を見て、ニヤリと笑った。それは紛れもなく
勝彦だったのである。
自分の子の
卑しい笑い顔を見たときに、
剛愎【剛胆】な
勝平も、ガンと
鉄槌で殴られたように思った。言い現し方もないような不快な、あさましいと言った感じが、彼の胸の
裡に一杯になった。自分の子があさましかった。が、あさましいのは、自分の子
丈けではなかった。もっと、あさましいのは、自分自身であったのだ。
「お前! 何をしているのだ!
茲で。」
勝平は、低くうめくように
訊いた。が、それは
勝彦に訊いているのではなく、自分自身に訊いているようにも思われた。
勝彦は、離れの日本間の方で寝ている筈なのだ。が、それがもう夜の二時過であるのに、
瑠璃子の部屋の前に立っている。それは、
勝平に取っては、
堪えられないほど、不快なあさましい想像の種だった。
「何をしているのだ! こんな
処で。こんなに遅く。」
何時もは、
馬鹿な息子に対し可なり寛大である父であったが、
今宵に限っては、彼は息子に対して可なり
烈しい
憎悪を感じたのである。
「何をしていたのだ! おい!」
勝平は、鋭い眼で
勝彦を
睨みながら、その肩の所を、グイと
小突いた。
166/390
四
「
茲に何をしていたのだ、
茲に!」
父が、必死になって責め付けているのにも
拘らず、
勝彦はたゞニヤリ/\と、たわいもなく笑い続けた。薄気味のわるい とりとめもなき子の笑いが、丁度自分の恥しい行為を、
嘲笑っているかのように、
勝平には思われた。
彼は、
瑠璃子やまた、
直ぐ次ぎの
扉の
裡に眠っている
美奈子の夢を破らないようにと、気を付けながらも、声がだんだん激しくなって行くのを抑えることが出来なかった。
「おい! こんなに遅く、
茲に何をしていたのだ。おい!」
そう言いながら、
勝平は再び子の肩を突いた。父にそう突き込まれると、白痴相当に、
勝彦は顔を
赤めて、口ごもりながら言った。
「姉さんの所へ来たのだ。姉さんの所へ来たのだ。」姉さん、
勝彦はこの頃、
瑠璃子をそう呼び
慣っていた。
「姉さん! 姉さんの所へ!」
勝平は、そう言いながらも、自分自身地の中へ、入ってしまいたいような、浅ましさと恥しさとを感じた。が、それと同時に、
韮を
噛むような
嫉妬が、ホンの
僅かではあるが、心の
裡に
萌して来るのを、
何うすることも出来なかった。が、父のそうした心持を、
嘲るように、
勝彦は又ニタリ/\と愚かな笑いを、笑いつゞけている。
「姉さんの所へ何をしに来たのだ。何の用があって来たのだ。こんなに夜遅く。」
勝平は、心の中の不愉快さを、じっと抑えながら、
訊く所まで、訊き
質さずにはいられなかった。
「何も用はない。たゞ顔を見たいのだ。」
勝彦は、平然とそれが普通な当然な事ででもあるように言った。
「顔を見たい!」
勝平は、そう口では言ったものの、眼が
眩むように思った。他人は、誰も居合わさない場所ではあったが、自分の顔を、両手で
掩い隠したいとさえ思った。
彼は、もう
此の上、
勝彦に言葉を掛ける勇気もなかった。
167/390
が、今にして、息子のこうした心を、刈り取って置かないと、どんな恐ろしい事が起るかも知れないと思った。彼は不快と恥しさとを制しながら言った。
「おい!
勝彦これから、夜中などに、お姉さんの部屋へなんか来たら、いけないぞ! 二度とこんな事があると、お父様が承知しないぞ!」
そう言いながら、
勝平は、わが子を、恐ろしい眼で
睨んだ。が、子はケロリとして言った。
「だって、お姉さまは、来てもかまわない! と言ったよ。」
勝平は、頭からガンと
殴られたように思った。
「来てもかまわない!
何時、そんな事を言った? 何時そんなことを言った?」
勝平は、思わず
平常の大声を出してしまった。
「何時って、何時でも言っている。部屋の前になら、何時まで立っていてもいゝって、番兵になって呉れるのならいゝって!」
「じゃ、お前は今夜だけじゃないのか。
馬鹿な
奴め! 馬鹿な奴め!」
そう言いながらも、
勝平は子に対して、可なり激しい嫉妬を
懐かずにはいられなかった。
それと同時に、
瑠璃子に対しても、
恨に似た
烈しい感情を持たずにはいられなかった。
「そんな事を姉さんが言った! 馬鹿な!
瑠璃子に訊いて見よう。」
彼は、息子を押し
退けながら、その
背後の
扉を、右の手で開けようとした。が、それは
釘付けにでもされたように、ピタリとして、少しも動かなかった。彼は声を出して、叫ぼうとした。
その途端に、ガタリと
扉が開く音がした。が、開いたのはその
扉ではなくして、
美奈子の寝室の
扉であった。
純白の
寝衣を付けた少女は
まろぶように、父の傍に走り寄った。
「お父様! 何と言うことでございます。何も言わないで、お休みなさいませ。お願いでございます。お姉様にこんなところを見せては親子の恥ではございませんか。」
美奈子の心からの叫びに、打たれたように、
勝平は黙ってしまった。
168/390
勝彦は、相変らず、ニヤリ/\と妹の顔を見て笑っていた。
丁度
此の時、
扉の
彼方の寝台の上に、夢を破られた女は、親子の間の浅ましい
葛藤を、聞くともなく耳にすると、
其美しい顔に、
凄い微笑を浮べると、雪のような
羽蒲団を又再び深々と、
被った。
五
自分の寝室へ帰って来てからも、
勝平は
悶々として、眠られぬ一夜を過してしまった。恋する者の心が、競争者の出現に
依って、
焦り出すように、
勝平の心も、
今迄の落着、冷静、
剛愎の
凡てを無くしてしまった。競争者、それが何と言う
堪らない競争者であろう。それが自分の肉親の子である。肉親の父と子が、一人の女を
回って争っている。親が女の
許へ忍ぶと子が先回りしている。それは、
勝平のような金の外には、物質の外には、何物をも認めないような
堕落した人格者に取っても堪らないほど あさましい【嘆かわしい】ことだった。
もし、
勝彦が普通の頭脳があり、道義の何物かを知っていれば、
罵り恥かしめて、反省させることも容易なことであるかも知れない。(
尤も、
勝平に自分の息子の不道徳を責め得る資格があるか
何うかは疑問であった。)が、
勝彦は盲目的な本能と
烈しい欲望の外は、何も持っていない男である。相手が父の妻であろうが、何であろうが、たゞ美しい女としか映らない男である。それに人並外れた
強力を持っている彼は、どんな乱暴をするかも分らなかった。
その上に、
勝平は自分の失言に対する苦い記憶があった。彼は、一時
瑠璃子を
勝彦の妻にと思ったとき、その事を冗談のように
勝彦に、言い聴かせたことがある。何事をも、
直ぐ忘れてしまう
勝彦ではあったが、事柄が事柄であった
丈に、その愚な頭の
何処かにこびり付かせているかも知れない。そう考えると、
勝平の頭は、
愈重苦しく濁ってしまった。
『そうだ!
勝彦を遠ざけよう。葉山の別荘へでも追いやろう。
169/390
何とか
賺して【なだめすかして】、東京を遠ざけよう。』
勝平はわが子に対して、そうした隠謀をさえ考え始めていた。
興奮と
煩悶とに
労れた
勝平の頭も、四時を打つ時計の音を聴いた後は、
何時しか
朦朧としてしまって、寝苦しい眠りに落ちていた。
眼が覚めた時、それはもう九時を回っていた。朗かな十月の朝であった。青い
紗の窓掛を
透した明るい日の光が、室中に快い明るさを
湛えた。
朝の
爽かな心持に、
勝平は昨夜の不愉快な出来事を忘れていた。
尨大【膨大】な身体を、寝台から、ムクムクと起すと、上
草履を突っかけて、朝の快い空気に吸い付けられたように、
縁側に出た。彼は自分の
広大な、広々と延びている庭園を見ながら、両手を高く
拡げて、快い
欠伸をした。が、彼が拡げた両手を下した時だった。十間ばかり離れた若い
楓の植込の中を、泉水の方へ降りて行く
勝彦の姿を見た。彼に似て、尨大な立派な体格だった。が、歩いて行くのは
勝彦一人ではなかった。
勝彦の大きい身体の
蔭から、時々ちら/\美しい色彩の着物が、見えた。
勝平は、最初、それが
美奈子であることを信じた。
勝彦は白痴ではあったが、
美奈子丈には、やさしい大人しい兄だった。
勝平は何時もの通り
兄妹の散歩であると思っていた。が、植込の中の道が右に折れ、
勝平の視線と一直線になったとき、その男女は相並んで、後姿を
勝平に見せた。女は紛れもなき
瑠璃子だった。
而も彼女の白い、遠目にも、くっきりと白い手は、
勝彦の肩、そうだ、肩よりも少し低い所へ、そっと後から当てられているのだった。
それを見たとき、
勝平は煮えたぎっている湯を、飲まされたような、
凄じい気持になっていた。ニヤリ/\と
悦に入っているらしいわが子の顔が、アリ/\と目に見えるように思った。彼は、
縁側から飛び降りて、わが子の顔を思うさま、殴り付けてやりたいような恐ろしい衝動を感じた。
170/390
が、それにも増して、
瑠璃子の心持が、グッと胸に堪えて来た。
昨夜の騒ぎを知らぬ
筈がない、親子の間の、浅ましい
情景を知らぬ筈がない。隣の部屋の
美奈子さえ、眼を覚しているのに、
瑠璃子が知らない筈はない。知っていながら、
昨夜の今日
勝彦をあんなに近づけている。
そう思うと、
勝平は、
瑠璃子の敵意を感ぜずにはいられなかった。そうだ! 自分が小娘として、つまらない油断や、約束をしたのが悪かったのだ。言わば降伏した敵将の娘を、妻にしているようなものである。美しい顔の下に、どんな害心を
蔵しているかも知れない。
が、そう警戒はしながら、
瑠璃子を愛する心は、少しも減じなかった。それと同時に、眼前の
情景に対する
嫉妬の心は少しも減じなかった。
六
勝平が、
縁側の
欄干に、
釘付けにされながら、二人の後姿が全く見えなくなった若い
楓の林を、じっと見詰めている時に、その林の向うにある泉水の
畔から、
瑠璃子の華やかな笑いが手に取るように聞えて来た。
それは、
雲雀の歌うように、自由な快活な笑いだった。結婚して以来、もう一月以上の日が
経つ内、
勝平に対しては決して笑ったことのないような自由な快活な笑い声であった。
茲からは見えない泉水のほとりで、
縦令馬鹿ではあるにしろ
年齢だけは若い、身体
丈は堂々と立派な
勝彦が、
瑠璃子と相並んで、打ち興じている有様が、
勝平の眼に、マザ/\と映って来るのであった。
彼は苦々しげに、二人に向ってでも吐くように、
唾を
遥かな地上へ吐いてから、その太い
眉に、深い決心の色を
凝めながら、階下へ降りて行った。
勝平は、抑え切れない不快な心持に、悩まされつゝ、罪のない召使を、
叱り飛ばしながら、
漸く顔を洗ってしまうと、苦り切った顔をして、朝の食卓に就いた。いつも朝食を一緒にする
筈の
瑠璃子はまだ庭園から、帰って来なかった。
「奥さんは
何うしたのだ。
171/390
奥さんは!」
勝平は、オド/\している十五六の小間使を、
噛み付けるように叱り飛した。
「お庭でございます。」
「庭から、早く帰って来るように言って来るのだ。
俺が起きているじゃないか。」
「ハイ。」小さい小間使は、
勝平の
凄じい様子に、縮み上りながら、
瑠璃子を呼びに出て行った。
瑠璃子が、入って来れば、
此の押え切れない
憤を、彼女に対しても、
洩そう。白痴の子を
弄んでいるような、彼女の
不謹慎を思い切り責めてやろう。
勝平はそう決心しながら、
瑠璃子が入って来るのを待っていた。
二三分も経たない
裡に、
衣ずれの音が、廊下にしたかと思うと、
瑠璃子は少女のようにいそいそと快活に、
馳け込んで来た。
「まあ! お早う! もう起きていらしったの。
妾ちっとも、知らなかったのよ。お寝坊の
貴方の事だから、どうせ十一時近くまでは大丈夫だと思っていたのよ。
昨夜あんなに遅く帰って来たのに、よくまあ早くお
目覚になったこと。この花美しいでしょう。一番大きくて、一番色の
烈しい花なのよ。
妾これが大好き。」
そう言いながら、
瑠璃子は右の手に折り持っていた、
真紅の大輪のダリヤを、
食卓の上の
一輪挿に投げ入れた。
勝平は、
何うかして
瑠璃子をたしなめようと思いながらも、彼女の快活な言葉と、矢継早の微笑に、面と向うと、彼は我にもあらず、
凡ての言葉が
咽喉のところに、からんでしまうように思った。
「昨夜、よくお眠りになって?
妾芝居で疲れましたでしょう、今朝まで、グッスリと寝入ってしまいましたのよ。こんなに、よく眠られたことはありませんわ、近頃。」
昨夜の騒ぎを、親子三人のあさましい騒ぎを、知っているのか知らないのか、
瑠璃子はその美しい顔の筋肉を、一筋も動かさずに、
華奢な指先で、軽く
箸を動かしながら、
勝平に話しかけた。
172/390
勝平は、心の
裡に、わだかまっている気持を、
瑠璃子に向って、洩すべき
緒を
見出すのに苦しんだ。相手が、昨夜の騒ぎを、少しも知らないと言うのに、それを材料として、話を進めることも出来なかった。
彼は、
瑠璃子には、一言も答えないで、そのいら/\しい気持を示すように、
自棄に
忙しく箸を動かしていた。
勝平の不機嫌を、
瑠璃子は少しも気に止めていないように、平然と、その美しい微笑を続けながら、
「
妾、今日
三越へ行きたいと思いますの。連れて行って下さらない?」
彼女は、プリ/\している
勝平に、
尚小娘か何かのように、甘えかゝった。
「駄目です。今日は東洋造船の臨時総会だから。」
勝平は、
瑠璃子に対して、初めて荒々しい言葉を使った。彼女はその荒々しい語気を跳ね返すように言った。
「あら、そう。それでは、
勝彦さんに一緒に行っていたゞくわ。……いゝでしょう。」
七
勝彦の名が
瑠璃子の唇を
洩れると、
勝平の
巨きい顔は、
益苦り切ってしまった。
相手のそうした表情を少しも眼中に置かないように、
瑠璃子は無邪気にしつこく言った。
「
勝彦さんに、連れて行っていたゞいたらいけませんの。一人だと何だか心細いのですもの。
妾一人だと買物をするのに何だか
定りが付かなくって困りますのよ。
表面丈でもいゝからいゝとか何とか
合槌を打って下さる方が欲しいのよ。」
「それなら、
美奈子と一緒に行らっしゃい。」
勝平は、怒った
牡牛のようにプリ/\しながら、それでも正面から
瑠璃子を
たしなめることが出来なかった。
「
美奈子さん。だって、
美奈子さんは、三時過ぎでなければ学校から、帰って来ないのですもの。それから支度をしていては、遅くなってしまいますわ。」
瑠璃子は、大きい駄々っ子のような表情を見せながら、その癖顔
丈は、微笑を絶たなかった。
勝平は又黙ってしまった。
173/390
瑠璃子は追撃するように言った。
「
何うして
勝彦さんに一緒に行っていたゞいては、いけませんの。」
勝平の顔色は、
咄嗟に変った。その
顳顬の筋肉が、ピク/\動いたかと思うと、彼は
顫える手で
箸を降しながら、それでも声
丈けは、平静な声を出そうと努めたらしかったが、変に上ずッてしまっていた。
「
勝彦! 勝彦 勝彦と、
貴女はよく口にするが、
貴女は
勝彦を一体何だと思っているのです。もう、一月以上
此家にいるのだから、気が付いたでしょう。親の身として、口にするさえ恥かしいが、あれは白痴ですよ。白痴も白痴も、御覧の
通東西も弁じない白痴ですよ。あゝ言う者を三越に連れて行く。それは
此の
荘田の恥、
荘田一家の恥を、世間へ広告して歩くようなものですよ。
貴女も、動機は
兎も
角、
一旦此の家の人となった以上、こう言う
馬鹿息子があると言うことを、広告して下さらなくってもいゝじゃありませんか。」
勝平は、結婚して以来、初めて荒々しい言葉を、
瑠璃子に対して吐いた。が、
象牙の箸を
飯椀の中に止めたまゝ、じっと聴いていた
瑠璃子は、
眉一つさえ動かさなかった。
勝平の言葉が終ると、彼女は
駭いたように、眼を丸くしながら、
「まあ! あんなことを。そんな
邪推していらっしゃるの。
妾勝彦さんを馬鹿だとか白痴だとか
賤しめたことは、一度もありませんわ。あんな無邪気な純な方はありませんわ。それは、少し足りないことは足りないわ。それは、お父様の前でも申し上げねばなりません。でも、あんなに正直な方に、
妾初めてお目にかゝりましたのよ。それに
妾の言ったことなら、何でもして下さるのですもの。
174/390
此間、お家が広いので、夜寝室の中に、一人いると何だか寂しく心細くなると、申しますと、
勝彦さんは、それなら毎晩部屋の外で番をしてやろうと
仰しゃるのですよ、
妾冗談だとばかり、思っていますと、一昨夜二時過ぎに、廊下に人の
気勢がするので、
扉を開けて見ますと、
勝彦さんが立っていらっしゃるじゃありませんか。それが、丁度中世紀の
騎士が、貴婦人を
護る時のように、
厳然として立っていらっしゃるのですもの。
妾可笑しくもあれば、有難くも思ったわ。
妾此の頃、
智恵のある
怜悧な方には、飽き/\していますの。また、その智恵を、人を苦しめたり
陥れたりする事に使う人達に、飽き/\していますのよ。また、人が
傷け合ったり
陥れ合ったりする世間その物にも、
愛想が尽きていますのよ。
妾、
勝彦さんのような、のんびりとした太古の心で、生きている方が、大好きになりましたのよ。
貴方の前でございますが、
何うして
勝彦さんを捨てゝ、貴方を選んだかと思うと、後悔していますのよ。おほゝゝゝゝゝ。」
爽かな
五月の流が、
蒼い野を走るように、
瑠璃子は雄弁だった。黙って聴いていた
勝平の顔は、
怒と
嫉妬のために、黒ずんで見えた。
余りに脆き
一
勝平は、冗談かそれとも
真面目かは分らないが、人を
馬鹿にしているように、からかっているように、
勝彦を賞める
瑠璃子の言葉を聞いていると、思わずカッとなってしまって、手に持っている
茶碗や
箸を、彼女に
擲つけてやりたいような
烈しい
嫉妬と怒とを感じた。が、口先ではそんな
嫌がらせを言いながらも、顔
丈は
此の頃の秋の空のように、澄み渡った
麗かな
瑠璃子を見ていると、不思議に手が
竦んで、茶碗を投げ付くることは愚か、一指を触るゝことさえも、
為し得なかった。
が、
勝平は心の中で思った。
此のままにして置けば、
瑠璃子と
勝彦とは、日増に親しくなって行くに違いない。
175/390
そして自分を苦しめるのに違いない。少くとも、当分の間、自分と
瑠璃子とが本当の夫婦となるまで、
何うしても二人を引き離して置く必要がある。
勝平は、
咄嗟にそう考えた。
「あはゝゝゝゝ。」彼は突然取って付けたように笑い出した。「まあいゝ!
貴女がそんなに馬鹿が好きなら連れて行くもよかろう。
貴女のようなのは、
天邪鬼と言うのだ。あはゝゝゝゝ。」
勝平は、嫉妬と
憤怒とを心の底へと、押し込みながら、何気ないように笑った。
「
何うも、有難う。やっと、お許しが出ましたのね。」
瑠璃子も、サラリと何事もなかったように微笑した。
その時に、
勝平は急に思い付いたように言った。
「そう/\。
貴女に話すのを忘れていた。
此間中 頭が重いので、
一昨日、
近藤に
診て
貰うと、神経衰弱の気味らしいと言うのだ。海岸へでも行って、少し静養したら
何うだと言うのだがね、そう言われると、
俺も
此の七月以来会社の創立や何かで、毎日のように飛び回っていたものだからね、精力主義の
俺も可なりグダ/\になっているのだ。神経衰弱だなんて、大したこともあるまいと思うが、まあ
暫らく葉山へでも行って、一月ばかり遊んで来ようかと思うのだ。
尤も、
彼処からじゃ、毎日東京に通っても訳はないからね。それに就いては、是非
貴女に一緒に行っていたゞきたいと思うのだがね。」
勝平は、熱心に、
退引ならないように
瑠璃子に言った。
「葉山へ!」と言ったまゝ、
遉に彼女は二の句を言い
淀んだ。
「そうです! 葉山です。
彼処に、林
子爵が持っていた別荘を、
此春譲って貰ったのだが、
此夏
美奈子が避暑に行った
丈で、
俺はまだ二三度しか
宿っていないのだ。秋の方が、
静でよいそうだから、ゆっくり滞在したいと思うのだが。」
勝平は、落着いた口調で言った。葉山へ行くことは、何の意味もないように言った。
176/390
が、
瑠璃子には、その言葉の奥に潜んでいる
勝平のよからぬ意思を、明かに読み取ることが出来た。葉山で二人
丈になる。それが
何う言う結果になるかは
瑠璃子には可なりハッキリ分るように思った。が、彼女はそうした危機を、未然に避くることを、
潔しとしなかった。どんな危機に陥っても、自分自身を立派に守って見せる。彼女には、女ながらそうした
烈しい最初の意気が、ピクリとも揺いでいなかった。
「結構でございますわ、
妾も、そんな所で静かな生活を送るのが大好きでございますのよ。」
彼女は、その清麗な面に、少しの曇も見せないで、
爽かに答えた。
「あゝ行って
呉れるのか。それは有難い。」
勝平は、心から
嬉しそうにそう言った。葉山へさえ、伴って行けば、当分
勝彦と引き離すことが出来る上に、
其処では召使を除いた外は、
瑠璃子と二人切りの生活である。
殊に、
鍵のかかり得るような西洋室はない。
瑠璃子を肉体的に支配してしまえば、高が一個の少女である。普通の
処女がどんなに嫌い抜いていても、結婚してしまえば、男の腕に
縋り付くように、彼女も
一旦その肉体を征服してしまえば、余りに
脆き一個の女性であるかも知れない。
勝平はそう思った。
「それなら丁度ようございますわ。
三越へ行って、
彼方で入用な品物を
揃えて参りますわ。」
彼女は、身に迫る危険な場合を、少しも意に介しないように、
寧ろいそ/\としながら言った。
二
愛し合った夫であるならば、それは楽しい新婚旅行である
筈だけれども、
瑠璃子の場合は、そうではなかった。
勝平と二人
限で、東京を離れることは、彼女に取っては死地に入ることであった。東京の
邸では、人目が多い
丈に、
勝平も
一旦与えた約束の手前、理不尽な振舞に出ることは出来なかったが、葉山では事情が違っていた。
今迄は敵と戦うのに、地の利を得ていた。小さいながらも、彼女の
城郭があった。
177/390
殊に盲目的に、彼女を
護っている
勝彦と言う番兵もあった。が、葉山には、何もなかった。彼女は
赤手【素手】にして、敵と渡り合わねばならなかった。勝敗は、天に
委せて、
兎に
角に、最後の必死的な戦いを、戦わねばならなかった。
そうした不安な期待に、心を
擾されながらも、彼女はいろ/\と、別荘生活に必要な準備を整えた。彼女は、当座の着替や化粧道具などを、一杯に詰め込んだ大きなトランクの底深く、
一口の短剣を入れることを忘れなかった。それが、夫と二人
限りの別荘生活に対する第一の準備だった。
父の
男爵が、
瑠璃子の
烈しい
執拗な希望に、
到頭動かされて、不承々々に結婚の承諾を与えて、最愛の娘を、憎み
賤しんでいた男に渡すとき、男爵は娘に最後の贈り物として、一口の短剣を手渡した。
「これは、お前のお母様が家へ来るときに持って来た守り刀なのだ。昔の女は、常に
懐刀を離さずに、それで自分の
操を守ったものだ。
貴女も普通の結婚をするのなら、こんなものは不用だが、今度のような結婚には、是非必要かも知れない。これで、
貴女の現在の決心を、しっかりと守るようになさい。」
父の言葉は簡単だった。が、意味は深かった。彼女はその
匕首を身辺から離さないで、最後の最後の用意としていた。そうした最後の用意が、
如何なる場合にも、彼女を勇気付けた。
牡牛のように
巨きい
勝平と相対していながら、彼女は一度だって、
怯れたことはなかった。
瑠璃子が
暫らく東京を離れると言うことが分ると、一番に驚いたのは
勝彦だった。彼は
瑠璃子が準備をし始めると、自分も一緒に行くのだと言って、父の大きいトランクを引っ
張出して来て、自分の着物や持物を
滅茶苦茶に詰め込んだ。おしまいには、自分の使っている洗面器までも、詰め込んで召使達を笑わせた。彼は、
瑠璃子に捨てゝ置かれないようにと、一瞬の間も
瑠璃子を見失わないように
後へ/\と付き
纏った。
178/390
それを見ると、
勝平は
眉を
顰めずにはいられなかった。
出立の朝だった。自分が捨てゝ置かれると言うことが分ると、
勝彦は狂人のように
暴れ出した。毎年一度か二度は、発作的に狂人のようになってしまう彼だった。彼は
瑠璃子と父とが自動車に乗るのを見ると、自分も
跣足で
馳け降りて来ながら、
扉を無理矢理に開けようとした。執事や書生が三四人で抱き止めようとしたが、
馬鹿力の強い彼は、後から抱き付こうとする男を、二三人も
其処へ振り飛ばしながら、自動車に
縋り付いて離れなかった。
白痴でありながらも、必死になっている顔色を見ると、
瑠璃子は可なり心を動かされた。主人に慕い
纏わって来る動物に対するような いじらしさを、
此の
無知な
勝彦に対して、
懐かずにはいられなかった。
「あんなに行きたがっていらっしゃるのですもの。連れて行って上げてはいけないのですか。」
瑠璃子は夫を振返りながら言った。その微笑が、
一寸皮肉な色を帯びるのを、彼女自身制することが出来なかった。
「馬鹿な!」
勝平は、苦り切って、一言に
斥けると、自動車の窓から顔を出しながら言った。
「遠慮をすることはない。グン/\引き離して
彼方へ連れて行け。暴れるようだったら、
何時かの部屋へ監禁してしまえ。当分の間、監視人を付けて置くのだぞ、いゝか。」
勝平は、
叱り付けるように怒鳴ると、丁度
勝彦の
身体が、多勢の力で車体から引き離されたのを
幸に、運転手に発車の合図を与えた。
動き出した車の中で
瑠璃子は
一寸居ずまいを正しながら、
背後に続いている
勝彦のあさましい怒号に耳を
掩わずにはいられなかった。
三
葉山へ移ってから、二三日の間は、
麗かな秋
日和が続いた。東京では、とても見られないような薄緑の朗かな空が、山と海とを
掩うていた。海は毎日のように静かで波の立たない海面は、時々緩やかな
うねりが滑かに起伏していた。海の色も、真夏に見るような
濃藍の色を失って、それ
丈親しみ
易い軽い
藍色に、はる/″\と続いていた。その
端に、
伊豆の連山が、淡くほのかに晴れ渡っているのだった。
十月も終に近い葉山の町は、洗われたように静かだった。どの別荘も、どの別荘も堅く閉されて人の
気勢がしなかった。
御用邸に近い海岸にある
荘田別荘は、裏門を出ると、もう
其処の白い砂地には、
崩れた波の名残りが、白い
泡沫を立てているのだった。
勝平は、葉山からも毎日のように、東京へ通っていた。夫の留守の間、
瑠璃子は
何人にも
煩わされない静寂の
裡に、浸っていることが出来た。
瑠璃子はよく、一人海岸を散歩した。人影の
稀な海岸には、自分一人の影が、寂しく砂の上に映っていた。
遥に/\悠々と
拡がっている海や、その上を
限なく広大に
掩うている秋の朗かな大空を見詰めていると、人間の世のあさましさが、しみ/″\と感ぜられて来た。自分自身が、
復讐に
狂奔して、心にもない偽りの結婚をしていることが、あさましい罪悪のように思われて、とりとめもなく、心を苦しめることなのであった。
葉山へ移ってから、三四日の間、
勝平は
瑠璃子を安全地帯に移し得たことに満足したのであろう。人のよい
好々爺になり切って、夕方東京から帰って来る時には、
瑠璃子の心を
欣すような品物や、おいしい食物などをお土産にすることを忘れなかった。
葉山へ移ってから、丁度五日目の夕方だった。
其日は、
午過ぎから空模様があやしくなって、海岸へ打ち寄せる波の音が、刻一刻
凄じくなって来るのだった。
海に
馴れない
瑠璃子には、高く海岸に打ち寄せる波の音が、何となく不安だった。別荘番の
老爺は暗く
澱んでいる海の上を、低く飛んで行く雲の脚を見ながら、『
今宵は
時化かも知れないぞ。』と、幾度も/\口ずさんだ。
夕刻になるに従って、風は段々吹き
募って来た。暗く暗く暮れて行く海の
面に、白い大きい
浪がしらが、後から/\走っていた。
瑠璃子は
硝子戸の
裡から、不安な
眉をひそめながら、海の上を見詰めていた。
烈しい風が砂を
捲いて、パラ/\と
硝子戸に打ち突けて来た。
「あゝ早く雨戸を閉めておくれ。」
瑠璃子は、
狼狽して、召使に命じると、ピッタリと閉ざされた部屋の中に、今宵に限って、妙に薄暗く思われる
電灯の下に、小さく縮かまっていた。人間同士の争いでは、非常に強い
瑠璃子も、こうした自然の脅威の前には、普通の女らしく
臆病だった。海岸に立っている、地形の
脆弱な家は、時々今にも吹き飛ばされるのではないかと思われるほど、打ち揺いだ。
179/390
海岸に砕けている波は、今にも
此の家を
呑みそうに
轟々たる響を立てゝいる。
瑠璃子には、結婚して以来、初めて夫の帰るのが待たれた。
何時もは、夫の帰るのを考えると、妙に
身体が、引き
緊ってムラ/\とした
悪感が、胸を
衝いて起るのであったが、今宵に限っては、不思議に夫の帰るのが待たれた。
勝平の鉄のような
腕が何となく頼もしいように思えた。
逗子の停車場から自動車で、危険な海岸伝いに帰って来ることが何となく
危まれ出した。
「こう荒れていると、
鐙摺のところなんか、危険じゃないかしら。」と女中に対して
瑠璃子は、我にもあらず、そうした心配を口に出してしまった。
その途端に、吹き
募った
嵐は、可なり
広壮な建物を打ち揺すった。鎖で地面へ
繋がれている
廂が、吹きちぎられるようにメリ/\と音を立てた。
四
「こんなに荒れると、本当に自動車はお危のうございますわ。一層こんな晩は、
彼方でお
宿りになると およろしいので ございますが。」
女中も主人の身を案ずるようにそう言った。が、
瑠璃子は是非にも帰って
貰いたいと思った。
何時もは、顔を見ている
丈でも、ともすればムカ/\して来る
勝平が、何となく頼もしく力強いように感ぜられるのであった。
日が、トップリ暮れてしまった頃から、
嵐は
益吹き
募った。海は
頻りに
轟々と
吼え狂った。波は岸を超え、常には
干乾びた砂地を走って、別荘の
土堤の根元まで押し寄せた。
「潮が満ちて来ると、もっと波が
ひどくなるかも知れねえぞ!」
海の模様を見るために出ていた、別荘番の
老爺は、
漆のように暗い戸外から帰って来ると、不安らしく
呟いた。
「まさか、
此間のような
大暴風雨にはなりますまいね。」
女中も、それに釣り込まれたように、オド/\しながら
訊いた。皆の頭に、まだ
一月にもならない十月一日の暴風雨の記憶がマザ/\と残っていた。
180/390
それは、東京の深川本所に
大海嘯を起して、多くの人命を奪ったばかりでなく、
湘南各地の別荘にも、可なりヒドイ
惨害を
蒙らせたのであった。
「まさか
先度のような
大暴風雨にはなるまいかと思うが、時刻も風の
方向もよく似ているでなあ!」
老爺は、心なしか
瑠璃子達を
脅すように、首を
傾げた。
夜に入ってから、間もなく雨戸を打つ雨の音が、ボツリ/\と聞え出したかと思うと、それが
忽ち盆を
覆すような大雨となってしまった。天地を洗い流すような雨の音が、
瑠璃子達の心を一層不安に
充たしめた。
恐ろしい風が、グラ/\と家を吹き揺すったかと思う途端に、
電灯がふっと消えてしまった。こうした場合に、
灯火の消えるほど、心細いものはない。女中は
闇の中から手探りにやっと、
洋灯を探し当てゝ火を点じたが、ほの暗い光は、一層
瑠璃子の心を
滅入らしてしまった。
暗い
灯火の下に
蒐まっている
瑠璃子と女中達を、もっと脅かすように、風は空を狂い回り、波は
断なしに岸を
噛んで殺到した。
風は少しも緩みを見せなかった。雨を交えてからは、有力な味方でもが加わったように、
益々暴威を加えていた。風と雨と波とが、三方から人間の作った自然の邪魔物を打ち砕こうとでもするように力を
協せて、
此建物を強襲した。
ガラ/\と、
何処かで物の砕け落ちる音がしたかと思うと、それに続いて海に面している
廂が吹き飛ばされたと見え、ベリ/\と言う
凄じい音が、家全体を震動した。
今迄は、それでも、
慎しく態度の落着を失っていなかった
瑠璃子もつい度を失ったように立ち上った。
「
何うしようかしら、今の
裡に避難しなくてもいゝのかしら。」
そう言う彼女の顔には、恐怖の影がアリ/\と動いていた。人間同士の交渉では、烈女のように、強い彼女も、自然の恐ろしい現象に対しては、女らしく弱かった。
女中達も、色を失っていた。
181/390
女中は声を挙げて別荘番の
老爺を呼んだけれども、風雨の音に
遮られて、別荘番の家までは、届かないらしかった。
ベリ/\と言う廂の飛ぶ音は、
尚続いた。その度に、家がグラ/\と今にも吹き飛ばされそうに揺いだ。
丁度、
此の時であった。
瑠璃子の心が、不安と恐怖のどん底に陥って、
藁にでも
縋り付きたいように思っている時だった。凄じい風雨の音にも紛れない、勇ましい自動車の
警笛が、暗い闇を
衝いてかすかに/\聞えて来た。
「あゝお帰りになった!」
瑠璃子は
甦えったように、思わず歓喜に近い声を挙げた。その声には、夫に対する妻としての信頼と愛とが
籠っていることを否定することが出来なかった。
五
風雨の
烈しい音にも消されずに、
警笛の響は
忽ちに近づいた。門内の
闇がパッと明るく照されて、その光の
裡に雨が銀糸を
列ねたように降っていた。
瑠璃子と女中達二人とは、その
燦然と輝く自動車の
頭光に
吸われたように、玄関へ
馳け付けた。
微醺を帯びた
勝平は、その赤い
巨きい顔に、
暴風雨などは、少しも心に止めていないような、悠然たる微笑を
湛えながら、
のっそりと車から降りた。
「お帰りなさいまし、まあ大変でございましたでしょうね。お道が。」
瑠璃子のそうした言葉は、
平素のように形式
丈のものではなく、それに相当した感情が、ピッタリと動いていた。
「なに、大したことはなかったよ。それよりもね、
貴女が
蒼くなっているだろうと思ってね。
此間の
大暴風雨で、みんなビク/\している時だからね。いや、
鎌倉まで一緒に乗り合わして来た友人にね、
此の
暴風雨じゃ道が大変だから、鎌倉で
宿まって行かないかと、言われたけれどもね。やっぱり
此方が心配でね。是非葉山へ行くと言ったら、冷かされたよ。美しい若い細君を
貰うと、それだから困るのだと、はゝゝゝゝゝ。」
182/390
凄じい風の音、
烈しい雨の音を、聞き流しながら、
勝平は愉快に
哄笑した。自然の脅威を跳ね返しているような
勝平の態度に接すると、
瑠璃子は心強く頼もしく思わずにはいられなかった。男性の強さが、今始めて感ぜられるように思った。
「
妾何うしようかと思いましたの。
廂がベリベリと吹き飛ばされるのですもの。」
瑠璃子は、まだ不安そうな眼付をしていた。
「なに、心配することはない。十月一日の
暴風雨の時だって、
土堤が少しばかり、崩された
丈なのだ。あんな大暴風雨が、二度も三度も続けて吹くものじゃない。」
勝平は、
瑠璃子が後から、着せかけた
褞袍に、くるまりながら、どっかりと腰を降ろした。
が、
勝平のそうした言葉を、裏切るように、風は刻々吹き募って行った。可なり、ピッタリと閉されている雨戸
迄が、今にも吹き外されそうに、バタ/\と鳴り響いた。
「さあ! お酒の用意をして下さらんか、こうした晩は、お酒でも飲んで、
大に暴風雨と戦わなければならん、はゝゝゝ。」
勝平は、暴風雨の音に、
怯えたように耳を
聳てゝいる
瑠璃子にそう言った。
酒盃の用意は、整った。
勝平は吹き
荒ぶ暴風雨の音に、耳を傾けながら、チビリ/\と
盃を重ねていた。
「
妾、本当に早く帰って下さればいゝと思っていましたのよ。男手がないと何となく心細くってよ。」
「はゝゝ、
瑠璃子さんが、
俺を心から待ったのは
今宵が始めてだろうな、はゝゝゝゝ。」
勝平は機嫌よく哄笑した。
「まあ! あんなことを、毎日心からお待ちしているじゃありませんか。」
瑠璃子は、ついそうした
心易い言葉を出すような心持ちになっていた。
「
何うだか。分りゃしませんよ。
老爺め、なるべく遅く帰って来ればいゝのに。こう思っているのじゃありませんか。はゝゝゝゝ。」
瑠璃子の今宵に限って、温かい態度に、
勝平は心から
悦に入っているのだった。
183/390
「それも、無理はありません。
貴女が内心
俺を嫌っているのも、全く無理はありません。当然です、当然です。
俺も嫌がる
貴女を、
何時までも名ばかりの妻として、
束縛していたくはないのです。これが、どんな恐ろしい罪かと言うことが分っているのです。所がですね。初めはホンの意地から、結婚した
貴女が、
一旦形式
丈でも
同棲して見ると、……一旦
貴女を傍に置いて見ると、死んでも
貴女を離したくないのです。いや、死んでも
貴女から離れたくないのです。」
余程酒が進んで来たと見え、
勝平は
管を
捲くようにそう言った。
六
風は
益々吹き荒れ雨は益々降り募っていた。が、
勝平は戸外のそうした物音に、少しも気を取られないで、
瑠璃子が
酌いでやった酒を、チビリ/\と
嘗めながら、熱心に言葉を継いだ。
「まあ、簡単に言って見ると、スッカリ心から
貴女に
惚れてしまったのです!
俺は今年四十五ですが、
此年まで、本当に女と言うものに心を動かしたことはなかったのです。
勝彦や
美奈子の母などとも、たゞ、
在来の結婚で、給金の
入らない高等な女中をでも、
傭ったように考うて、接していたのです。金が出来るのに従って、金で自由になる女とも沢山接して見ましたが、どの女もどの女も、たゞ
玩具か何かのように、
弄んでいたのに過ぎないのです。
俺は女などと言うものは、酒や
煙草などと同じに、我々男子の事業の疲れを慰めるために存在している者に過ぎないとまで高を
括っていたのです。所がです、俺のそうした考えは
貴女に会った瞬間に、見事に打ち破られていたのです。男子の
為に作られた女でなくして、女自身のために作られた女、俺は
貴女に接していると、
直ぐそう言う感じが頭に浮かんだのです。男の玩具として作られた女ではなくして、男を支配するために作られた女、俺は
貴女を、そう思っているのです。
184/390
それと一緒に、今まで女に対して
懐いていた
侮蔑や軽視は、
貴女に対してはだん/\無くなって行くのです。その反対に、一種の尊敬、まあそう言った感じが、だん/\胸の中に
萌して来たのです。結婚した当座は、何の
此の小娘が、俺を嫌うなら嫌って見ろ! 今に、征服してやるから。と、こう思っていたのです。所が、今では
貴女の前でなら、どんなに頭を下げても、いいと思い出したのです。
貴女の愛情を、得るためになら、どんなに頭を下げても、いゝと思い始めたのです。
何うです、
瑠璃子さん! 俺の心が少しはお分りになりますか。」
勝平は、そう言って言葉を切った。酔ってはいたが、その顔には、一本気な
真面目さが、アリ/\と動いていた。こうした心の告白をするために、
故意と
酒盃を重ねているようにさえ、
瑠璃子に思われた。
「
俺は、世の中に金より貴いものはないと思っていました。俺は金さえあれば、どんな事でも出来ると思っていました。実際
貴女を妻にすることが、出来た時でさえ、金があればこそ、
貴女のような美しい名門の子女を、自分の思い
通にすることが出来るのだと思っていたのです。が、俺が
貴女を、金で買うことが出来たと
想ったのは、俺の
考違でした。金で俺の買い得たのは、たゞ妻と言う名前
丈です。
貴女の
身体をさえ、まだ自分の物に、することが出来ないで苦しんでいるのです。まして、
貴女の愛情の
断片でも、俺の自由にはなっていないのです。
俺は
貴女の俺に対する態度を見て、つく/″\
悟ったのです。俺の全財産を投げ出しても、
貴女の心の
断片をも、買うことが出来ないと言うことを、つく/″\悟ったのです。が、そう思いながらも、俺は
貴女を思い切ることが出来ないのです。俺は金で買い損ったものを、俺の真心で、買おうと思い立ったのです。いや、買うのではない、
貴女の前に
跪いて、買うことの出来なかったものを哀願しようとさえ思っているのです。
185/390
また、そうせずにはいられないのです。
先刻も申しました
通、もう一刻も
貴女なしには生きられなくなったのです。」
変に言葉までが改まった
勝平は、恋人の前に
跪いている若い青年か、何かのように、激していた。彼の
巨きい真赤な顔は、
何処にも
偽りの影がないように、真面目に緊張していた。彼は大きい眼を
刮きながら、
瑠璃子の顔を、じっと見詰めていた。敵意のある凝視なら、
睨み返し得る
瑠璃子であったが、そうした火のような熱心の凝視には
却って
堪えかねたのであろう、彼女は、
眩しいものを避けるように、じっと顔を
俯けた。
「
何うです!
瑠璃子さん!
俺の心を、少しは了解して下さいますか。」
勝平の声は、
瑠璃子の心臓を
衝くような力が
籠っていた。
七
酒の力を借りながら、その本心を告白しているらしい
勝平の言葉を、聴いていると、今までは
獣的な、俗悪な男、精神的には救われるところのない男だと思い捨てゝいた
勝平にも、人間的な善良さや弱さを、感ぜずにはいられなかった。
あれ
丈、
傲岸で黄金の万能を、主張していた男が、金で買えない物が、世の中に
儼として存在していることを、
潔く認めている。金では、人の心の愛情の
断片をさえ、買い得ないことを告白している。彼は、今自分の非を悟って、
瑠璃子の前に平伏して彼女の愛を哀願している。敵は
脆くも、
降ったのだ。そうだ! 敵は余りにも、脆くも降ったのだ、
瑠璃子は心の
裡で思わず、そう叫ばずには いられなかった。
「
瑠璃子さん!
俺はお願いするのだ。俺は、俺の前非を悔いて
貴女に、お願いするのじゃ。
貴女は、心から俺の妻になって下さることは出来んでしょうか。これまでの偽りの結婚を、俺の真心で
浄めることは出来んでしょうか。俺は、この結婚を
浄めるために、どんなことをしてもいゝ。俺の財産を、みんな投げ出してもいゝ。いや俺の
身体も
生命もみんな投げ出してもいゝ。
186/390
俺は、
貴女から、夫として信頼され愛されさえすれば、どんな犠牲を払ってもいゝと思っているのです。俺は、
先刻自動車から降りて、
貴女と顔を見合せた時、俺は結婚して以来初めて幸福を感じたのです。今日
丈は、
貴女が心から俺を迎えて
呉れている。
貴女の笑顔が心からの笑顔だと思うと、俺は初めて結婚の幸福を感じたのです。が、それも落着いて考えて見ると、
貴女が俺を喜んで迎えて呉れたのも、夫としてではない、たゞこんな恐ろしい晩に必要な男手として喜んでいるのだと思うと、又急に情なくなるのです。俺が
貴女を、
賤しい手段で、妻にしたと言う罪を、俺の
貴女に対する現在の真心で
浄めさせて下さい!」
勝平は、酒のために、気が狂ったのではないかと思われるほどに
激高していた。
瑠璃子は相手の激しい情熱に
咽せたように
何時の間にか知らず/\、それに動かされていた。
「
瑠璃子さん、
貴女も今までの事は、心から水に流して、
俺の本当の妻になって下さい。
貴女が心ならずも、
俺の妻になったことは、不幸には違いない。が、
一旦妻になった以上、
貴女が肉体的には、妻でないにしろ、世間では誰も、そうは思っていないのです。社会的に言えば、
貴女は飽くまでも、荘田
勝平の妻です。
貴女も、こうした羽目に陥ったことを、不幸だと
諦めて、心から俺の妻になって下さらんでしょうか。」
勝平の眼は、熱のあるように輝いていた。
瑠璃子も、相手の熱情に、ついフラ/\と動かされて、思わず感激の言葉を口走ろうとした。が、その時に彼女の冷たい理性が、やっとそれを制した。
『相手が余りに
脆いのではない! お前の方が余りに
脆いのではないか。お前は、最初のあれほど
烈しい決心を忘れたのか。正義のために、私憤ではなくして、むしろ公憤のために、相手を倒そうと言う強い決心を忘れたのか。
勝平の口先
丈の
懺悔に動かされて、余りに
脆くお前の決心を捨てゝしまうのか。
187/390
お前は
勝平の態度を疑わないのか。彼は、お前に降伏したような様子を見せながら、お前を肉体的に、征服しようとしているのだ。
兜を脱いだような風を
装いながら、お前に飛び付こうとしているのだ。お前が、
勝平の告白に感激して、お前の手を与えて御覧! 彼は、その手を
戴くような風をしながら、何時の間にかお前を
蹂み
躙ってしまうのだ。お前は敵の暴力と戦うばかりでなく、敵の甘言とも戦わなければならぬ。敵は、お前の
誇に
媚びながら、逆にお前を征服しようとしているのだ。余りに
脆いのは敵でなくしてお前だ。』
瑠璃子の冷たい理性は、覚めながらそう叫んだ。彼女は、ハッと眼が覚めたように、居ずまいを正しながら言った。
「あら、あんな事を
仰しゃって? 最初から、本当の妻ですわ。心からの妻ですわ。」
そう言いながら、彼女は冷たい、
然しながら、美しい笑顔を見せた。
嵐を衝いて
一
勝平は、
瑠璃子の言葉だけは、打ち解けていても、笑顔は氷のように冷たいのを見ると、絶望したように言った。
「あゝ
貴女は、
何うしても
俺を理解して下さらぬのじゃ。
俺の最初の罪を
何うしても許して下さらぬのじゃ。
貴女は、俺と
勝彦とを、
操って俺に、畜生道の苦しみを見せようとしているのじゃ。よい、それならよい! それならそれでよい!
貴女が、
何時までも俺を
敵と見るのなら、俺も、俺も敵になっていてもいゝ。俺が
貴女の前に、
跪いてこれほどお願しているのに、
貴女は俺の真心を受け
容れて下さらんのじゃから。」
もう
先刻から、一升以上も飲み
乾している
勝平は、濁った
眸を見据えながら、
威丈高に
瑠璃子にのしかゝるような態度を見せた。相手が
下手から出ると、ついホロリとしてしまう
瑠璃子であったが相手が正面からかゝって
呉れゝば、一足だって踏み
退く彼女ではなかった。
188/390
相手の態度が急変すると、
瑠璃子は先刻の
勝平の神妙な態度は、たゞ自分を説き落すための、偽りの手段であったことが、ハッキリしたように思った。
「あら、あんな事を
仰しゃって、
貴君の真心は、
初から分っているじゃありませんか。」
瑠璃子は、相手の
脅を軽く受け流すように、
嫣然と笑った。
「あゝ、
貴女のその笑顔じゃ。それは俺を悩ますと同時に、
嘲けり恥しめ
罵しっているのじゃ。あゝ俺は
貴女のその笑顔に
堪えない。俺は
貴女のその笑顔を、初はどんなに楽しんでいたか分らないが、だん/\見ていると、
貴女のその美しい笑顔の皮一つ下には、俺に対する
憎悪と
嘲笑とが、一杯に
充ちているのだ。
貴女の笑顔ほど皮肉なものはない。
貴女の笑顔ほど、俺の心を突き刺すものはない。
貴女は、その笑顔で俺を悩まし殺そうとしているのだ。いや、俺ばかりじゃない! あの
馬鹿の
勝彦をまで悩ましておるのじゃ。」
勝平の態度には、
愈々乱酔の
萌が見えていた。彼の
眸は、怪しい輝きを帯び、狂人か何かのように
瑠璃子をジロ/\と見詰めていた。
風も雨も、海岸の
此一角に、その全力を
蒐めたかのように、
益々吹き
荒び降り
増った。が
瑠璃子は人と人との必死の戦いのために、そうした暴風雨の音をも、聞き流すことが出来た。
「
疑心暗鬼と言うことがございますね。
貴君のは、それですよ。
妾を疑ってかかるから、
妾の笑顔
迄が、
夜叉の面か何かのように見えるのでございますよ。」
そう言いながらも、
瑠璃子はその美しい冷たい笑いを絶たなかった。
勝平は、その
巨きい
身体を のたうつ ようにして言った。
「
貴女は、俺を飽くまでも、馬鹿にしておられるのじゃ。
貴女は人間としての俺を信用しておられんのじゃ。
貴女は、俺の人格を信じておられないのじゃ。俺に人間らしい心のあることを信じておられないのじゃ。
189/390
よし、
貴女が俺を人間として扱って下さらないなら、俺は
獣として、
貴女に向って行くのじゃ。俺は獣のように、
貴女に迫って行くのじゃ。」
勝平の
眸は燃ゆるように輝やいた。
「そうだ! 俺は獣として
貴女に迫って行く外はない!」
そう言ったかと思うと、
勝平は
羆が人間を襲う時のように、のッと立ち上った。
瑠璃子も
弾かれたように、立ち上った。
立ち上った
勝平は、フラ/\と
蹌めいてやっと踏み
堪えた。彼はその
凄じい
眸を、真中に据えながら、
瑠璃子の方へジリ/\と迫って来た。
かよわい
瑠璃子の顔は、
真蒼だった。身体はかすかに
顫えていたけれども、
怯びれた所は少しもなかった。その美しい
眉宇は、きっと、
緊き【引き】しまって、許すまじき色が、アリ/\と動いた。
丁度、その時だった。風に
煽られた大雨が
一頻り
沛然として降り注いで来た。
二
荒るゝまゝに、夜は十二時に近かった。
台所にいる
筈の女中達は、眠りこけてでもいるのだろう、話声一つ聞えて来なかった。ただ吹き
暴るゝ大風雨の
裡に
勝平と
瑠璃子と
丈が、取り残されたように、
睨みながら、相対していた。
空に風と雨とが、戦っているように、地に彼等は戦っているのだった。
瑠璃子は戦うべき力もなかった。武器も持ってはいなかった。たゞ彼女の態度に備る天性の美しい威厳一つが、
勝平の獣的な攻撃を
躊躇させていた。が、その躊躇も、永く続く筈はなかった。
勝平の眼が、段々狂暴な色を帯びると共に、彼は
勢猛に
瑠璃子に迫って来た。彼女は、相手の激しい勢に
圧されるようにジリ/\と
後退りをせずにはいられなかった。
190/390
勝平の今少し前の
懺悔や告白が、こうした態度に出るまでの径路であった――
一旦下手から説いて見て、それで行かなければ腕力に訴える――かと思うと、
勝平に対して、
懐いていた一時の好感は、煙のようになくなって、たゞ苦い苦い
憎悪の
滓丈が、残っていた。指一つ触れさせてなるものか、そうした堅い決意が、彼女の繊細な心臓を、鉄のように堅くしていた。
が、彼女の精神的な強さも、
勝平の肉体の上の優越に打ち勝つことが出来なかった。
何時の間にか追い詰められたように、部屋の一方に、海に面した
硝子戸の方へ、逃るゝ道のない硝子戸の方へ、
瑠璃子は圧し付けられている自分を
見出した。
其処で、追い詰められた
牝鹿と
獅子とのように、二人は
暫らくは相対していた。
暴風雨は、少しも勢いを減じていなかった。岸を
噛んで殺到する
波濤の響が、前よりも、もっと恐ろしく聞えて来た。が、相争っている二人の耳には、波の音も風の音も聞えては来なかった。
「何をなさるのです。
貴君は?」
勝平が、その
堅肥りの
巨い手を差し出そうとした時、
瑠璃子は初めて声を出して
叱した。
「何をしようと、
俺の勝手だ。夫が妻を、
生そうが殺そうが。」
勝平は、そう言いながら、再び
猿臂【長い腕】を延して、
瑠璃子の
柔かな、やさ肩を
掴もうとしたが、
軽捷な彼女に、ひらりと身体を避けられると、酒に酔った足元は、ふら/\と二三歩
蹌めいて、のめりそうになった。
「恥をお知りなさい! 恥を! 妻ではございましても
奴隷ではありませんよ。暴力を振うなんて。」
彼女は、汚れた者を叱するように、吐き捨てるように言った。彼女の声は、
遉にわな/\と
顫えていた。
「なに! 恥を! 恥も何もあるものか、俺はもう獣になり切っているのじゃ。」
勝平は、そう言ったかと思うと前よりももっと
烈しい勢で
瑠璃子に迫った。
191/390
こうしたあさましい人間の争いを、
賛美するかのように、風は空中に
凄じい歓声を挙げ続けている。
瑠璃子は、ふとその時
護り刀のことを思い出した。こうした非常な場合には、それを抜き放って自分を護る外はない。が、そう思い付いたものの、それはトランクの底深く、
蔵ってあるので、急場の今は、何の
援けにもならなかった。
彼女は、最後の手段として、声を振り
搾って女中を呼んだ。が、彼女の呼び声は、風雨の音に消されてしまって、台所の方からは、物音も聞えて来なかった。
瑠璃子が、
愈窮したのを見ると、
勝平は愈
威丈高になった。彼は、獣そのまゝの形相を現していた。ほの暗い
洋灯の光で、眼が
物凄く光った。
「あれ!」と、
瑠璃子が身を避けようとした時、
勝平の強い腕は、彼女の弱い二の腕を、グッと握り占めていた。
「何をするのです。お放しなさい!」
彼女は必死になって、振りほどこうとした。が、強い
把握は、容易に解けそうもなかった。
「何を! 何をするのです!」
瑠璃子は、死者狂いになって突き放した。が、突き放された
勝平は、前よりも二倍の狂暴さで、再び
瑠璃子に飛びかゝった。
その時だった。
瑠璃子の
背後の雨戸と硝子戸とが、バタ/\と音を立てゝ外れると、恐ろしい一陣の風が、サッと
室の中へ吹き込んだ。
洋灯は
忽ちに消えてしまった。が、灯の消える
刹那だった。風と共に飛び込んで来た一個の黒影が今
瑠璃子に飛びかゝろうとする
勝平に、横合からどうと組み付くのが、灯の消ゆる
たゆたい【揺らめき】の瞬間に
瞥見された【ちらりと見えた】。
三
硝子戸の外れるのと共に、
室の中へ吹き入った風と雨とは、
忽ちに、二十畳に近い大広間に
渦巻いた。床の間の掛軸が、バラ/\と吹き
捲られて、
跳ね落ちると、ガタ/\と
烈しい音がして、
鴨居の額が落ちる、六曲の
金屏風が吹き倒される。
192/390
一旦吹き込んだ風は逃れ口がないために、室内の
闇を縦横に
馳け
回って、
何時までも何時までも狂奔した。
而も、
此の風雨の
暴れ狂う漆黒の闇の中に、
勝平は飛び込んだ黒影と、必死の格闘を続けていたのだ。
「貴様は誰だ! 誰だ!」
不意の襲撃に驚いたらしく
勝平は、
狼狽して怒号した。が、相手は黙々として返事をしなかった。
肉と肉とが、
相搏つ音が、風雨の音にも
紛れず、
凄じい音を立てた。身体と身体とが、打ち合う音、筋肉と筋肉とが、
軋み合う音、それは風雨の争いにも、負けないほどに恐ろしかった。
其の
中に
どうと家中を揺がせる地響を打って、一方が投げ出される音が聞えた、それに続いて転がり合いながら、格闘する凄じい音が続いた。
「強盗だ! 強盗だ! 早く
老爺を呼んで来い!
瑠璃子! 瑠璃子!」
戦いが不利と見えて、
勝平の声は悲鳴に近かった。
瑠璃子は、物事の
烈しい変化に、気を
奪られたように、ボンヤリ闇の中に立っていた。身に迫った危険を、思いがけなく脱し得た安心と、新しく突発した危険に対する不安とで、心が一種不思議な動乱の中に在った。
勝平の悲鳴を聴いていると、助けてやらねばならぬと思いながら、一種の小気味よさを感ぜずにはいられなかった。自分に獣の
如く迫って来た彼が、突然の侵入者に
依って、
脆くも取って伏せられている。そう思うと
瑠璃子の動乱した胸にも皮肉な快感が、ぞく/\とこみ上げて来る。
格闘は
尚続いた。組み合いながら、座敷中をのたくっている恐ろしい物音が絶えなかった。
「
瑠璃子! 瑠璃子! 早く、早く。」
援けを呼ぶ
勝平の声は、だん/\苦しそうに
喘いで来た。
193/390
瑠璃子の心の
裡に、もっと
勝平を苦しませてやれ、こうした不意の出来事に
依って、もっと彼を
懲してやれと言う、
勝平に対する
憎悪の心持と、平生の憎悪は
兎に
角、不時の災難に苦しんでいる相手を、援けてやろうと言う人間的な心持とが、相争った。
其裡裡に、
ゼイ/\と息も絶えそうに、喘ぎ始めた
勝平の声が、聞え出した。
「苦しい! 苦しい! 人殺し! 人殺し!」
勝平は、
到頭最後の悲鳴を出してしまった。そうした声を聞くと、
瑠璃子の心にも、
勝平に対する
憐憫が
湧かずには いなかった。彼女は、始めて我に返ったように、台所の方に駆け出しながら、大声を出した。
「
老爺! 老爺! 早く来ておくれ! 泥棒! 泥棒!」
瑠璃子の声も、スッカリ上ずッてしまっていた。が、そう叫んだ時、彼女の頭の中に突然恋人の
直也の事が
閃いた。彼は、
勝平を
射とうとして誤って、
美奈子を傷つけた
為、危く罪人となろうとしたのを、
勝平に対する父の
子爵の哀訴のために、告訴されることを免れた。が、彼は
敵の
勝平からそうした恩恵を受けたことを、死ぬほど恥しがって、学業を捨ててしまって、遠縁の
親戚が経営しているボルネオの
護謨園に走ろうとしている。
瑠璃子は、そんな
噂を、耳にはさんでいる。が、あの多血性な【血の気の多い】恋人は、そうした逃避的な態度を、捨てゝ、その恋の敵を倒すために、再び風雨の夜に乗じて迫ったのであろうか。
否、自分に
決別するため、
外ながら自分を見ようとした時、偶然自分が危難に遭遇したため、前後の思慮もなく飛び込んだのではないだろうか。
強盗! 泥棒! 強盗や泥棒が、あゝした襲撃を
為すだろうか。もし、あれが
直也だったら、
縦令、
勝平を倒したにしろ、彼の一生はムザ/\と埋れてしまうのだ。
尤も、今でも自分のために、半分埋れかけているのだが。
194/390
そう思うと、
瑠璃子は老爺を呼ぶ声も出なくなってしまって、再び
其処へ立ち
竦んだ。
が、
瑠璃子の声に騒ぎ立った女中は、声を振り
搾って老爺を呼んだ。
四
叫び立てる女中達の声に、別荘番の老爺は驚いて
馳け付けて来た。強盗だと聴くと、いきなり取って返して、古い猟銃用の
村田銃を持って来た。彼は手早く台所の棚から、カンテラを取り出すと、取り乱す容子もなく、灯を点じて、戸外同様に風雨の
暴れ狂う広間の方へと、勇ましく立ち向った。もう六十を越した老人ではあったが、根が漁師育ちである
丈けに、
胆力【度胸】はガッシリと
据っていた。
瑠璃子は、
勝平と相
搏っている相手が、もしや恋人の
直也でありはしないかと思うと、
此の一徹の老人が、一気に銃口を向けやしないかと思う心配で、心が怪しく
擾れた。それかと言って、強盗であるかも知れぬ
闖入者を、
庇うような口は
利けなかった。台所に
顫えている女中を後に残しながら、
固唾を飲みながら、老人の後から、
随いて行った。
座敷は、風雨で
滅茶苦茶になっていた。室の中に渦巻く風のために、
硝子戸が三枚も外れていた。
其処から吹き入る雨のために、水を流したように、
濡れた畳が、カンテラの光に
物凄く映っていた。今にも、天井が吹き抜かれるように、バリ/\と恐ろしい音を立てゝ、鳴り続けた。
老人は、カンテラの光を
翳しながら、
「
旦那! 旦那!
喜太郎が参りましたぞ!」と次ぎの間から、
先ず大声で怒鳴った。
が、
勝平はそれに対して、何とも答えなかった。たゞ
勝平が発しているらしい低いうめき声が聞える
丈だった。
「旦那! 旦那! しっかりなさい!」
そう言いながら、
喜太郎は暗い座敷の中を、カンテラで照しながら、
駈け込んだ。その光で、ほの暗く照し出された大広間の
中央に、
勝平は仰向に打ち倒れながら、苦しそうにうめいているのだった。
195/390
「旦那! 旦那! しっかりなさい!
喜太郎が参りましたぞ! 泥棒は
何うしただ!」
喜太郎は、
勝平の
耳許で勢よく叫んだ。が、
勝平はたゞ低く、
喘息病みか何かのように
咽喉のところで、低くうめく
丈だった。
「旦那!
怪我をしたか。
何処だ! 何処だ!」
老人は、
狼狽しながら、その太い堅い手で、
勝平の身体を
撫で回した。が、何処にも傷らしい傷はなかった。が、それにも
拘わらず、半眼に開かれている
勝平の眼は、白く釣り上がっている。
「あゝ! こりゃいけねえ。奥様、こりゃいけねえぞ。」
そう言いながら、老人は
勝平の身体を
半抱き起すようにした。が、
巨きい身体は少しの弾力もなく石の
塊か何かのように重かった。
瑠璃子は、
遉に驚いた。
「もし、
貴君! もし
貴君!
貴君!」
彼女は、名ばかりの夫の胸に、
縋り付くようにして叫んだ。が、
勝平の身体に残っている生気は、こうしている間にも、だん/\消えて行くように思われた。
おず/\
顫えながら、座敷へ近づいて来た女中を顧みながら、
瑠璃子はハッキリと少しも取り
擾さない口調で言った。
「ブランデーの
壜を大急ぎで持っておいで。それから、
吉川様へ
直ぐお
出下さるように電話をおかけなさい! 直ぐ! 主人が
危篤でございますからと。」
女中の一人は、直ぐブランデーの
壜を持って来た。
瑠璃子は、それをコップに
酌ぐと、
甲斐甲斐しく
勝平の口を割って、口中へ注ぎ入れた。
勝平の
蒼ざめていた顔が、心持赤く興奮するように見えた。彼の釣り上った眼が、ほんの僅かばかり、人間の眼らしい光を回復したように見えた。
「旦那! 旦那! 相手は
何うしただ。強盗ですか。
何方へ逃げました。」
老人の別荘番は、主人の
敵を取りたいような意気込で
訊いた。
勝平はその大きい声が、消えかゝる聴覚に聞えたのだろう、口をモグ/\させ初めた。
「何でございますか。
196/390
何でございますか。」
瑠璃子も、
勝平を励ますために、そう叫ばずにはいられなかった。
その時に、
室の薄暗い一隅で、何者とも知れずカラ/\と悪魔の
嗤うように声高く笑った。
五
カンテラの光の届かない部屋の一隅から、急にカラ/\と
頓狂に笑い出す声を聴くと、元気のある度胸の据った
喜太郎迄が、ハッと色を変えた。村田銃の方へ差し延した左の手が、二三度銃身を
掴み損っていた。勝気な
瑠璃子の襟元をも、気味の悪い冷たさが、ぞっと
襲って来た。
「誰だ! 誰だ!」
喜太郎は
狼狽えながら、しわがれた声で
闇の中の見知らぬ人間を
誰何した。が、相手はまだ笑い声を収めたまゝ、じっとしている。
「誰だ! 誰だ! 黙っていると、
射ち殺すぞ!」
相手が黙っているので、勢いを得た
喜太郎は、村田銃を取り上げながら、その方へ差し向けた。
暗い片隅に
蹲まっている人間の姿が、差し向けられたカンテラの灯で、
朧ろげながら
判って来た。
「誰だ! 誰だ! 出て来い! 出て来い! 出て来ないと射つぞ!」
喜太郎は、
益々勢を得ながらそれでも飛び込んで行くほどの勇気もないと見えて、間を
隔てながら、叫んでいた。
相手が、割に落着いているところを見ると、それが強盗でないことは、判っていた。が、不意に耳を襲った頓狂な笑い声に
依っては、それが
何人であるかは、
瑠璃子にも判らなかった。彼女は、じっと
眸を
凝して、それが自分の
怖れている
如く、恋人の
直也ではありはしないかと、闇の中を見詰めていた。
丁度その時に、
喜太郎の大きい怒声に
依って、
朧気な意識を回復したらしい
勝平は、低くうめくように言った。
「射つな、射ったらいけないぞ!」
それは、一生懸命な必死な言葉だった。そう言ってしまうと、
勝平はまたグタリと死んだようになってしまった。
197/390
主人の言葉を聴くと、
喜太郎は何かを
悟ったように鉄砲を、投げ出すと、じり/\と見知らぬ男の方に近づいた。男は、
喜太郎が近づくと、だん/\
蹲まったまゝで、身を
退かしていたが、壁の所まで、追い詰められると、
矢庭に、スックと立ち上った。
瑠璃子は、また恐ろしい格闘の
光景を想像した。が、
瑠璃子の想像は
忽ち裏切られた。
「やあ!
若旦那じゃねえか!」
喜太郎は、
驚駭とも何とも付かない、調子外れの声を出した。
瑠璃子も、その
刹那弾かれたように立ち上った。
「奥様! 若旦那だ! 若旦那だ。」
喜太郎は、意外なる発見に、狂ったように叫び続けた。
瑠璃子も思わず、
瀕死の
勝平の傍を離れると、二人が突っ立ちながら、相対している方へ近づいた。
いかにも、その男は
勝彦だった。
何時も
見馴れている大島の不断着が、雨でズブ
濡れに濡れている。髪の毛も、雨を浴びて黒く
凄く光っている。日頃は、
無気味な顔ではあるが、何となく温和であるのが、
今宵は殺気を帯びている。それでも、
瑠璃子の顔を見ると、少し顔を
赤めながら、ニタリと笑った。
暫らくの間は、
瑠璃子も言葉が出なかった。が、
凡ては明かだった。東京の家に監禁せられていた彼は、
瑠璃子を慕うの余り、監禁を破って、東京から葉山まで、風雨を
衝いて、やって来たのに違いなかった。
「お父様をあんなにしたのは、
貴君でしたか。」
瑠璃子は、可なり
厳粛な態度でそう
訊いた。
勝彦は、黙って
肯いた。
「東京から、一人で来たのですか。」
勝彦は黙って肯いた。
「汽車に乗ったのですか。」
勝彦は、又黙って肯いた。
「お父様を、
何うしてあんなにしたのです。
何うしてあんなにしたのです。」
瑠璃子に、そう問い詰められると、
勝彦は顔を赤めながら、モジ/\していた。
198/390
もし
勝彦が、
聡明な青年であったならば、簡単に率直に、しかも貴夫人を救った
騎士のように勇ましく、
『
貴女を救うために。』と答え得たのであるが。
六
瑠璃子から、何と
訊かれても、
勝彦は何とも返事はしないで、たゞニタリ/\と笑い続けている
丈だった。
老人の
喜太郎は、張り詰めていた勇気が、急に抜け出してしまったように言った。
「仕様のない
若旦那だ。こんな晩に東京から、飛び出して来て、旦那をとっちめるなんて、
理屈のねえ事をするのだから、始末に
了えねえや。奥様! こんな人に
介意っているよりか旦那の容体が大事だ!」
喜太郎は、
勝彦を
噛んで捨てるように非難しながら、座敷の真中に、生死も
判らず
横わり続けている
勝平の方へ行った。
が、
瑠璃子は
喜太郎のように心から
勝彦を、非難する気には、なれなかった。口では
勝彦を
咎めるようなことを言いながら、心の中では
此の勇敢な救い主に、
一味温かい感謝の心を持たずにはいられなかった。
丁度、その時に、
勝平のうめき声が、急に高くなった。
瑠璃子は思わず、その方に引き付けられた。
彼の顔面の筋肉が、
頻りに
痙攣し、太い
巨きい四肢は、最後のあり
丈の力を
籠めたように、
烈しく畳の上にのたうった。
「水! 水!」
勝平は、苦しそうな
呻き声を
洩した。
女中が、転がるように持って来た水を、コップのまゝ口へ注ごうとしたが、思い
通にはならないらしい口辺の筋肉は、
当がわれたコップの水を、
咽喉の辺から胸にかけて
滾してしまった。
瑠璃子は、それを見ると、コップの水を一息飲みながら、口移しに
勝平の口中へ注いでやった。名ばかりではあるが、妻としての情であった。
水に
依って、
湿された
勝平の
咽喉は、初めてハッキリした
苦悶の言葉を発した。
「あゝ苦しい。胸が苦しい。切ない。」
彼は、そう叫びながら、心臓の
辺を幾度も
掻きむしった。
199/390
「
直ぐ医者が参ります。もう少しの御辛抱です。」
瑠璃子も、オロ/\しながら、そう答えた。
瑠璃子の言葉が、耳に通じたのだろう。彼は、
空虚な視線を妻の方に差し向けながら、
「
瑠璃子さん、
俺が悪かった。みんな、俺が悪かった。許して下さい!」
彼は、
身体中に残った精力を
蒐めながら、やっと切々に言った。つい一時間前の告白を疑った
瑠璃子にも、男子のこうした
瀕死の言葉は疑えなかった。
瑠璃子の冷たく閉じた心臓にも、それが針のように刺し貫いた。
「あゝ苦しい。切ない! 心臓が裂けそうだ!」
勝平は、心臓を両手で抱くようにしながら、畳の上を、二三回転げ回った。
「
美奈子! 美奈子はいないか!」
彼は、
突如苦しそうに、半身を起しながら、座敷中を見回した。
併し
美奈子が
其処にいる訳はなかった。二三秒間身体を支え得た
丈で、またどうと後へ倒れた。
「
美奈子さんも直ぐ来ます。電話で呼びますから。」
瑠璃子は、
耳許に口を寄せながら、そう言った。
「あゝ苦しい! もういけない! 苦しい!
瑠璃子さん! 頼みます、
美奈子と
勝彦のこと。
貴女は、俺を憎んでいても、子供達は憎みはしないでしょう。
貴女を頼むより外はない! 俺の罪を許して子供達を見てやって下さい! 頼みます!
勝彦!
勝彦!」
彼は、そう言いながら、再び身体を起そうとした。愚かなる子に、最後の言葉をかけようとしたのであろう。が、愚なる子は、父の臨終の苦しみを
外に、以前のまゝに、ケロリとして立ったまゝ、
此場の異常な
光景を、ボンヤリと凝視している
丈であった。
「あゝ苦しい! 切ない!」
勝平は最後の苦痛に入ったように、何物かを
掴もうとして、二三度
虚空を掴んだ。
瑠璃子は、その時始めて心から、夫のために、その白い二つの手を差し延べた。
200/390
勝平は、
瑠璃子の白い腕に触れるとそれを
生命の最後の力で握りしめながら、また差し延べられた手に、
瑠璃子からの
宥を感じながら、妻からの情を感じながら、最後の
呼吸を引き取ってしまったのである。
七
勝平の最後の息が絶えようとしている時に、医師がやって来た。レインコートの下へまで、激しい雨が
浸み入ったと見え、洋服の所々から、
雫がタラ/\と落ちていた。
「車で来ようと思ったのですが、家を二間ばかり離れると、
直ぐ吹き倒されそうになりましたから、徒歩で来ました。風が北へ回ったようですから、もう大丈夫です。まさか、
先度のようなことはありませんでしょう。」
医師は、
遉に職業的な落着を見せながら、女中達の出迎えを受けて、座敷へ通って来た。
「お電話じゃ十分
判りませんでしたが、
何うなさったのです。強盗と組打ちをなさったと言うのは本当ですか。」
医師は、横わっている
勝平の傍近く、
膝行り寄りながら、
瑠璃子にそう
訊いた。
瑠璃子は、
遉に落着きを失わなかった。
「いゝえ! 女中が
狼狽えて、そんなことを申したのでございましょう。強盗などとは
嘘でございます。お恥かしいことでございますが、つい息子と……」
そう言ったものの、後は続け得なかった。医師は直ぐその場の事情を
呑み込んだように、
勝平の身体に手をやって、
一通検めた。
「
何処もお
負傷はないのですね。」
「はい! 負傷はないようでございます。」
瑠璃子は静かに答えた。
「御心配はありません。何処か打ち所が悪くって気絶をなさったのです。」
医師は事もなげにそう言いながら、その夜目にも白い手を脈に触れた。五秒十秒、医師はじっと耳を傾けていた。それと同時に、彼の
眸に、
勝平の
蒼ざめて行く顔色が映ったのだろう。彼は、急に
狼狽したように前言を打ち消した。
201/390
「あゝこりゃいけない!」
そう言いながら、彼は手早く
聴診器を、
鞄の中から、引きずり出しながら、
勝平の
肥り切った胸の中の心臓を、探るように、幾度も/\当がった。
「あゝこりゃいけない!」
彼は再び絶望したような声を出した。
「いけませんでございましょうか。」
そう訊いた
瑠璃子の声にも、深い
憂慮が含まれていた。
「こりゃいけない! 心臓
麻痺らしいです。
何時か診察したときにも、よく御注意して置いた
筈ですが、可なり
酷い脂肪心だから、よく御注意なさらないと、直ぐ心臓麻痺を起し
易いと、幾度も言った筈ですが。
喧嘩だとか格闘だとか、興奮するようなことは、一切してはならないと、注意して置いたのですがね。」
医師は、いかにも、自分の与えた注意が守られなかったのが、
遺憾に
堪えないように、耳は聴診器に当がいながら、幾度も繰り返した。
「心臓の周囲に、脂肪が
溜ると、非常に心臓が弱くなってしまうのです。火事の時などに、
駈け出した
丈で、倒れてしまう人があるのです。それに酒を召し上っていたのですね。酒を飲んでいる上に、
烈しい格闘をやっちゃ
堪りません。お子さんとなら、また何だって早くお止めにならなかったのです。」
そう言われると、
瑠璃子の良心は、グイと何かで突き刺されるように感じた。
「もう駄目だとは思いますが、
諦めのために、カンフル注射をやって見ましょう。」
医師は、手早くその用意をしてしまうと、今肉体を去ろうとして、たゆとうている【ゆらゆらと揺れ動いている】魂を、呼び返すために、巧みに注射針を
操って、一筒のカンフルを体内に注いだ。
医師は、注射の反応を待ちながらも、二三度人工呼吸を試みた、が、
勝平の身体は、刻一刻、人間特有の温みと生気とを失いつゝあった。その
巨きい顔に、死相がアリ/\と刻まれていた。
「お気の毒ですが、もう何とも仕方がありません。」
202/390
医師は、死に対する人間の無力を現すように、
悄然と【元気がなく】最後の宣告を下した。
八
戦は終った。不意に突然に意外に、敵は今彼女の眼前に、何の力もなく何の意地もなく
土塊の
如くに横わっている。
彼女は見事に勝った。勝ったのに違いなかった。
傲岸な、金の力に
依って、人間の道を
蔑しようとした相手は倒れている。そうだ! 勝利は明かだ。
が、
勝平の死顔をじっと見詰めている時に、彼女の心に
湧いて来たものは、勝の
欣びではなくしてむしろ勝の悲しみだった。勝利の
悲哀だった。確に勝っている。が、
勝平の肉体に勝った如く、彼の精神にも勝ち得ただろうか。
勝平は、その
瀕死の
刹那に
於て、精神的にも
瑠璃子に破られていただろうか。
否! 否!
瑠璃子自身の良心が、それを否定している。
愈々、死が迫って来た時の
勝平の心は、彼の一生の
凡ての罪悪を
償い得るほどに、美しく輝いていたではないか。
彼は、自分の
容しを
瑠璃子に
乞うた上、二人の愛児の行末を、
瑠璃子に頼んでいる。彼は名ばかりの妻から、夫として
堪えがたき反抗を受けながら、
尚彼女に美しき信頼を置こうとしている。
それよりも、もっと
瑠璃子の心を
穿った【物事の本質を深く見抜く】ものは、彼が臨終の時に示した子供に対する、綿々たる愛だった。格闘の相手が――従って彼の死の原因が――
勝彦であることを知りながらも、
此の愚なる子の行末を、苦しき臨終の
刹那に気遣っている。彼の人間らしい心は、その死床に於て、
燦然として輝いたではないか。
彼を敵として結婚し、結婚してからも、彼に心身を許さないことに
依って、彼に
悶々の悩みを
嘗めさせ、それが半ば偶然であるとは言え、
勝彦を
操ることに
依って、畜生道の苦しみを味わせた自分を死の刹那に於て心から信頼している。
203/390
そうした言葉を聴いたとき、
瑠璃子の良心は、可なり深い痛手を負わずにはいられなかった。
悪魔だと思って刺し殺したものは、意外にも人間の相を現している。が、刺し殺した
瑠璃子自身は、刺し殺す
径路に於て、刺し殺した結果に於て、悪魔に近いものになっている。
自分の一生を犠牲にして、倒したものは、意外にも倒し
甲斐のないものだった。恋人を捨てゝ、
処女としての誇を捨てゝ、世の悪評を買いながら、全力を尽くして、戦った戦いは、戦い
栄のしない無名の
戦だった。
負けた
勝平は、負けながら、その死床に人間として救われている。が、見事に勝った
瑠璃子は、救われなかった。
自分の一生を
賭してかゝった仕事が、空虚な幻影であることが、分った時ほど、人間の心が
弛緩し堕落することはない。
彼女の心は、その時以来別人のように
荒んだ。
清浄なる
処女時代に立ち帰ることは、その肉体は許しても、心が許さなかった。敵と戦うために、自分自身心に塗った毒は、いつの間にか、心の
中深く
浸み入って消えなかった。
その上に、もっと悪いことには、名ばかりの妻として、
擅にした物質上の栄華が、
何時の間にか、彼女の心に魅力を持ち始めていた。
彼女は、荒んだ心と、
処女としての新鮮さと、未亡人としての
妖味とを兼ね備えた美しさと、その美を飾るあらゆる自由とを
以て、何時となく、世間のあらゆる男性の間に、
孔雀の如く、その双翼を
拡げていた。
怪頭醜貌【異様で醜悪な容貌】の女怪
ゴルゴンは、見る人をして
悉く石に化せしめたと
希臘神話は伝えている。
黒髪
皎歯清麗真珠の如く【黒髪はつややかで、歯は白く、気品は清らかで、真珠のように麗しい】、
艶容【なまめかしく美しい】人魚の如き
瑠璃子は、その
聡明なる
機知と、その奔放自由なる所作とを以て、彼女を見、彼女に近づくものを、果して何物に化せしめるであろうか。
204/390
魅惑
一
奇禍のために死んだ青年の手記を見た後も、美しき
瑠璃子夫人は、
尚信一郎の心に、一つの
謎として
止まっていた。手記に
依れば、青年を
翻弄し、彼をして、形は
奇禍であるが、心持の上では、自殺を遂げしめた彼女なる女性が、
瑠璃子夫人であるようにも思われた。が、夫人その人は、
信一郎の目前で、青年の最後の
怨みが
籠っている
筈の、時計の持主であることを否定していた。
信一郎は、夫人の白いしなやかな手で、軽く五里霧中の
裡へ、突き放されたように思った。
血腥い
青木淳の死と、美しい夫人とを、不思議な糸が、結び付けて、その周囲を、神秘な霧が幾重にも閉ざしている。その霧の中に、チラ/\と時折、
瞥見するものは、半面紫色になった青年の死顔と、
艶然たる微笑を含んだ夫人の
皎玉の
如き美観とであった。
青年から、瀕死の声で、返すことを頼まれた時計は、――青年の怨みを籠めて、返さなければならぬ時計は、
あやふやな口実のもとに、謎の夫人の手に、手軽に手渡されている。
信一郎は、死んだ青年に対する責任感からも、
此の謎を
一通は解かねばならぬと思った。時計が、その真の持主に、青年の望んだ通の意味で、返されることの
為に、出来る
丈は尽さねばならぬことを感じた。
が、その謎を解くべき、
唯一の手がかりなる時計は、既に夫人の手に渡っている。たゞ、それの受取のように、夫人から贈られた慈善音楽会の一葉の入場券が、
信一郎の紙入に、何の不思議もなく残っている
丈である。
が、
此の何の
奇もない入場券と、『是非お
出下さいませ。その節お目にかゝりますから。』と言う夫人の言葉とが、今の場合夫人に近づく、従って夫人の謎を解くべき唯一の心細い頼りない手がかりだった。夫人と
信一郎とを結び付けている細い/\
蜘蛛の糸のような、
継ぎであった。
205/390
尤も、どんなに細くとも、蜘蛛の糸には、それ相応の粘着力はあるものだが。
音楽会の期日は、六月の最後の日曜だった。その日の朝までも、
信一郎の心には、妙に
躊躇する心持もあった。お前は、青年に対する責任感からだと、お前の行為を解釈しているが、本当は一度言葉を交えた
瑠璃子夫人の
美貌に
惹き付けられているのではないか。彼の心の
裡で、
反噬するそうした叫びもあった。その上、今日までは、こうした会合へ出るときは、
屹度新婚の
静子を伴わないことはなかった。が、今日は妻を伴うことは、考えられないことだった。会場で出来る
丈、夫人に接近して夫人を知ろうとするためには、妻を同伴することは、足手
纏いだった。
昼食を済ましてからも、
信一郎は音楽会に行くことを、妻に打ち明けかねた。が、外出をするためには、着替をすることが、必要だった。
「
一寸散歩に。」と言ってブラリと、着流しのまま、外出する訳には行かなかった。
「
一寸音楽会に行って来るよ。着物を出しておくれ。」
そうした言葉が、
何うしても気軽に出なかった。それは、何でもない言葉だった。が、
信一郎に取っては、妻に対して吐かねばならぬ最初の冷たい言葉だった。
「音楽会に行くから、お前も支度をおしなさい。」
そうした言葉
丈しか、聞かなかった
静子には、それが可なり冷たく響くことは、
信一郎には余りによく
判っていた。
彼は、ぼんやり縁側に立っているかと思うと、また、何かを思い出したように二階へ上った。が、机の前に
座っても、少しも落着かなかった。彼は、思い切って妻に言う積りで、再び
階下へ降りて来た。
が、
解き物をしながら、階段を降りて来る夫の顔を見ると、心の
裡の幸福が、自然と弾み出るような微笑を浮べる妻の顔を見ると、手軽に言って
退ける
筈の言葉が、またグッと
咽喉にからんでしまった。
206/390
「あら!
貴君、
先刻から何をそんなに、ソワソワしていらっしゃるの?」
無邪気な妻は夫の図星を指してしまった。指さゝれてしまうと、
信一郎は
却って落着いた。
「うっかり忘れていたのだ。今日は専務が米国へ行くのを送って行かなければ ならないのだった!」
彼は、
咄嗟に今日出発する筈の専務のことを思い出したのだ。
「何時の汽車? これから行っても、間に合うのでございますか?」
静子は
一寸心配そうに言った。
「間に合うかも知れない。確か二時に新橋を立つ筈だから。」
そう言いながら、
信一郎は柱時計を見上げた。それは、一時を回ったばかりだった。
「じゃ、早くお支度なさいまし。」解き物を、
掻きやって、妻は、
甲斐々々しく立ち上った。
信一郎は、最初の冷たい言葉を言う代りに、最初の嘘を言ってしまった。その方が、ズッと悪いことだが。
二
その日の音楽会は、
露西亜のピアニスト若きセザレヴィッチ兄妹の独奏会だった。
去年から今年にかけて、故国の動乱を避けて、
漂泊の旅に出た
露西亜の音楽家達が、幾人も幾人も東京の楽壇を
賑わした。
其中には、ピアノやセロやヴァイオリンの世界的名手さえ交っていた。セザレヴィッチ兄妹もやっぱり、漂泊の旅の寂しさを、背負っている人だった。
殊に、妹のアンナ・セザレヴィッチの
何処か東洋的な、日本人向きの
美貌が、兄妹の天才的な演奏と共に、楽壇の人気を
唆っていた。その日の演奏は、確か三四回目の演奏会だった。上流社会の貴夫人達の主催にかゝる、その日の演奏会の純益は、東京にいる
亡命の露人達の窮状を救うために、
投ぜられる筈だった。
信一郎が、その日の会場たる上野の精養軒の階上の大広間の入口に立った時、会場はザッと一杯だった。が、人数は三百人にも足らなかっただろう。七円と言う高い会費が、今日の聴衆を、可なり貴族的に制限していた。
207/390
極楽鳥のように着飾った夫人や令嬢が、ズラリと
静粛に並んでいた。その中に諸所
瀟洒なモオニングを着て、楽譜を手に持っている、音楽研究の若殿様と言ったような紳士が、二三人
宛交じっていた。
信一郎は聴衆を
一瞥した
刹那に、
直ぐ油に交じった水のような寂しさを感じた。こうした華やかな
群の中に、
女王のように立ち働いている
荘田夫人が、自分に――片隅に小さく控えている自分に、少しでも注意を向けて
呉れるかと思うと、妻の手前を繕ろってまで、出席した自分が、何だか心細く
馬鹿々々しくなって来た。
信一郎が、席に着くと間もなく、妹の方のアンナが、華やかな拍手に迎えられて壇上に現われた、
スラヴ美人の典型と言ってもいゝような、
碧い
眸と、白い雪のような頬とを持った美しい娘だった。彼女は微笑を含んだ
会釈で
喝采に
応えると、水色のスカートを
翻しながら、快活にピアノに向って腰を降した。と、思うと、その白い
蝋のような
繊手【かぼそい、しなやかな手】は、直ぐ
霊活な
蜘蛛か何かのように、
鍵盤の上を、
駈け回り始めた。曲は、
露西亜の国民音楽家の一人として名高い
ボロディンの
譚歌【バラード】だった。
その素朴な、軽快な旋律に、耳を傾けながら、
信一郎の注意は、半ば聴衆席の前半の方に走っていた。彼は、若い婦人の後姿を、それからそれと一人々々
検めた。が、たった一度、相見た
丈の女は、後姿に
依っては、直ぐそれと分りかねた。
妹の演奏が終ると、美しい
花環が、幾つも幾つも、壇上へ運ばれた。
露西亜の少女は、それを一々
溢れるような感謝で受取ると、子供のように
欣びながら、ピアノの上へ幾つも/\置き並べた。余り沢山置き並べるので、演奏の邪魔になりそうなので、司会者が
周章て取り降した。聴衆が、
此の少女の無邪気さを
どっと笑った。
信一郎も、少女の美しさと無邪気さとに、引きずられて、つい笑ってしまった。
208/390
丁度その途端、
信一郎の肩を軽く
軟打するものがあった。彼は
駭いて、振り
顧った。そこに微笑する美しき
瑠璃子夫人の顔があった。
「よくいらっしゃいましたのね。先刻からお探ししていましたのよ。」
信一郎の言うべきことを、向うで言いながら、
瑠璃子は、
信一郎と並んで
其処に空いていた
椅子に腰を下した。
「あまりお見えに ならないものですから、いらっしゃらないのかと思っていましたのよ。」
信一郎の方から、改めて
挨拶する機会のないほど、向うは親しく
馴々しく、友達か何かのように言葉をかけた。
「先日は、
何うも失礼しました。」
信一郎は、遅ればせに、ドギマギしながら、挨拶した。
「いゝえ!
妾こそ。」
彼女は、
小波一つ立たない池の面か何かのように、落着いていた。
丁度、その時に兄のニコライ・セザレヴィッチが壇上に姿を現した。が、
瑠璃子夫人は立とうとはしなかった。
「
妾、
暫らく
茲で聴かせていただきますわ。」
彼女は、
信一郎に言うともなく
独語のように
呟いた。
三
丁度その時、兄のセザレヴィッチの
奏き初めた曲は、ショパンの
前奏曲だった。聴衆は、水を打ったような
静寂の
裡に、全身の注意を二つの耳に
蒐めていた。が、その中で、
信一郎の注意
丈は、彼の左半身の触覚に、
溢れるように満ち渡っていた。彼の左側には、
瑠璃子夫人が、
座っていたからである。彼女は、故意にそうしているのかと思われるほどに、その
華奢な身体を、
信一郎の方へ寄せかけるように、座っていた。
信一郎は、
淡彩【薄くて淡い色】に夏草を散らした
薄葡萄色の、
金紗縮緬の着物の下に、軽く波打っている彼女の肉体の暖かみをさえ、感じ得るように思った。
彼女は、演奏が初まると、
直ぐ独語のように、「
雨滴のプレリュウドですわね。」と、軽く小声で言った。
209/390
それは、いかにもショパンの数多い前奏曲の
中、『雨滴の前奏曲』として、知られたる傑作だった。
彼女は、演奏が進むに連れて、彼女の
膝の、夏草模様に、実物
剥製の
蝶が、群れ飛んでいる
辺を、
其処に目に見えぬ
鍵盤が、あるかのように、白い細い指先で、軽くしなやかに、打ち続けているのだった。
而も、それと同時に、彼女の美しい
横顔は、本当に音楽が
解るものゝ感ずる
恍惚たる喜悦で輝いているのだった。
其処には日本の普通の女性には見られないような、精神的な美しさがあった。思想的にも、感覚的にも、開発された本当に新しい女性にしか、許されていないような、
神々しい美しさがあった。
信一郎は、時々彼女の横顔を、その
くっきりと通った襟足を、そっと見詰めずにはいられないほど、彼女独特の美しさに、心を
惹かされずにはいられなかった。
曲が、終りかけると、彼女は
何人よりも、先に
慎しい拍手を送った。
快い緊張から夢のように
醒めながら、彼女は
信一郎を顧みた。
「妹の方が、技巧は確ですけれども、どうも兄の方が、奔放で、自由で、それ
丈天才的だと思いますのよ。」
「僕も同感です。」
信一郎も、心からそう答えた。
「
貴君、音楽お好き? ほゝゝゝ、わざ/\来て下さったのですもの、お好きに
定っていますわね。」
彼女は、二度目に会ったばかりの
信一郎に、少しの気兼もないように、話した。
「好きです。高等学校にいたときは、音楽会の会員だったのです。」
「ピアノお
奏きになって?」
「簡単なバラッドや、マーチ位は奏けます。はゝゝゝゝ。」
「ピアノお持ちですか。」
「いいえ。」
「じゃ、
妾の宅へ時々、奏きにいらっしゃいませ。誰も気の置ける人【遠慮が必要な相手】はいませんから。」
彼女は、薄気味の悪いほど、
馴々しかった。その時に、壇上には、妹のアンナが立っていた。
210/390
「
バラキレフの『イスラメイ』を
演るのですね。随分難しいものを。」
そう言いながら、彼女は立ち上った。
「みんなが、
妾を探しているようですから、失礼いたしますわ。会が終りましたら、
階下の食堂でお茶を一緒に召上りませんか。約束して下さいますでしょうね。」
「はあ! 結構です。」
信一郎は、何かの命令をでも、受けたように答えた。
「それでは後ほど。」
彼女は、軽く
会釈すると、静まり返っている聴衆の間の通路を、
怯れもせず
遥か前方の自分の席へ帰って行った。
信一郎は可なり熱心な眼付で、彼女を見送った。
彼女が、席に着こうとしたとき彼女の席の周囲にいた、多くの男性と女性とは、彼女が席に帰って来たのを、女王でもが、帰還したように、銘々に会釈した。彼女が多くの男性に囲まれているのを見ると、
信一郎の心は、妙な不安と動揺とを感ぜずにはいられなかったのである。
四
それから、演奏が終ってしまうまで、
信一郎は、ピアノの快い
旋律と、
瑠璃子夫人の残して行った魅惑的な移り香との中に、
恍惚として夢のような時間を過してしまった。
最後の演奏が終って、華やかな拍手と共に、皆が立ち上ったとき、
信一郎は夢から、さめたように席を立ち上った。
彼は、自分から
先刻の約束を守るために、
瑠璃子夫人を探し求めるほど大胆ではなかった。それかと言って、そのまま帰ってしまうには、彼は夫人の美しさに、支配され過ぎていた。彼は聴衆に先立って階段を降りたものゝ、階段の下で誰かを待ってでもいるように、
躊躇していた。
美しい女性の流れが、
暫らくは階段を滑っていた。が、待っても、待っても夫人の姿は見えなかった。
彼が、待ちあぐんでいる
裡に、聴衆は降り切ってしまったと見え、下足の前に
佇んでいる人の数がだん/\
疎になって来た。
彼は『一緒にお茶を飲もう。
211/390
』と言うことが、ただ
一寸した、夫人のお世辞であったのではないかと思った。それを
金科玉条のように、一生懸命に守って、待ちつゞけていた自分が、少し
馬鹿らしくなった。夫人は、
屹度混雑を避けて、別の出口から、もうとっくに帰り去ったに違いない。そう思って、彼は軽い失望を感じながら、
踵を返そうとした時だった。階段の上から、軽い靴音と、やさしい
衣擦の音と、
流暢な
仏蘭西語の会話とが聞えて来た。彼が、軽い
駭きを感じて、見上げると、階段の中途を静に降りかかっているのは、今日の
花形なるアンナ・セザレヴィッチと
瑠璃子夫人とだった。その二人の洗い出したような鮮さが、
信一郎の心を、深く深く動かした。一種
敬虔な心持をさえ
懐かせた。
白皙な【色が白い】
露西亜美人と並んでも、
瑠璃子夫人の美しさは、その特色を立派に発揮していた。
殊に、そのスラリとして高い長身は、
凡ての日本婦人が白人の女性と並び立った時の醜さから、彼女を救っていた。
信一郎は、
うっとりとして、名画の美人画をでも見るように、暫らくは見詰めていた。
それと同じように、彼を
駭かしたものは
瑠璃子夫人の
暢達な
仏蘭西語であった。仏法出【フランス法を習った】の法学士である
信一郎は、可なり会話にも自信があった。が、水の
迸しるように、自然に豊富に、美しい発音を
以て、語られている言葉は、
信一郎の心を魅し去らず【魅了せず】にはいなかった。
瑠璃子は、階段の傍に、ボンヤリ立っている
信一郎には、
一瞥も与えないで、アンナを玄関まで送って行った。
其処で、後から来た兄のセザレヴィッチを待ち合わすと、兄妹が自動車に乗ってしまう
迄、主催者の貴婦人達と一緒に見送っていた。彼女一人、兄妹を相手に、始終快活に談笑しながら。
兄妹を乗せた自動車が、去ってしまうと、彼女は、初めて
信一郎を見付けたように、いそいそと彼の傍へやって来た。
212/390
「まあ! 待っていて下さいましたの。随分お待たせしましたわ。でも兄妹を送り出すまで、幹事として責任がございますの。」
彼女は、そう言いながら、帯の間から、時計を取り出して見た。それはやっぱり
白金の時計だった。それを見た
刹那、不安ないやな連想が、
電火のように、
信一郎の心を走せ過ぎた。
「おやもう、六時でございますわ。お茶なんか飲んでいますと、遅くなってしまいますわ。
如何でございます。あのお約束は、またのことにして下さいませんか。ねえ! それでいゝでございましょう。」
「はあ! それで結構です。」
信一郎は、従順な
僕のように答えた。
「
貴君! お宅は
何方!」
「
信濃町です。」
「それじゃ、院線で御帰りになるのですか。」
「市電でも、院線でも
孰らでゞも帰れるのです。」
「それじゃ、院線で御帰りなさいませ。万世橋でお乗りになるのでしょう。
妾の自動車で万世橋までお送りいたしますわ。」
彼女は、それが何でもないことのように、微笑しながら言った。
五
わずか二度しか逢っていない、
而も確かな紹介もなく妙な事情から、
知己になっている男性に――その職業も位置も身分も十分分っていない男性に、突然自動車の同乗を勧める
瑠璃子夫人の大胆さに、勧められる
信一郎の方が、
却ってタジ/\となってしまった。
信一郎は、
一寸狼狽しながら、急いでそれを断ろうとした。
「いゝえ恐れ入ります。電車で帰った方が勝手ですから。」
「あら、そんなに改まって遠慮して下さると困りますわ。
妾本当は、お茶でもいたゞきながら、ゆっくりお話がしたかったのでございますよ。それだのに、ついこんなに遅くなってしまったのですもの。せめて、一緒に乗っていたゞいて、お話したいと思いますの。死んだ
青木さんのことなども、お話したいことがございますのよ。」
「でも御迷惑じゃございませんか。」
213/390
信一郎は、もう可なり、同乗する興味に、動かされながら、それでも口先ではこう言って見た。
「あら、御冗談でございましょう。御迷惑なのは、
貴君ではございませんか。」
夫人の言葉は、銘刀のように鮮かな
冴を持っていた。
信一郎が、夫人の奔放な言葉に圧せられたように、モジ/\している間に、夫人はボーイに合図した。ボーイは、玄関に立って、声高く自動車を呼んだ。
暮れなやむ初夏の宵の
夕暗に、今点火したばかりの、
眩しいような
頭光を輝かしながら、青山の葬場で一度見たことのある青色大型の自動車は、軽い爆音を立てながら、玄関へ横付になった。会衆は
悉く散じ去って、
供待する
俥も自動車一台も残っていなかった。
「さあ!
貴君から。」
信一郎の確な承諾をも聴かないのにも
拘わらず、夫人はそれに
定った事のように、
信一郎を促した。
そう勧められると、
信一郎は不安と幸福とが、半分
宛交ったような心持で、胸が
掻き乱された。彼は、心から同乗することを欲していたのにも拘わらず、乗ることが何となく不安だった。その踏み段に足をかけることが、何だか行方知らぬ運命の岐路へ、一歩を踏み出すように不安だった。
「あら、何をそんなに遠慮していらっしゃるの。じゃ、
妾が御先に失礼しますわ。」
そう言うと、夫人は軽やかに、紫のフェルトの
草履で、
踏台を軽く踏んで、ヒラリと車中の人になってしまった。
「さあ! 早くお乗りなさいませ。」
彼女は振り
顧って、微笑と共に
信一郎を
麾ねいた。
相手が、そうまで何物にも
囚われないように、奔放に振舞っているのに、男でありながら、こだわり通しにこだわっていることが、
信一郎自身にも、
嫌になった。彼は、思い切って、
踏台に足を踏みかけた。
信一郎は、車中に入ると、夫人と対角線的に、前方の腰かけを、引き出しながら、腰を掛けようとした。
214/390
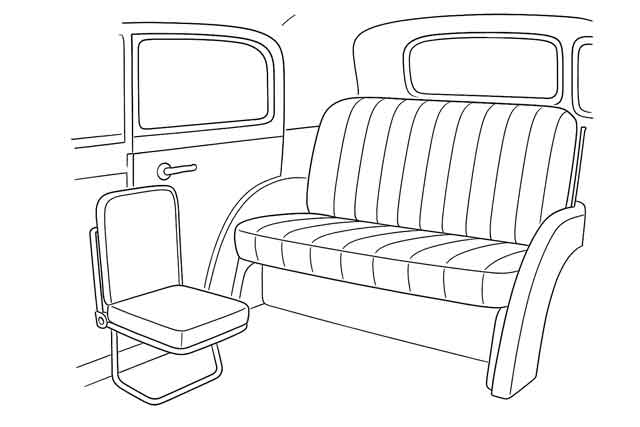
夫人は
駭いたように、それを制した。
「あら、そんなことをなさっちゃ、困りますわ。まあ、殿方にも似合わない、何と言う遠慮深い方でしょう。さあ
此方へおかけなさい!
妾と並んで。そんなに遠慮なさるものじゃありませんよ。」
信一郎を、
窘めるように、
叱るように、夫人の言葉は力を持っていた。
信一郎は、今は
止むを得ないと言ったように、夫人と擦れ/\に腰を降した。夫人の身体を
掩うている
金紗縮緬の
いじり痒いような触感が、
衣服越しに、彼の身体に
浸みるように感ぜられた。
給仕やボーイなどの
挨拶に送られて、自動車は滑るように、玄関前の緩い
勾配を、公園の青葉の
闇へと、進み始めた。
給仕人達の挨拶が、耳に入らないほど、
信一郎は、
烈しい興奮の
裡に、夢みる人のように、
恍惚としていた。
六
つい知り合ったばかりの女性、しかも美しく高貴な女性と、たった二度目に会ったときに、もう既に自動車に、同乗すると言うことが、
信一郎には、
宛ら美しい夢のような、二十世紀の
伝奇譚の主人公になったような、不思議な
歓びを与えて
呉れた。万世橋駅
迄の三四分が、彼の生涯に再び得がたい貴重な三四分のように思われた。彼の生涯を通じて、宝石のように輝く、尊い瞬間のように思われた。彼は、その時間を心の底から、
享け入れようと思っていた。が、そう決心した
刹那に、もう自動車は、公園の
蒼い
樹下闇を、後に残して、上野山下に
拡がる初夏の夜、そうだ、豊に輝ける夏の夜の描けるが
如き、光と色との中に、
馳け入っているのだった。時は速い翼を持っている。が、
此の三四分の時間は、電光その物のように、アッと言う間もなく過ぎ去ろうとしている。
215/390
試験の答案を書く時などに、時間が短ければ短いほど、冷静に筆を運ばなければならないのに、時間があまりに短いと、
却てわく/\して、少しも手が付かないように、
信一郎も飛ぶが如くに、過ぎ去ろうとする時間を前にして、たゞ
茫然と手を
拱いている【何もしない】
丈だった。
然るに、
瑠璃子夫人は悠然と、落着いていた。親しい友達か、でなければ自分の夫とでも、一緒に乗っているように、微笑を車内の
薄暗に、漂わせながら、急に話しかけようともしなかった。
丁度、自動車が松坂屋の前にさしかゝった時、
信一郎は、やっと――と言っても、たゞ一分間ばかり黙っていたのに過ぎないが――会話の
緒を見付けた。
「先刻、
一寸立ち聴きした訳ですが、大変
仏蘭西語が、お上手でいらっしゃいますね。」
「まあ! お恥かしい。聴いていらしったの。動詞なんか
滅茶苦茶なのですよ。単語を並べる
丈。でもあのアンナと言う方、大変感じのいい方よ。大抵お話が通ずるのですよ。」
「
何うして滅茶苦茶なものですか。大変感心しました。」
信一郎は心でもそう思った。
「まあ! お
賞めに
与って有難いわ。でも、本当にお恥かしいのですよ。ほんの二年ばかり、お
稽古した
丈なのですよ。
貴君は仏法の出身でいらっしゃいますか。」
「そうです。高等学校時代から、六七年もやっているのですが、それで会話と来たら、丸切り駄目なのです。よく、会社へ仏蘭西人が来ると、私
丈が仏蘭西語が出来ると言うので、応接を命ぜられるのですが、その度
毎に、閉口するのです。奥さんなんか、このまゝ
直ぐ外交官夫人として、
巴里辺の社交界へ送り出しても、立派なものだと思います。」
信一郎は、つい心からそうした
賛辞を呈してしまった。
「外交官の夫人! ほゝゝ、
妾などに。」
そう言ったまゝ、夫人の顔は急に曇ってしまった。外交官の夫人。
216/390
彼女の若き日の
憧れは、未来の外交官たる
直也の妻として、遠く海外の社交界に、日本婦人の華として、咲き
出ることではなかったか。彼女が、仏蘭西語の稽古をしたことも、みんなそうした日のための、準備ではなかったか。それもこれも、今では煙の如く
空しい過去の思出となって
了っている。外交官の夫人と言われて、彼女の華やかな表情が、急に光を失ったのも無理はなかった。
瞬間的な沈黙が、二人を支配した。自動車は
御成街道の電車の右側の
坦々たる道を、速力を加えて
疾駆していた。万世橋迄は、もう三町もなかった。
信一郎は、もっとピッタリするような話がしたかった。
「仏蘭西文学は、お好きじゃございませんか。」
信一郎は、夫人の顔を
窺うように
訊いた。
「あのう――好きでございますの。」
そう言ったとき、夫人の曇っていた表情が、華やかな微笑で、
拭い取られていた。
「大好きでございますの。」
夫人は、再び強く肯定した。
七
「
仏蘭西文学が大好きですの。」と、夫人が答えた時、
信一郎は
其処に夫人に親しみ近づいて行ける会話の範囲が、急に開けたように思った。文学の話、芸術の話ほど、人間を本当に親しませる話はない。同じ文学なり、同じ作家なりを、両方で愛していると言うことは、ある未知の二人を可なり親しみ近づける事だ。
信一郎は、初めて夫人と交すべき会話の題目が見付かったように
欣びながら、勢よく
訊き続けた。
「やはり近代のものをお好きですか、
モウパッサンとか
フローベルなどとか。」
「はい、近代のものとか、
古典とか申し上げるほど、沢山はよんでおりませんの。でも、モウパッサンなんか大嫌いでございますわ。
何うも日本の文壇などで、仏蘭西文学とか
露西亜文学だとか申しましても、英語の
廉価版のある作家ばかりが、
流行っているようでございますわね。」
217/390
信一郎は、
瑠璃子夫人の
辛辣な皮肉に苦笑しながら訊いた。
「モウパッサンが、お嫌いなのは僕も同感ですが、じゃ、どんな作家がお好きなのです?」
「一等好きなのは、
メリメですわ。それからアナトール・フランス、オクターヴ・ミルボーなども嫌いではありませんわ。」
「メリメは、どんなものがお好きです。」
「みんないゝじゃありませんか。カルメンなんか、日本では通俗な名前になってしまいましたが、原作はほんとうにいゝじゃありませんか。」
「あの
女主人公を
何うお考えになります。」
「好きでございますよ。」
言下にそう答えながら、夫人は
嫣然と笑った。
「
妾そう思いますのよ。女に捨てられて、女を殺すなんて、本当に男性の
暴虐だと思いますの。男性の
甚だしい
我ままだと思いますの。大抵の男性は、女性から女性へと心を移していながら、平然と済していますのに、女性が反対に男性から男性へと、心を移すと、
直ぐ何とか非難を受けなければ なりませんのですもの。
妾、ホセに刺し殺されるカルメンのことを考える度
毎に、男性の我ままと暴虐とを、
憤らずには いられないのです。」
夫人の美しい顔が、興奮していた。やゝ薄赤くほてった頬が、悩しいほどに、
魅惑的であった。
信一郎は生れて初めて、男性と対等に話し得る、立派な女性に会ったように思った。彼は、はしなくも【はからずも】、自分の愛妻の
静子のことを考えずにはいられなかった。彼女は、愛らしく
慎しく従順貞淑な妻には違いない。が、趣味や思想の上では、自分の間に手の届かないように、広い/\
隔が横わっている。天気の話や、衣類の話や、食物の話をするときには立派な話相手に違いない。
が、話が少しでも、高尚になり精神的になると、もう小学生と話しているような、
もどかしさと頼りなさがあった。
218/390
同伴の登山者が、わずか一町【約100m】か二町か、離れているのなら、
麾いてやることも出来れば、声を出して呼んでやることも出来た。が、二十町も三十町も離れていれば、
何うすることも出来ない。
信一郎は、趣味や思想の生活では、
静子に対してそれほどの隔を感ぜずにはいられなかった。
が、彼は今までは、
諦めていた。日本婦人の教養が現在の程度で止まっている以上、そうしたことを、妻に求めるのは無理である。それは妻一人の責任ではなくして、日本の文化そのものの責任であると。
が、彼は今
瑠璃子夫人と会って話していると、日本にも初めて新しい、趣味の上から言っても、思想の上から言っても優に男性と対抗し得るような女性の存在し始めたことを知ったのである。夫人と話していると、妻の
静子に
依って
充されなかった欲求が、わずか三四分の同乗に
依って、十分に充たされたように思った。
そう思ったとき、その貴い三四分間は、過ぎていた。自動車は、万世橋の橋上を、やゝ速力を緩めながら、走っていた。
「いやどうも、大変有難うございました。」
信一郎は、そう
挨拶しながら、降りるために、腰を浮かし始めた。
その時に、
瑠璃子夫人は、突然何かを思い出したように言った。
「
貴君! 今晩お暇じゃなくって?」
八
「
貴君! 今晩お
暇じゃなくって?」
と、言う思いがけない問に、
信一郎は立ち上ろうとした腰を、つい降してしまった。
「暇と言いますと。」
信一郎は、夫人の問の真意を
解しかねて、ついそう
訊き返さずにはいられなかった。
「何かお宅に御用事があるかどうか、お伺いいたしましたのよ。」
「いゝえ! 別に。」
信一郎は夫人が、何を言い出すだろうかと言う、軽い好奇心に胸を動かしながら、そう答えた。
219/390
「実は……」夫人は、微笑を含みながら、
一寸言い
澱んだが、「今晩、演奏が済みますと、あの兄妹の
露西亜人を、
晩餐旁帝劇へ案内してやろうと思っていましたの。それでボックスを買って置きましたところ、向うが
止むを得ない
差支があると言って、辞退しましたから
妾一人でこれから参ろうかと思っているのでございますが、一人ボンヤリ見ているのも、何だか変でございましょう。
如何でございます、もし、およろしかったら、付き合って下さいませんか。どんなに有難いか分りませんわ。」
夫人は、心から
信一郎の同行を望んでいるように、余儀ないように誘った。
信一郎の心は、そうした突然の申出を聴いた時、可なり
動揺せずにはいなかった。今までの三四分間でさえ彼に取ってどれほど貴重な三四分間であるか分らなかった。夫人の美しい声を聞き、その華やかな表情に接し、女性として驚くべきほど、進んだ思想や趣味を味わっていると、彼には今まで、閉されていた楽しい世界が、夫人との接触に
依って、洋々と開かれて行くようにさえ思われた。
そうした夫人と、
今宵一夜を十分に、語ることが出来ると言うことは、彼にとってどれほどな、幸福と
欣びを意味しているか分らなかった。
彼は、
直ぐ同行を承諾しようと思った。が、その時に妻の
静子の面影が、チラッと頭を
掠め去った。新橋へ、人を見送りに行ったと言う以上、二時間もすれば帰って来るべき
筈の夫を、
夕餉の支度を
了えて、ボンヤリと待ちあぐんでいる妻の
邪気ない面影が、
暫らく彼の頭を支配した。その妻を、十時過ぎ、恐らく十一時過ぎ迄も待ちあぐませることが、どんなに妻の心を
傷ませることであるかは、彼にもハッキリと分っていた。
「如何でございます。そんなにお考えなくっても、手軽に
定めて下さっても、およろしいじゃありませんか。」
夫人は
躊躇している
信一郎の心に、
拍車を加えるように、やゝ高飛車にそう言った。
220/390
信一郎の顔をじっと見詰めている夫人の
高貴な
厳かに美しい面が、
信一郎の心の内の
静子の
慎しい
可愛い面影を打ち消した。
「そうだ!
静子と過すべき晩は、これからの長い結婚生活に、幾夜だってある。飽き/\するほど幾夜だってある。が、こんな美しい夫人と、一緒に過すべき機会がそう幾度もあるだろうか。こんな
浪漫的な美しい機会が、そう幾度だってあるだろうか。生涯に再びとは得がたいたゞ一度の機会であるかも知れない。こうした機会を逸しては……」
そう心の中で思うと、
信一郎の心は、
籠を放れた
鳩か何かのように、フワ/\となってしまった。彼は思い切って言った。
「もし
貴女さえ、御迷惑でなければお伴いたしてもいゝと思います。」
「あらそう。付き合って下さいますの。それじゃ、直ぐ、丸の内へ。」
夫人は、後の言葉を、運転手へ通ずるように声高く言った。
自動車は、緩みかけた爆音を、再び高く上げながら、車首を転じて、夜の
須田町の混雑の中を泳ぐように、
馳けり始めた。
電車道の、
鋪石【敷き石】が悪くなっている
故か、車台は
頻りに動揺した。
信一郎の心も、それに連れて、軽い動揺を続けている。
車が、小川町の角を、急に曲ったとき、夫人は思い出したように、とぼけたように訊いた。
「失礼ですが、奥様おありになって?」
「はい。」
「御心配なさらない! 黙って行らしっては?」
「いゝえ。決して。」
信一郎は、言葉
丈は強く言った。が、その声には一種の不安が響いた。
九
帝劇の南側の車寄の階段を、夫人と一緒に上るとき、
信一郎の心は、再び動揺した。この晴れがましい建物の中に、
其処にはどんな人々がいるかも知れない群衆の中へ、こうした美しい、それ
丈人目を
惹き
易い女性と、たった二人連れ立って、公然と入って行くことが、可なり気になった。
221/390
が、
信一郎のそうした心遣いを、
救けるように、舞台では今丁度幕が開いたと見え、廊下には、遅れた二三の観客が、急ぎ足に、
座席へ帰って行くところだった。
夫人と並んで、広い
空しいボックスの一番前方に、腰を下したとき、
信一郎はやっと、自分の心が落着いて来るのを感じた。舞台が、
煌々と明るいのに比べて、観客席が、ほの暗いのが
嬉しかった。
夫人は席へ着いたとき、二三分ばかり舞台を見詰めていたが、ふと
信一郎の方を振り返ると、
「本当に御迷惑じゃございませんでしたの。芝居はお嫌いじゃありませんの。」
「いゝえ! 大好きです。
尤も、今の
歌舞伎芝居には可なり不満ですがね。」
「
妾も、そうですの。外に行く
処もありませんからよく参りますが、
妾達の実生活と歌舞伎芝居の世界とは、もう丸きり違っているのでございますものね。歌舞伎に出て来る女性と言えば、みんな個性のない自我のない、古い道徳の人形のような女ばかりでございますのね。」
「同感です。全く同感です。」
信一郎は、心から夫人の
秀れた見識を
賛嘆【深く感心してほめる】した。
「親や夫に
臣従しないで、もっと自分本位の生活を送ってもいゝと思いますの。古い感情や道徳に
囚われないで、もっと解放された生活を送ってもいゝと思いますの。英国のある近代劇の女主人公が、男が
雲雀【ひばり】のように、多くの女と
戯れることが出来るのなら、女だって
雲雀のように、多くの男と戯れる権利があると申しておりますが、そうじゃございませんでしょうか。
妾もそう思うことがございますのよ。」
夫人は、周囲の静けさを
擾さないように、出来る
丈信一郎の耳に口を寄せて語りつゞけた。夫人の温い
薫るような呼吸が、
信一郎のほてった頬を、
柔かに
撫でるごとに、
信一郎は
身体中が、
溶けてしまいそうな魅力を感じた。
「でも、
貴君なんか、そうした女性は、お好きじゃありませんでしょうね。」
222/390
そう、
信一郎の耳に、あたゝかく
囁いて置きながら、夫人は顔を少し離して
嫣然と笑って見せた。男の心を、
掻き
擾してしまうような
媚が、そのスラリとした身体全体に動いた。
夫人の大胆な告白と、美しい
媚のために、
信一郎は、目が
眩んだように、フラ/\としてしまった。美しい
妖精に魅せられた少年のように、
信一郎は顔を薄赤く、ほてらせながら、たゞ
茫然と黙っていた。
夫人は、ひらりと身を
躱すように、
真面目なしんみりとした態度に帰っていた。
「でも、
妾、こんな打ち解けたお話をするのは、
貴君が初めてなのよ、文学や思想などに、理解のない方に、こんなお話をすると、
直ぐ誤解されてしまうのですもの、
妾、かねてから、
貴君のようなお友達が欲しかったの、本当に
妾の心持を、聴いて下さるような男性のお友達が、欲しかったの、二人の異性の間には、真の友情は成り立たないなどと言うのは嘘でございますわね、異性の間の友情は、恋愛への階段だなどと言うのは、嘘でございますわね。本当に自覚している異性の間なら、立派な友情が
何時までも続くと思いますの。貴方と
妾との間で、先例を開いてもいゝと思いますわ。ほゝゝゝ。」
夫人は、真の友情を説きながらも、その美しい唇は、悩ましきまでに、
信一郎の右の頬近く寄せられていた。
信一郎は、うっとりとした心持で、
阿片吸入者が、毒と知りながら、その
恍惚たる感覚に、身体を
委せるように、夫人の
蜜のように甘い呼吸と、音楽のように美しい言葉とに全身を浸していた。
客間の女王
一
帝劇のボックスに、夫人と肩を並べて、過した数時間は、
信一郎に取っては、夢とも
現とも分ちがたいような
恍惚たる時間だった。
夫人の身体全体から出る、
馥郁たる【よい香りがただよう】女性の香が、彼の感覚を
爛し【おぼれさせ】、彼の魂を溶かしたと言ってもよかった。
223/390
彼は、
其夜、半蔵門
迄、夫人と同乗して、
其処で新宿行の電車に乗るべく、彼女と別れたとき、自動車の窓から、夜目にもくっきりと白い顔を、のぞかしながら、
「それでは、
此次の日曜に
屹度お訪ね下さいませ。」と、
媚びるような美しい声で叫んだ夫人の声が、彼の心の底の底まで徹するように思った。彼は、
其処に化石した人間のように立ち止まって、葉桜の
樹下闇を、ほの/″\と照し出しながら、遠く去って行く自動車の車台の後の青色の灯を、
何時までも何時までも見送っていた。彼の頬には、
尚夫人の甘い快い
呼吸の
匂が漂うていた。彼の耳の底には、夫人の
此世ならぬ美しい声の余韻が残っていた。彼の感覚も心も、夫人に酔うていた。
彼の耳に
囁かれた夫人の言葉が、甘い
蜜のような言葉が、一つ/\記憶の
裡に
甦がえって来た。『自分を理解して
呉れる最初の男性』とか、『そんな女性をお好きじゃありませんの』と言ったような
馴々しい言葉が、それが語られた
刹那の夫人の美しい
媚のある表情と一緒に、
信一郎の頭を悩ました。
自分が、生れて始めて会ったと思うほどの美しい女性から、
唯一人の理解者として、馴々しい信頼を受けたことが、彼の心を
攪乱し、彼の心を有頂天にした。
彼の頭の
裡には、もう半面紫色になった
青木淳の顔もなかった。
謎の
白金の時計もなかった。愛している妻の
静子の顔までが、
此の
﨟たけた【気品がある】
瑠璃子夫人の美しい面影のために、
屡々掻き消されそうになっていた。
十二時近く帰って来た夫を、妻は何時ものように無邪気に、何の疑念もないように、いそいそと出迎えた。そうした
淑かな妻の態度に接すると、
信一郎は可なり、心の底に良心の
苛責を感じながらも、しかも今迄は可なり美しく見えた妻の顔が、平凡に単純に、見えるのを
何うともすることが出来なかった。
その次ぎの日曜まで、彼は絶えず、美しい夫人の記憶に悩まされた。
224/390
食事などをしながらも、彼の想像は美しい夫人を頭の中に描いていることが多かった。
「あら、何をそんなにぼんやりしていらっしゃいますの、今度の日曜は何日? と言ってお尋ねしているのに、たゞ『うむ! うむ!』と言っていらっしゃるのですもの。何をそんなに考えていらっしゃるの?」
静子は、夫がボンヤリしているのが、
可笑しいと言いながら、給仕をする手を止めて、笑いこけたりした。夫が、他の女性のことを考えて、ボンヤリしているのを、可笑しいと言って無邪気に笑いこける妻のいじらしさが、分らない
信一郎ではなかったが、それでも彼は刻々に頭の中に、浮んで来る美しい面影を
拭い去ることが出来なかった。
到頭夫人と約束した次ぎの日曜日が来た。その間の一週間は、
信一郎に取っては、一月も二月もに相当した。彼は、自分がその日曜を待ちあぐんでいるように、夫人がやっぱりその日曜を待ち望んでいて呉れることを信じて疑わなかった。
夫人が、自分を唯一人の真実の友達として、選んで呉れる。夫人と自分との
交情が発展して行く有様が、いろ/\に頭の中に描かれた。異性の間の友情は、恋愛の階段であると、夫人が言った。もしそれがそうなったら、
何うしたらよいだろう。あの自由奔放な夫人は、
屹度言うだろう。
「それが、そうなったって、別に
差支はないのよ。」
夫のない夫人はそれで差支がないかも知れない。が、自分は
何うしたらいゝだろう。妻のある自分は。結婚して間もない愛妻のある自分は。
信一郎は、そうした取りとめもない空想に頭を悩ましながら、七月の最初の日曜の午後に、夫人を訪ねるべく家を出た。
夫人を訪ねるのも、二度目であった。が、妻を
欺くのも二度目であった。
「社の連中と、午後から郊外へ行く約束をしたのでね。新宿で待ち合わして、多摩川へ行く
筈なのだよ。」
帽子を持って送って出た
静子に、彼は何気なくそう言った。
225/390
二
電車に乗ってからも、妻を欺いたと言う心持が、可なり
信一郎を苦しめた。が、あの美しい夫人が自分が尋ねて行くのを、じっと待っていて呉れるのだと思うと、電車の速力さえ
平素よりは、鈍いように思われた。
夫人と会ってからの、談話の題目などが、頭の中に次から次へと、浮んで来た。文芸や思想の話に
就ても、今日はもっと、自分の考えも話して見よう。自分の平生の
造詣を、十分
披瀝して見よう。
信一郎はそう考えながら、夫人のそれに対する
溌剌たる受答や表情を絶えず頭の中に描き出しながら
何時の間にか五番町の
広壮な夫人の邸宅の前に立っている自分を
見出した。
お
濠の
堤の青草や、向う側の堤の松や、大使館前の葉桜の林などには、十日ほど前に来たときなどよりも、もっと激しい夏の色が動いていた。
十日ほど前には、可なりビク/\と
潜った
花崗石らしい大石門を、今日は可なり自信に
充ちた歩調で潜ることが出来た。
楓を植え込んである馬車回しの中に、たゞ一本の
百日紅が、もう可なり強い日光の中に、赤く咲き乱れているのが目に付いた。
遉に、大理石の柱が、並んでいる車寄せに立ったとき、胸があやしく動揺するのを感じた。が、夫人が別れ
際に、再び繰り返して、
「本当にお暇なとき、何時でもいらしって下さい。誰も気の置ける人はいませんのよ。
妾がお山の大将をしているのでございますから。」と、言った言葉が、彼に元気を与えた。その上に、あれほど堅く約束した以上、
屹度心から待っていて
呉れるに違ない。心から、
歓び迎えて呉れるに違ない。そう思いながら、彼は「押
せ!」と、
仏蘭西語で書いてある呼鈴に手を触れた。
この前、来たときと同じように、小さい軽い靴音が、それに応じた。
扉が静に押し開けられると、一度見たことのある少年が、名刺受の銀の盆を、手にしながら、
笑靨のある
可愛い顔を現した。
226/390
「あのう、奥様にお目にかゝりたいのですが。」
信一郎が、そう言うと少年は待っていたと言わんばかりに、
「失礼でございますが、
渥美さまとおっしゃいますか。」
信一郎は軽く肯いた。
「
渥美さまなら、
直ぐ
何うかお通り下さいませ。」
少年は、
慇懃【物腰が丁寧で礼儀正しい】に
扉を開けて、奥を
指した。
「
何うか
此方へ。今日は奥の方の客間にいらっしゃいますから。」
敷き詰めてある青い
絨毯の上を、少年の後から歩む
信一郎の心は、可なり激しく興奮した。自分の名前を、ちゃんと玄関番へ伝えてある夫人の心遣いが、
嬉しかった。一夜夫人と語り明したことさえ生涯に二度と得がたい幸福であると思っていた。それが、一夜限りの
空しい夢と消えないで、実生活の上に、ちゃんとした根を下して来たことが、
信一郎には
此上なく嬉しかった。彼は絨毯の上を、しっかりと歩んでいた
積であったが、もし傍観者があったならば、その足付が、
宛然躍っているように見えたかも知れない。夫人と、美しい客間で二人
限り、何の邪魔もなしに、日曜の午後を愉快に語り暮すことが出来る。そうした楽しい予感で、
信一郎の心は、はち切れそうに一杯だった。
長い廊下を、十間ばかり来たとき、少年は立ち止まって、
其処の扉を指した。
「
此方でございます。」
信一郎は、その中に
瑠璃子夫人が、腕
椅子に身体を埋ませるように掛けながら、自分を待っているのを想像した。
彼は、興奮の余り、かすかに
顫えそうな手を扉の
把手にかけた。彼が、胸一杯の幸福と歓喜とに充されて、その扉を静かに開けたとき、部屋の中から、波の崩れるように、ワーッと彼を襲って来たものは、数多い男性が一斉に笑った笑い声だった。
彼は、不意に頭から、水をかけられたように、ゾッとして立ち
竦んだ。
三
彼がハッと立ち
竦んだ時には、もう半身は客間の中に入っていた。
227/390
凡てが、意外だった。
瑠璃子夫人の
華奢なスラリとした、身体の代りに、
其処に十人に近い男性が色々な
椅子に、いろいろな姿勢で
以って陣取っていた。
瑠璃子夫人はと見ると、これらの惑星に囲まれた太陽のように、客間の中央に、女王のような美しさと威厳とを以て、大きい、彼女の身体を
埋めてしまいそうな腕椅子に、ゆったりと腰を下していた。
楽しい予想が、滅茶々々になってしまった
信一郎は、もし事情が許すならば、一目散に逃げ出したいと思った。が、彼が一足踏み入れた瞬間に、もうみんなの視線は、彼の上に
蒐まっていた。
「あゝ、お前もやって来たのだな。」と、言ったような表情が、薄笑いと共に、彼等の顔の上に浮んでいた。
信一郎は、そうした表情に
依って可なり傷つけられた。
瑠璃子夫人は、
遉に
目敏く彼を見ると、
直ぐ立ち上った。
「あ、よくいらっしゃいました。さあ、どうぞ。お掛け下さいまし。先刻からお待ちしていました。」
そう言いながら、彼女は部屋の中を見回して、空椅子を見付けると、その空椅子の直ぐ傍にいた学生に、
「あゝ
阿部さん
一寸その椅子を!」と、言った。
するとその学生は、命令をでも受けたように、
「はい!」と、言って気軽に立ち上ると、その椅子を、夫人の美しい眼で、命ずるまゝに、夫人の腕椅子の直ぐ傍へ持って来た。
「さあ! お掛けなさいませ。」
そう言って、夫人は
信一郎を
麾ねいた。
孰らかと言えば、小心な
信一郎は、多くの先客を押し分けて、夫人の傍近く
座ることが、可なり心苦しかった。彼は、自分の頬が、可なりほてって来るのに気が付いた。
信一郎が椅子に着こうとすると夫人は
一寸押し止めるようにしながら言った。
「そう/\。
一寸御紹介して置きますわ。この方、法学士の渥美
信一郎さん。
三菱へ出ていらっしゃる。
228/390
それから、
茲にいらっしゃる方は、――そう右の端から順番に起立していたゞくのですね、さあ
小山さん!」
と彼女は傍若無人と言ってもよいように、一番縁側の近くに座っている、若いモーニングを着た紳士を指した。紳士は、
柔順にモジ/\しながら立ち上った。
「外務省に出ていらっしゃる
小山男爵。その次の方が、洋画家の
永島龍太さん。
其の次の方が、帝大の文科の
三宅さん、作家志望でいらっしゃる。その次の方が、慶応の理財科の阿部さん、第一銀行の重役の阿部保さんのお子さん。その次の方が日本生命へ出ていらっしゃる深井さん、高商出身の。その次の方が、寺島さん、御存じ? 近代劇協会にいたことのある方ですわ。其の次の方は、芳岡さん! 芳岡伯爵の長男でいらっしゃる。
彼処に一人離れていらっしゃる方が、
富田さん! 政友会の少壮代議士として有名な方ですわ。みんな私のお友達ですわ。」
夫人は、夫人の眼に操られて、次から次へと立ち上る男性を、出席簿でも調べるように、
淀みなく紹介した。
信一郎は、可なり激しい失望と幻滅とで、夫人の言葉が、耳に入らぬ程不愉快だった。自分一人を友達として選ぶと言った夫人が、十人に近い男性を、友人として自分に紹介しようとは、彼は
憤怒と
嫉妬との入り交じったような激高で、眼が
眩めくようにさえ感じた。彼は直ぐ席を
蹴って帰りたいと思った。が、何事もないように、こぼれるように微笑している夫人の美しい顔を見ていると、胸の中の激しい
憤怒が春風に解くるように、
何時の間にか、消えてゆくのを感じた。
コロネーションに結った黒髪は、夫人の長身にピッタリと似合っていた。黒地に目も
醒めるような白い
棒縞のお召が、夫人の若々しさを一層引立てゝいた。白地の
仏蘭西縮緬の丸帯に、施された
薔薇の
刺繍は、
匂入りと見え、人の心を魅するような芳香が、夫人の身辺を包んでいる。
229/390
信一郎の失望も
憤怒も、夫人の
鮮な姿を見ていると、何時の間にか
撫でられるように、和んで来るのだった。
四
「
渥美さん! 今大変な議論が始まっているのでございますよ。明治時代第一の文豪は、誰だろうと言う問題なのでございますよ。
貴君の御説も伺わして下さいませな。」
夫人は、
信一郎を会話の
圏内に入れるように、取り
做して
呉れた。が、初めて顔を合わす未知の人々を相手にして、
直ぐおいそれ! と文学談などをやる気にはなれなかった。その上に、夫人から、帝劇のボックスで聴いた「こんなに打ち解けた話をするのは、
貴君が初めてなのよ。」と、言うような、今となっては白々しい
嘘が、彼の心を
抉るように思い出された。
「だって奥さん! 独歩には、いゝ芽があるかも知れません。が、
然しあの人は先駆者だと思うのです。本当に完成した作家ではないと思うのです。」
信一郎が、何も言い出さないのを見ると、
三宅と言う文科の学生が、可なり熱心な口調でそう言った。先刻から続いて、明治末期の小説家国木田独歩を論じているらしかった。
「それに、独歩のような作品は、外国の自然派の作家には
幾何でもあるのだからね。先駆者と言うよりも、
或意味では移入者だ。日本の文学に対して、ある新鮮さを寄与したことは確だが、それがあの人の創造であるとは言われないね。外国文学の移植なのだ。ねえ! そうではありませんか、奥さん!」
モーニングを着た
小山男爵は、自分の見識に対する夫人の
賞賛を期待しているように、自信に
充ちて言った。
「でも
妾、可なり独歩を買っていますのよ。明治時代の作家で、本当に人生を見ていた作家は、独歩の外にそう沢山はないように思いますのよ。ねえ、そうじゃございませんか。
渥美さん。」
夫人は、多くの男性の中から、
信一郎丈を、選んだように、
信一郎の賛意を求めた。
230/390
が、
信一郎は不幸にも、独歩の作品を、余り沢山読んでいなかった。四五年も前に、『運命論者』や『牛肉と
馬鈴薯』などを読んだことがあるが、それが
何う言う作品であったか、もう記憶にはなかった。が、夫人に話しかけられて、たゞ
盲従的に返答することも出来なかった。その上、彼は周囲の人達に対する手前、何か
彼にか自分の意見を言わねばならぬと思った。
「そうかも知れません。が、明治文壇の第一の文豪として推すのには、少し偏しているように思うのです。やはり、月並ですが、明治の文学は紅葉などに代表させたいと思うのです。」
「尾崎紅葉!」
小山男爵は、『クスッ』と冷笑するような口調で言った。
「『金色
夜叉』なんか、今読むと全然通俗小説ですね。」
文科の学生の
三宅が、その冷笑を説明するように、
吐出すように言った。
瑠璃子夫人は、
三宅の思い切った断定を
嘉納するように、ニッと
微笑を
洩した。
信一郎は初めて、口を入れて、直ぐ
横面を
叩かれたように思った。
瑠璃子夫人までが、微笑で
以て、相手の意見を裏書したことが、更に彼の心を傷けた。彼は思わず、ムカ/\となって来るのを
何うともすることが出来なかった。彼は、自分の顔色が変るのを、自分で感じながら、死身になって口を開いた。
「『金色夜叉』を通俗小説だと言うのですか。」
彼の口調は、
詰問になっていた。
「無論、それは読む者の趣味の程度に
依ることだが、僕には全然通俗小説だと思われるのです。」
若い文科大学生は、何の遠慮もしないで、彼の信念を
昂然と語った。
「それは、
貴君が作品と時代と言うことを考えないからです。現在の文壇の標準から言えば、『金色夜叉』の
題目なんか、通俗小説に
違ないです。が、然しそれは『金色夜叉』の書かれた明治三十五年から、現在まで二十年も経過していることを忘れているからです。
231/390
現在の文壇で、
貴君が芸術的小説だと信じているものでも、二十年も
経てば、みんな通俗小説になってしまうのです。過去の作品を論ずるのには、時代と言うことを考えなければ駄目です。『金色夜叉』は今読めば通俗小説かも知れませんが、明治時代の文学としては、立派な代表的作品です。」
信一郎は、思いの外に、スラ/\と出て来る自分の雄弁に興奮していた。
「過去の文学を論ずるには、やはり文学史的に見なければ駄目です。」
彼は、きっぱりと断定するように言った。
「それもそうですわね。」
瑠璃子夫人は、
信一郎の
素人離れした主張を、感心したように、しみ/″\そう言った。
信一郎は
俄に勇敢になって来た。
五
瑠璃子夫人が、新来の
信一郎、
殊に文学などの分りそうもない会社員の
信一郎の言葉に、賛成したのを見ると、今度は
三宅と
小山男爵との二人が、躍気になった。
殊に青年の
三宅は、その若々しい浅黒い顔を、心持 薄赤くしながら可なり興奮した調子で言った。
「時代が
経てば、どんな芸術的小説でも、通俗小説になる。そんな
馬鹿な話があるものですか。芸術的小説は
何時が来たって、芸術的小説ですよ。日本の作家でも、
西鶴などの小説には、何時が来ても
亡びない芸術的分子がありますよ。天才的な
閃がありますよ。それに比べると、尾崎紅葉なんか、徹頭徹尾通俗小説ですよ。紅葉の考え方とか物の
観方と言うものは、常識の範囲を、一歩も出ていないのですからね。たゞ、
洗練された常識に過ぎないのですよ。例えば『三人妻』など言う作品だって
如何にも三人の妻の性格を描き分けてあるけれども、それが世間に有り触れた常識的
型に過ぎないのですからね。紅葉を
以て、明治時代の文学的常識を、代表させるのなら
差支えないが、第一の文豪として、紅葉を推す位なら、むしろ露伴 柳浪 美妙、そんな人の方を僕は推したいね。」
232/390
三宅の語り終るのを待ち兼ねたように、
小山男爵は、横から口を入れた。
「第一『金色
夜叉』なんか、あんなに世間で読まれていると言うことが、通俗小説である第一の証拠だよ。万人向きの小説なんかに、
碌なものがある訳はないからね。」
二人の、攻撃的な挑戦的な口調を聴いていると、
信一郎もつい、ムカ/\となってしまった。
瑠璃子夫人はと見ると、その平静な顔に、
嗾かけるような微笑を
湛えて、『
貴君も負けないで、しっかりおやりなさい。』と、言うように
信一郎の顔を見ていた。
「それは
可笑しいですな。」
そう言いながら、
信一郎は
何処か貴族的な
傲慢さが、
漂うている
小山男爵の顔をじっと見た。
「そんな暴論はありませんよ。広く読まれているのが、通俗小説の証拠ですって、そんな暴論はないと思いますね。そう言う議論をすれば、
沙翁の戯曲だって、通俗戯曲だと言うことになるじゃありませんか。ホーマアの詩だって、ダンテの神曲だって、みんな広く読まれていると言う点で、通俗的作品と言うことになりそうですね。僕は、そうは思いませんよ。それと反対に、立派な芸術的作品ほど、時代が経てば、だん/\通俗化して行くのだと思うのですね。トルストイの作品が日本などでも段々通俗化して来たように、通俗化して行かない作品こそ、
却って何かの欠陥があると思うのですね。御覧なさい! 馬琴でも西鶴でも、通俗化して行けばこそ、後代に伝わるのじゃありませんか。『金色夜叉』が通俗化しているからと言って、あの小説の芸術的価値を否定することは出来ませんよ。僕は芸術的に
秀れていればこそ、民衆の教養が進むに従って、段々通俗化して行ったのだと思うのです。紅葉の考え方や、観方はいかにも常識的かも知れません。が、然し作品全体の味とかその表現などにこそ、却って芸術的な価値があるのじゃありませんか。
233/390
あの作品の
規模の大きさから言っても、画面的に描き出す手腕から言っても、明治時代無二の作家と言ってもよいと思うのです。いや、あの
鼈甲牡丹のように、
絢爛華麗な文章
丈を取っても、優に明治文学の代表者として、推す価値が十分だと思うのです。」
信一郎は、可なり熱狂して
喋った。法科に籍を置いていたが、高等学校に入学の当時には、父の反対さえなければ、
欣んで文科をやった
筈の
信一郎は、文学に
就ては自分自身の見識を持っていた。
信一郎の意外な雄弁に、半可な文学通に過ぎない
小山男爵は、もうとっくに圧倒されたと見え、その白い頬を、心持赤くしながら、不快そうに黙ってしまった。
三宅は、言い込められた口惜しさを、
何うかして晴そうと、
駁論の筋道を考えているらしく口の辺りをモグ/\させていた。
「
渥美さんは、本当に立派な文芸批評家でいらっしゃる。
妾全く感心してしまいましたわ。」
瑠璃子夫人は、心から感心したように、
賞賛の微笑を
信一郎に注いだ。
信一郎は、女王の御前仕合で、見事な勝利を
獲た騎士のように、晴れがましい揚々たる気持になっていた。
「然し……」と、
三宅と言う青年が、必死になって
駁論を初めようとした時だった。
廊下に面した
扉を、外からコツ/\と
叩く音がした。
六
「
誰方?」
夫人は、扉を
叩く音に応じてそう言った。
「僕です。」
外の人は
明晰な、美しい声でそう答えた。
「あら、
秋山さんなの。丁度よいところへ。」
夫人は、そう言いながら、いそ/\と
椅子を離れた。
信一郎が、入って来たときは、夫人はたゞ椅子から、腰を浮かした
丈だったのに。
夫人が、手ずから扉を開けると、『僕です。』と、名乗った男は、軽く
会釈をしながら、入って来た。
信一郎は、一目見たときに、
何処かで見覚えのある顔だと思ったが、
一寸思い出せなかった。
234/390
が、一目見た
丈で、作家か美術家であることは、
直ぐ
解った。白い面長な顔に、黒い長髪を
獅子の立髪か何かのように、振り乱していた。が、頭は極端に奔放であるにも
拘わらず、
薩摩上布の
衣物に、
鉄無地の
絽の薄
羽織を着た姿は、可なり
瀟洒たるものだった。夫人はその男とは、立ちながら話した。
「
暫く
御無沙汰致しました。」
「ほんとうに長い間お見えになりませんでしたのね。箱根へお
出でになったって、新聞に出ていましたが、行らっしゃらなかったの。」
「いや、何処へも行きやしません。」
「それじゃ、やっぱり例の長編で苦しんでいらしったの。本当に、
妾の家へいらっしゃる道を忘れておしまいになったのかと思っていましたの。ねえ!
三宅さん。」
夫人は、
三宅と言う学生を顧みた。
「やあ!」
「やあ!」
三宅とその男とは顔を見合して
挨拶した。
「本当に、暫らくお見えになりませんでしたね。
貴君が、いらっしゃらないと、
此処の
客間も
淋しくていけない。」
三宅は、後輩が先輩に迎合するような、口の
利き方をした。
「さあ!
秋山さん!
此方へお掛けなさいませ。本当によい所へ
入らしったわ。
今貴君に断定を下していたゞきたい問題が、起っていますのよ。」
そう言いながら、今度は夫人自ら、空いた椅子を、自分の傍へ、置き換えた。
「さあ! お掛けなさいませ!
貴君の御意見が、伺いたいのよ。ねえ!
三宅さん!」
信一郎に、説き
圧されていた
三宅は、援兵を得たように、勇み立った。
「さあ、是非
秋山さんの御意見を伺いたいものです。ねえ!
秋山さん、今明治時代の第一の小説家は、誰かと言う問題が、起っているのですがね、
貴君のお考えは、
何うでしょう。こう言う問題は、専門家でなければ駄目ですからね。」
三宅は、最後の言葉を、
信一郎に当てこするように言った。
235/390
瑠璃子夫人までが、その最後の言葉を説明するように
信一郎に言った。
「
此の方、
秋山正雄さん、御存じ! あの
赤門派の新進作家の。」
秋山正雄、そう言われて見れば、最初見覚えがあると思ったのは、間違っていなかったのだ。
信一郎が一高の一年に入った時、その頃三年であった
秋山氏は文科の秀才として、
何時も校友会雑誌に、詩や評論を書いていた。それが、大学を出ると、見る間に、メキ/\と売り出して、今では新進作家の第一人者として文壇を圧倒するような盛名を
馳せている。その上、教養の広く多方面な点では若い小説家としては珍らしいと言われている人だった。
信一郎は、自分が有頂天になって、
喋べった文学論が、こうした人に
依って、批判される結果になったかと思うと、可なりイヤな
羞しい気がした。有頂天になっていた彼の心持は
忽ち
奈落の底へまで、引きずり落された。場合に
依っては、
此の教養の深い文学者――しかも先輩に当っている――と、文学論を戦わせなければ ならぬか と思うと、彼は思わず冷汗が背中に
湧いて来るのを感じた。
信一郎の心が、不快な動揺に悩まされているのを
外に、
秋山氏は、今火を
点けた金口の
煙草を
燻らしながら、落着いた調子で言った。
「それは、大問題ですな。僕の意見を述べる前に、
兎に
角皆様の御意見を承わろうじゃありませんか。」
そう言いながら、
秋山氏は
額に
掩いかゝる長髪を、二三度続けざまに後へ
掻き上げた。
七
「大分いろ/\な御意見が出たのですがね。
茲にいらっしゃる
渥美君、確かそう
仰しゃいましたね。」
三宅は、
一寸信一郎の方を振り
顧った。「大変紅葉をお説きになるのです。紅葉を
措いて明治時代の文豪は、外にないだろうと、こう仰しゃるのです。文章
丈を取っても、
鼈甲牡丹のような
絢爛さがあるとか何とか仰しゃるのです。」
236/390
三宅が、
秋山氏に
信一郎の持説を伝えている語調の中には、『
此の
素人が』と言った語気が、ありありと動いていた。
秋山氏は、いかにも小説家らしく澄んだ眼で、
信一郎の方をジロリと
一瞥したが、吸いさしの金口の火を、鉄の灰皿で、擦り消しながら、「鼈甲牡丹の絢爛さ! なるほど、うまい形容だな。だが、
擬の鼈甲牡丹なら三四十銭で、
其処らの小間物屋に売っていそうですね。」
瑠璃子夫人を初め、一座の人々が、
秋山氏の皮肉を、どっと笑った。
「紅葉山人の絢爛さも、きィちゃん、みィちゃん的読者を
欣ばせる擬の鼈甲牡丹じゃありませんかね。
一寸見は、
光沢があっても、触って見ると、牛の骨か何かだと言うことが、
直ぐ分りそうな。」
秋山氏が、文壇での論戦などでも、自分自身の
溢れるような才気に乗じて、常に相手を
馬鹿にしたような、おひゃらかしてしまうような態度に出ることは、
信一郎は
予々知っていた。それが、妙な羽目から、自分一人に向けられているのだと思うと、
信一郎は不愉快とも
憤怒とも付かぬ気持で、胸が一杯だった。が、こうした文学者を相手に、議論を戦わす勇気も自信もなかった。相手の
辛辣な皮肉を黙々として、聴いている外はなかった。たゞ、文壇の花形ともある
秋山氏が、自分などの素人を捕えて、真向から皮肉を浴びせているのが、可なり大人気ないようにも思われて、それが恨めしくも、
憤ろしくもあった。
「第一『金色
夜叉』なんか、今読んで見ると全然通俗小説ですね。」
秋山氏は、一刀の下に、何かを両断するように言った。
瑠璃子夫人は、『おや。』と言ったような軽い叫びを挙げながら言った。
「
三宅さんも、先刻そんなことを言ったのよ。あ、分った!
三宅さんのは
秋山さんの受売だったのね。」
三宅は、赤面したように、頭を
掻いた。一座は、
信一郎を除いて、皆ドッと笑った。
237/390
秋山氏は、皮肉な微笑を浮べながら、
「いや、
三宅君と期せずして意見を同じくしたのは、光栄ですね。」
一座は、
秋山氏の皮肉を、又ドッと笑った。その笑が静まるのを待ち兼ねて、
三宅が言った。
「今僕が、その『金色夜叉』通俗小説論を持ち出したのです。すると、
渥美さんが言われるのです。現在の我々の標準で律すれば、『金色夜叉』は通俗小説かも知れない。が、作品を論ずるには、その時代を考えなければならない。文学史的に見なければならない。こう仰しゃるのです。」
「文学史的に見る。それは
卓見だ。」
秋山氏は、ニヤ/\と冷笑とも微笑とも付かぬ笑いを浮べながら言った。
「だが、紅葉山人と同時代の人間が、みんな我々の眼から見て、通俗小説を書いているのなら、『金色夜叉』が通俗小説であっても、一向
差支ないが、紅葉山人と同時代に生きていて、我々の眼から見ても、立派な芸術小説をかいている人が外にあるのですからね。
幾何文学史的に見ても、紅葉を第一の小説家として、許すことは僕には出来ませんね。文学史的に見れば、紅葉山人などは、明治文学の代表者と言うよりも、徳川時代文学の
殿将ですね。あの人の考え方にも、
観方にも描き方にも、徳川時代文学の殻が、こびりついているじゃありませんか。」
遉の
信一郎も、黙っていることは出来なかった。
「そう言う観方をすれば、明治時代の文学は、全体として徳川時代の文学の伝統を引いているじゃありませんか。何も、紅葉一人
丈じゃないと思いますね。」
「いや、徳川時代文学の
糟粕などを、少しも
嘗めないで、明治時代独特の小説をかいている作家がありますよ。」
「そんな作家が、本当にありますか。」
信一郎も可なり激した。
「ありますとも。」
秋山氏は、水の
如く冷たく言い放った。
汝妖婦よ!
一
「誰です。一体その人は。」
238/390
信一郎は、可なり
急き込んで
訊いた。
が、
秋山氏は落着いたまゝ、冷然として言った。
「
然し、こう言う問題は、
銘々の主観の問題です。僕が、
此の人がこうだと言っても、
貴君にそれが分らなければ、それまでの話ですが、
兎に
角言って見ましょう。それは、誰でもありません。あの
樋口一葉です。」
秋山氏は、それに少しの疑問もないように、ハッキリと言い切った。
瑠璃子夫人は、それを聴くと、躍り上るようにして
欣んだ。
「一葉!
妾スッカリ忘れていましたわ。そう/\一葉がいますね。
妾が、今まで読んだ小説の女主人公の中で、あの『たけくらべ』の中の
美登利ほど好きな女性はないのですもの。」
「
御尤もです。勝気で意地っ張なところが
貴女に似ているじゃありませんか。」
秋山氏は、夫人を
揶揄するように言った。
「まさか。」
と、夫人は打ち消したが、
其の比較が、彼女の心持に
媚び得たことは明かだった。
「一葉! そう/\あれは天才だ、
夭折した天才だ! 一葉に比べると、紅葉なんか才気のある凡人に過ぎませんよ。」
小山男爵は、
信一郎に言い伏せられた
腹癒がやっと出来たように、得々として口を挟んだ。
「そうだ! 『たけくらべ』と『金色
夜叉』とを比べて見ると、どちらが通俗小説で、どちらが芸術小説だか、ハッキリと分りますね。
渥美さんの御意見じゃ、『金色夜叉』よりも六七年も早く書かれた『たけくらべ』の方が、もっと早く通俗小説になっている
筈だが、我々が今読んでも『たけくらべ』は通俗小説じゃありませんね。決してありませんね。」
三宅も、
信一郎の方を意地悪く見ながら、そう言った。
其処にいた多くの人々も、銘々に口を出した。
「『たけくらべ』! ありゃ明治文学第一の傑作ですね。」
「ありゃ、僕も昔読んだことがある。ありゃ確にいゝ。」
239/390
「あゝそう/\、
吉原の附近が、光景になっている小説ですか、それなら私も読んだことがある。坊さんの息子か何かがいたじゃありませんか。」
「女主人公が、それを
潜に恋している。が、勝気なので、口には言い出せない。その
中に、
一寸した意地から不和になってしまう。」
「
信如とか何とか言う坊さんの子が、
下駄の緒を切らして困っていると、美登利が、紅入友禅か何かの
布片を出してやるのを、信如が妙な意地と遠慮とで使わない。あの光景なんか今でもハッキリと思い出せる。」
代議士の
富田氏までが、そんなことを言い出した。こうした一座の迎合を、
秋山氏は冷然と、聴き流しながら、最後の断案を下すように言った。
「とにかく、明治の作家の
中で、本当に人間の心を描いた作家は、一葉の外にはありませんからね。
硯友社の作家が、文章などに浮身を
窶して【身のやせるほど熱中して】、本当に人間が描けなかった中で、一葉
丈は
嶄然として独自の位置を占めていますからね。一代の
驕児【だだっこ】
高山樗牛が、一葉
丈には頭を下げたのも無理はありませんよ。僕は明治時代第一の文豪として一葉を推しますね。」
秋山氏は、
如何にも芸術家らしい冷静と力とを以て、
昂然とそう言い放った。
信一郎は、もう先刻からじり/\と
湧いて来る不愉快さのために、一刻もじっとしてはいられないような心持だった。
凡てが不愉快だった。
凡てが、
癪に触った。
樫の棒をでも持って、一座の人間を片ッ端から、殴り付けてやりたいようにいら/\していた。
そうした
信一郎の心持を、知ってか知らずにか、夫人は何気ないように微笑しながら、
「
渥美さん! しっかり遊ばしませ。大変お旗色が悪いようでございますね。」
二
信一郎が、フラ/\と立ち上るのを見ると、皆は彼が
大に論じ始めるのかと思っていた。が、今彼の心には、
樋口一葉も尾崎紅葉もなかった。
240/390
たゞ、
瑠璃子夫人に対する――夫人の移り
易きこと浮草の
如き不信に対する憎みと、恨みとで胸の中が燃え狂っていたのだった。
彼は一刻も早く
此席を脱したかった。彼は
其処に
蒐まっている男性に対しても、激しい
憎悪と反感とを感ぜずにはいられなかった。
「奥さん! 僕は失礼します。僕は。」
彼は、感情の激しい
渦巻のために、何と
挨拶してよいのか分らなかった。
彼は、
吃りながら、そう言ってしまうと、泳ぐような手付で、並んだ
椅子の間を分けながら
扉の方へ急いだ。
遉に一座の者は
固唾を飲んだ。今まで
瑠璃子夫人を
挟さんで、
鞘当的な論戦の花が咲いたことは幾度となくあったが、そんな時に、形もなく打ち負された方でも、こんなにまで取り
擾したものは一人もなかった。
真蒼な顔をして、憤然として、立ち
出でて行く
信一郎を、皆は
呆気に取られて見送った。
信一郎は、もう美しい
瑠璃子夫人にも何の未練もなかった。後に残した華やかな客間を、心の中で
唾棄した。夫人の
艶美な微笑も
蜜のような言葉も、今は
空の空なることを知った。
否、空の空なるか、ではなくして、その中に恐ろしい毒を持っていることを知った。それは、目的のための毒ではなくして、毒のための毒であることを知った。彼女は、目的があって、男性を
翻弄しているのではなく、たゞ翻弄することの面白さに、翻弄していることを知った。自分の男性に対する魅力を、楽しむために、無用に男性を魅していることを知った。丁度、激しい毒薬の所有者が、その毒の効果を自慢して
妄に人を毒殺するように。
『
汝 妖婦よ!』
信一郎は、心の中で、そう叫び続けた。彼は、客間から玄関までの十間に近い廊下を、電光の
如くに歩んだ。
周章てゝ見送ろうとする玄関番の少年にも、彼は
一瞥をも与えなかった。
彼は突き破るような勢いで、玄関の扉に手をかけた。
が、その
刹那であった。
241/390
信一郎の興奮した耳に、冷水を注ぐように、
「
渥美さん!
渥美さん!
一寸お待ち下さい。」と、言う夫人の美しい言葉が聞えて来た。
信一郎はそれを船人の命を奪う
妖魚の声として、そのまゝ聞き流して、戸外へ飛び出そうと思った。が、彼のそうした決心にも
拘わらず、彼の右の手は、しびれたように、扉の
把手にかゝったまゝ動かなかった。
「
何うなすったのです。本当にびっくりいたしましたわ。何をそんなにお腹立ち遊ばしたの。」夫人は小走りに
信一郎に近づきながら、
可愛い小さい息をはずませながら言った。
心配そうに見張った黒い美しい
眸、
象牙彫のように気高い鼻、端正な唇、
皎い
艶やかな頬、こうした
神々しい
﨟たけた夫人の顔を見ていると、彼女の嘘、偽りが、夢にもあろうとは思われなかった。彼女の微笑や言葉の中に、
微塵賤しい虚偽が、潜んでいようとは思われなかった。
「
何うして、そんなに早くお帰り遊ばすの。
妾、皆さんがお帰りになった後で、
貴君と
丈で、ゆっくりお話していたかったの。
秋山さんと言う方は、本当に
あまんじゃくよ。反対のために反対していらっしゃるのですもの。それをまた、みんなが迎合するのだから、
嫌になってしまいますわね。
客間にいらっしゃるのがお嫌なら、
図書室の方へ、御案内いたしますわ。あなたのお好きな『紅葉全集』でも、お読みになって、待っていらっしゃいませ。
妾、もう三十分もすれば、何とか口実を見付けて、皆さんに帰っていたゞきますわ。ほんの少しの間、待っていて下さらない?」
三
『ほんの少し待っていて下さらない?』と、言う夫人の言葉を聴くと、『
汝 妖婦よ!』と、心の中で叫んでいた
信一郎の決心も、またグラ/\と揺ごうとした。
が、彼は揺ごうとする自分の心を、辛うじて、最後の所で、グッと引き止めることが出来た。
242/390
お前はもう既に、夫人の
蜜のような言葉に乗ぜられて、散々な目にあったではないか。再びお前は、夫人から何を求めようとしているのだ。お前が夫人の言葉を信ずれば、信ずるほど、夫人のお前に与うるものは、
幻滅と侮辱との外には、何もないのだ。男性の威厳を思え! 今日夫人から受けた幻滅と侮辱とは、まだ夫人に対するお前の幻覚を破るのに足りなかったのか。男性の威厳を思え! 夫人の言葉をスッパリと突き放してしまえ!
信一郎の心の奥に、弱いながら、そう叫ぶ声があった。
信一郎は、心の中に夫人の美しさに、抵抗し得る
丈の勇気を、やっと
蒐めながら言った。
「でも、奥さん! 私、このまゝお
暇いたした方がいゝように思うのです。あゝした立派な方が
蒐まっている客間には、私のような者は全く無用です。どうも、大変お邪魔しました。」
信一郎は、可なりキッパリと断りながら、急いで
踵を返そうとした。
「まあ!
貴君、何をそんなにお怒り遊ばしたの、何か
妾が
貴君のお気に触るようなことをいたしましたの、折角いらして下すって、
直ぐお帰りになるなんて、
余りじゃありませんか。客間に
蒐まっていらっしゃる方なんて、
妾仕方なくお相手いたしておりますのよ。
妾が、
妾の方から求めてお友達になりたいと思ったのは、本当は
貴君お一人なのですよ。」
信一郎は、そう言いながら、何事もないように、笑っている夫人の美しさに、ある
凄味をさえ感じた。夫人の
口吻から察すれば、夫人は周囲に集まっている男性を、
蠅同様に思っているのかも知れない。もし、そうだとすると、
信一郎なども、新来の初心な蠅として、たゞ
一寸した珍しさに引き止められているのかも知れない。そうした
上部丈けの甘言に乗って、ウカ/\と夫人の
掌上などに、止まっている中には、あの
象牙骨の
華奢な扇子か何かで、ビシャリと
一打にされるのが、当然の帰結であるかも知れないと
信一郎は思った。
243/390
「でも、今日は帰らせていたゞきたいと思います。又改めて伺いたいと思いますから。」
信一郎は、可なり強くなって、キッパリと言った。
夫人も、
遉にそれ以上は、勧めなかった。
「あらそう。
何うしてもお帰りになるのじゃ仕方がありませんわ。やっぱり、
妾の心持が、
貴君にはよく分らないのですね。じゃ、左様なら。」
夫人は、淡々として、そう言い切ると、グルリと身体を
回らして、客間の方へ歩き出した。
夫人から引き止められている内は、それを振切って行く勇気があった。が、こう
あっさりと軽く突き放されると、
信一郎は何だか、拍子抜けがして
淋しかった。
夫人と別れてしまうことに
依って、異常な
絢爛な人生の悦楽を、味う機会が、永久に失われてしまうようにも思われた。自分の人生に、明けかゝった
冒険の
曙が、またそのまゝ夜の方へ、逆戻りしたようにも思われた。
が、危険な華やかな毒草の美しさよりも、
慎しい、しおらしい花の美しさが、今彼の心の
裡によみがえった。
淋しいしかし安心な、暗いしかし質素な心持で、彼は大理石の丸柱の立った車寄を静に下った。もう
此の家を二度と
訪うことはあるまい。あの美しい夫人の面影に、再び
咫尺することもあるまい。彼がそんなことを考えながら、トボ/\と門の方へ歩みかけた時だった。彼はふと、門への道に添う植込みの間から、左に透けて見える庭園に、語り合っている二人の男性を見たのである。彼は、その人影を見たときに、ゾッとして
其処に立ち止まらずにはいられなかった。
四
信一郎が、
駭いて立ち
竦んだのも、無理ではなかった。玄関から門への道に添う植込の間から、透けて見える、キチンと整った庭園の丁度真中に、庭石に腰かけながら、語り合っている二人の男を見たのである。
二人の男を見たことに、不思議はなかった。
244/390
が、その二人の男が、両方とも、彼の心に恐ろしい激動を与えた。
彼の方へ面を向けて、腰を下している学生姿の男を見た時に、彼は思わず『アッ!』と、声を立てようとした。品のよい鼻、
白皙【色が白い】の
面、それは自分の介抱を受けながら、横死【不慮の死】した
青木淳と
瓜二つの顔だった。それが、白昼の、かほど、けざやかな太陽の下の遭遇でなかったならば、彼はそれを不慮の死を遂げた青年の亡霊と思い
過ったかも知れなかった。
が、彼の理性が働いた。彼は一時は、
駭いたものの
直ぐその青年が、いつかの葬場で見たことのある
青木淳の弟であることに、気が付いた。
然し、彼が最初の
駭きから、やっと回復した時、今度は第二の
駭きが彼を待っていた。青年と相対して語っている男は、
紛れもなく海軍士官の軍服を着けている。海軍士官の軍服に気が付いたとき、
信一郎の頭に、電光のように
閃いたものは、
村上海軍
大尉という名前であった。青年が、
遺して行った手記の中に出て来る
村上海軍大尉と言う名前だった。
青木淳が、
烈しい
忿恨【腹を立てて恨む】を
以て、ノートに書き付けた文句が、
信一郎の心に、アリ/\と
甦って来た。
245/390
『昨日自分は、村上海軍大尉と共に、彼女の家の庭園で、彼女の帰宅するのを待っていた。その時に、自分はふと、大尉がその軍服の腕を捲り上げて、腕時計を出して見ているのに気が付いた。よく見ると、その時計は、自分の時計に酷似しているのである。自分はそれとなく、一見を願った。自分が、その時計を、大尉の頑丈な手首から、取り外したときの駭きは、何んなであったろう。若し、大尉が其処に居合せなかったら、自分は思わず叫声を挙げたに違ない。』
信一郎は、
青木淳の弟と語っている軍服姿の男を見たときに、それが手記の中の
村上大尉であることに、もう何の疑もなかった。もし、それが、
村上海軍大尉であるとしたならば、
青木淳と大尉との双方に、同じ
白金の時計を与えて、『これは、
妾の
貴君に対する愛の印として、
貴君に差し上げますのよ。本当は、かけ替のない秘蔵の品物ですけれど。』と、言いながら二人を
翻弄し去った女性が、果して
何人であるかが、
信一郎にはもうハッキリと分ってしまった。
『
汝 妖婦よ!』
彼は心の
中で再びそう声高く、叫ばずにはいられなかった。
が、
信一郎の心を、もっと痛めたことは、兄が恐ろしく美しい
蜘蛛の糸に操られて、悲惨な横死【不慮の死】を――形は
奇禍【思いがけない災難】であるが、心は自殺を――遂げたと言うことを夢にも知らないで、その肉親の弟が、又同じ蜘蛛の網に、ウカ/\とかゝりそうになっていることだった。いや恐らくかゝっているのかも知れない。いや、兄と同じように、もう白金の時計を
貰っているのかも知れない。あゝして、話している中に、相手の海軍大尉の腕時計に、気が付くのかも知れない。兄の血と同じ血を持っている
筈の弟は、それを見て兄と同じように
激高する。兄と同じように自殺を決心する。
246/390
そう考えて来ると、
信一郎は、烈々と輝いている七月の太陽の下に、
尚周囲が暗くなるように思った。兄が陥った
深淵へ又、弟が
陥ちかかっている。それほど、悲惨なことはない。そう思うと、
信一郎は、
『おい! 君!』と、高声に注意してやりたい希望に動かされた。が、それと同時に、血を分けた兄弟を、兄に悲惨な死を遂げしめた上に、更に弟をも近づけて、翻弄しようとする毒婦を憎まずにはいられなかった。
『
汝 妖婦よ!』彼は、心の中でもう一度そう叫んだ。が、
信一郎が、これほど心を痛めているにも
拘らず、当の青年は、何が
可笑しいのか、軽く上品に笑っているのが、手に取るように聞えて来た。
信一郎は、見るべからざるものを見たように、面を
背けて足早に門を
駈け
出でたのである。
五
新宿行の電車に乗ってからも、
信一郎の心は
憤怒や
憎悪の
烈しい渦巻で一杯だった。
瑠璃子夫人こそ、白金の時計を返すべき当の本人であることが
解ると、夫人の美しさや気高さに対する
賛嘆の【深く感心してほめる】心は、影もなくなって、憎悪と軽い恐怖とが、
信一郎の心に
湧いた。
青木淳の死の原因が、直接ではなくても、間接な原因が、自分であることを知りながら、
嫣然として時計を受け取った夫人の態度が、
空恐しいように思い返された。『
妾が預って本当の持主に返して上げます。』と、事もなげに言い放った夫人の美しい面影が、
空恐ろしいように
想い返された。
247/390
『が、彼女と面と向って、不信を詰責しようとしたとき、自分は却って、彼女から忍びがたい恥かしめを受けた。自分は小児の如く、翻弄され、奴隷の如く卑しめられた。而も美しい彼女の前に出ると、唖のようにたわいもなく、黙り込む自分だった。自分は憤と恨との為にわな/\顫えながら而も指一本彼女に触れることが出来なかった。自分は力と勇気とが、欲しかった。彼女の華奢な心臓を、一思いに突き刺し得る丈の力と勇気とを。……彼女を心から憎みながら、しかも片時も忘れることが出来ない。彼女が彼女のサロンで多くの異性に取囲まれながら、あの悩ましき媚態を惜しげもなく、示しているかと思うと、自分の心は、夜の如く暗くなってしまう。自分が彼女を忘れるためには、彼女の存在を無くするか、自分の存在を無くするか二つに一つだと思う。……そうだ、一層死んでやろうかしら。純真な男性の感情を弄ぶことが、どんなに危険であるかを、彼女に思い知らせてやるために。そうだ、自分の真実の血で、彼女の偽の贈物を、真赤に染めてやるのだ。そして、彼女の僅に残っている良心を、恥しめてやるのだ。』
青木淳の
遺して
逝った手記の言葉が、太陽の光に
晒されたように、何の疑点もなくハッキリと
解って来た。彼女が、
瑠璃子夫人であることに、もう何の疑いもなかった。純真な青年の感情を
弄んで彼を死に導いた彼女が、
瑠璃子夫人であることに、もう何の疑いもなかった。
『
汝 妖婦よ!』
信一郎は、十分な確信を
以て、心の中でそう叫んだ。青年は、彼女に対して、綿々の【長く積もり積もった】恨を
呑んで死んだのである。白金の時計を『返して
呉れ。
248/390
』と言うことは、『
叩き返して呉れ。』と言うことだったのだ。彼女の僅に残っている良心を恥かしめてやるために、叩き返して呉れと言うことだった。
そうだ! それを
信一郎は、
瑠璃子夫人のために、不得要領に【何が何だかよく分からずに】
捲き上げられてしまったのである。
『取り返せ。もう一度取り返せ! 取り返してから、叩き返してやれ!』
信一郎の心に、そう叫ぶ声が起った。『それで彼女の僅に残っている良心を恥かしめてやれ。お前は死者の神聖な
遺託に背いてはならない。これから取って返して、お前の義務を尽さねばならない。あれほど青年の恨の
籠った時計を、不得要領に、返すなどと言うことがあるものか。もう一度やり直せ。そしてお前の当然な義務を尽せ。』
信一郎の心の
中の
或る者が、そう叫び続けた。が、心の中の他の者は、こう
呟いた。
『危きに近寄るな。お前は、あの美しい夫人と太刀打が出来ると思うのか。お前は、今の
今迄危く夫人に翻弄されかけていたではないか。夫人の張る網から、やっと逃れ得たばかりではないか。お前が血相を変えて
駈付けても、また夫人の美しい魅力のために、手もなく丸められてしまうのだ。』
こうした硬軟二様の心持の争いの
裡に、
信一郎は
何時の間にか、自分の家近く帰っていた。停留場からは、一町とはなかった。
電車通を、右に折れたとき、半町ばかり
彼方の自分の家の前あたりに、一台の自動車が、止まっているのに気が付いた。
六
信一郎の興奮していた
眸には、最初その自動車が、漠然と映っている
丈だった。それよりも、彼は自分の家が、近づくに従って、『社の連中と多摩川へ行く。』などと言う口実で、家を飛び出しながら、二時間も
経たない
裡に、早くも帰って行くことが、心配になり出した。また早く、帰宅したことに就いて、妻を納得させる
丈の、口実を考え出すことが、可なり心苦しかった。
249/390
彼は、電車の中でも、
何処か外で、ゆっくり時間を
潰して、夕方になってから、帰ろうかとさえ思った。が、彼の本当の心持は、一刻も早く家に帰りたかった。妻の
静子の優しい温順な面影に、一刻も早く接したかった。危険な冒険を経た者が、平和な休息を、
只管 欲するように、他人との
軋轢や争いに胸を傷つけられ、
瑠璃子夫人に対する幻滅で心を痛めた
信一郎は、家庭の持っている平和や、妻の持っている
温味の
裡に、一刻も早く、浴したかったのである。
縦令、もう一度妻を
欺く口実を考えても、一刻も早く家に帰りたかったのである。
が、彼が一歩々々、家に近づくに従って、自分の家の前に停っている自動車が、気になり出した。
勿論、
此の近所に自動車が、停っていることは、珍らしいことではなかった。彼の家から、つい五六軒向うに、ある実業家の
愛妾が、住っているために、三日にあげず、自動車がその家の前に、永く長く停まっていた。今日の自動車も、やっぱり
何時もの自動車ではないかと、
信一郎は最初思っていた。が、近づくに従って、何時もとは、可なり停車の位置が違っているのに気が付いた。
何うしても、彼の家を訪ねて来た訪客が、乗り捨てたものとしか見えなかった。
が、段々家に近づくに従って、恐ろしい事実が、
漸く分って来た。何だか見たことのある車台だと言う気がしたのも、無理ではなかった。それは、
紛れもなくあの青色大型の、
伊太利製の自動車だった。
信一郎も一度乗ったことのある、あの自動車だった。そうだ、
此の前の日曜の夜に、
荘田夫人と同乗した自動車に、寸分も違っていなかった。
夫人が、訪ねて来たのだ! そう思ったときに、
信一郎の心は、
烈しく打ち
叩かれた。当惑と、ある恐怖とが、胸一杯に
充ち満ちた。
出先で、
妖怪に
逢い
這々の体で自分の家に逃げ帰ると、その恐ろしい魔物が、先回りして、自分の家に入り込んでいる。
250/390
昔の
怪譚にでもありそうな、絶望的な出来事が、
信一郎の心を、底から
覆してしまった。
瑠璃子夫人の美しい脅威に
戦いて、家庭の平和の
裡に隠れようとすると、相手は、先回りして、その家庭の平和をまで、
掻き
擾そうとしている。静かな
慎しい家庭と、温和な妻の心をまでも掻き
擾そうとしている。
信一郎は、当惑と恐怖とのために、
暫くは、道の真中に立ち
竦んだまゝ、
何うしてよいか分らなかった。その
裡に、
信一郎の絶望と、恐怖とは、夫人に対する激しい反抗に、変って行った。
温和しい妻が、美しい、
溌剌たる夫人の突然な訪問を受けて
狼狽している有様が、あり/\と浮んで来た。自分が、妻に内密で、ああした美しい夫人と、交りを結んでいたと言うことが、どんなに彼女を痛ましめたであろうかと思うと、
信一郎は一刻も、じっとしてはいられなかった。
温和しい妻が夫人のために、どんなに言いくるめられ、どんなに
翻弄されているかも知れぬと思うと、一刻も
逡巡しているときではないと思った。自分の彼女に対する不信は、後でどんなにでも、許しを
乞えばいゝ。今は妻を、美しい夫人の圧迫から救ってやるのが第一の急務だと思った。
それにしても、夫人は何の恨みがあって、これほどまで、
執拗に自分を悩ますのであろう。自分を欺いて、客間へ
招んで恥を掻かせた上に、自分の家庭をまで、掻き
擾そうとするのであろうか。今は夫人の美しさに、
怖れているときではない。戦え! 戦って、彼女の
僅に残っているかも知れぬ良心を恥しめてやる時だ! そうだ! 死んだ
青木淳のためにも、
弔合戦を戦ってやる時だ! そう思いながら、
信一郎は必死の勇を振って、敵の城の中へでも飛び込むような勢で、自分の家へ飛び込んだのである。
251/390
七
玄関先に立っている、もしくは客間に上り込んでいる
妖艶な夫人の姿を、想像しながら、それに必死に突っかゝって行く覚悟の
臍を固め【腹を固め】ながら、
信一郎は自分の家の門を、潜った。
見覚えのある運転手と助手とが、玄関に腰を下しているのが
先ず眼に入った。
信一郎は、彼等を悪魔の手先か何かを見るように、
憎悪と反感とで
睨み付けた。が、夫人の姿は見えなかった。手早く眼をやった玄関の敷石の上にも、夫人の
履物らしい履物は脱ぎ捨てゝはなかった。
信一郎は、少しは救われたように、ホッとしながら、玄関へ入ろうとした。
運転手は素早く彼の姿を見付けた。
「いやあ。お帰りなさいまし。
先刻からお待ちしていたのです。」
彼は、
馴れ/\しげに、話しかけた。
信一郎はそれが、可なり不愉快だった。が、運転手は
信一郎を、もっと不愉快にした。彼は、無遠慮に大きい声で、奥の方へ呼びかけた。
「奥さん! やっぱり、お帰りになりましたよ。
何処へもお回りにならないで、直ぐお帰りになるだろうと思っていたのです。」
運転手は、いかにも自分の予想が当ったように、得意らしく言った。運転手が、そう言うのを聴いて、
信一郎は冷汗を流した。運転手と妻とが、どんな会話をしたかが、彼には明かに分った。
「御主人はお帰りになりましたか。」
運転手は、最初そう
訊ねたに違いない。
「いゝえ、まだ帰りません。」
妻は、自身
若しくは女中をしてそう答えさせたに違いない。
「それじゃ、お帰りになるのをお待ちしていましょう。」
運転手は、そう言ったに違いない。
「あの、会社の人達と一緒に、多摩川へ行きましたのですから、帰りは夕方になるだろうと思います。」
何も知らない、
信一郎を信じ切っている妻は、そう答えたに違いない。それに対して、この無遠慮な運転手はこう言い切ったに違いない。
252/390
「いゝえ、直ぐお帰りになります。
只今私の宅からお帰りになったのですから、
外へお回りにならなければ三十分もしない
裡に、お帰りになります。」
初めて会った他人から、夫の
背信を教えられて、妻は可なり心を傷けられながら赤面して黙ったに違いない。そう思うと、突然運転手などを寄越す
瑠璃子夫人に、彼は心からなる
憤怒を感ぜずにはいられなかった。
信一郎は、可なり激しい、
叱責するような調子で運転手に言った。
「一体何の用事があるのです?」
運転手は、ニヤ/\気味悪く笑いながら、
「宅の奥様のお手紙を持って参ったのです。何の御用事があるか私には分りません。返事を承わって来い! お
帰になるまで、お待して返事を承わって来い! と、申し付けられましたので。」
運転手は、待っていることを、言い訳するように言った。
手紙を持って来たと聴くと、
信一郎は可なり
狼狽した。妻に、
内密で、ある女性を訪問したことが
露顕している上に、その女性から急な手紙を
貰っている。そうしたことが、どんなに妻の幼い純な心を傷けるかと思うと、
信一郎は顔の色が
蒼くなるまで当惑した。彼は、妻に知られないように、手早く手紙を受け取ろうと思った。
「手紙! 手紙なら、早く出したまえ!」
信一郎は、低く可なり狼狽した調子でそう言った。
運転手が、何か言おうとする時に、夫の帰りを知った妻が、急いで玄関へ出て来た。彼女は、夫の顔を見ると、ニコ/\と
嬉しそうに笑いながら、
「お手紙なら、
此方にお預りしてありますのよ。」と、言いながら、薄桃色の
瀟洒な封筒の手紙を差し出した。
暢達な女文字が、半ば血迷っている
信一郎の眼にも美しく映った。
面罵
一
妻から、
荘田夫人の手紙を差し出されて見ると、
信一郎は激しい
羞恥と当惑とのために、顔がほてるように熱くなった。
253/390
平素は、何の隔てもない妻の顔が、
眩しいもののように、
真面から見ることが出来なかった。
が、
静子の顔は、
平素と寸分
違わぬように穏かだった。春のように穏かだった。夫の不信を
咎めているような顔色は、少しも浮んでいなかった。見知らぬ女性から、夫へ突然舞い込んで来た手紙を、疑っているような容子は、少しも見えなかった。夫の帰宅を、いそ/\と出迎えている
平素の優しい
静子だった。
信一郎は、妻の
神々しい
迄に、
慎しやかな容子を見ると、
却って心が咎められた。これほどまでに自分を信じ切っている妻を
欺いて、他の女性に、好奇心を、
懐いたことを、後悔し心の中で
懺悔した。
妻が差出した夫人の手紙が、悪魔からの
呪符か何かのように、
嫌わしく感ぜられた。もし、人が見ていなかったら、それを、封も切らないで、寸断することも出来た。が、妻が見て居る以上、そうすることは却って彼女に疑惑を起させる
所以だった。
信一郎は、おず/\と封を開いた。
手紙と共に封じ込められたらしい、高貴な香水の
匂が、
信一郎の鼻を魅するように襲った。が、もうそんなことに
依って、魅惑せらるゝ
信一郎ではなかった。
彼は敵からの手紙を見るように警戒と
憎悪とで、あわたゞしく
貪るように読んだ。
254/390
『先刻は貴君を試したのよ。妾の客間へ、妾と戯恋しに来る多くの男性と貴君が、違っているか何うかを試したのですわ。妾は戯恋することには倦き/\しましたのよ。本当の情熱がなしに、恋をしているような真似をする。擬似恋愛! 妾は、それに倦き/\しましたのよ。身体や心は、少しも動かさないで、手先丈で、恋をしているような真似をする。恋をしているような所作丈をする。恋をしているような姿勢丈を取る。妾は、妾の周囲に蒐まっている、そうした戯恋者のお相手をすることには、本当に倦き/\しましたのよ。妾は真剣な方が、欲しいのよ。男らしく真剣に振舞う方が欲しいのよ。凡ての動作を手先丈でなく心の底から、行う方が欲しいのよ。
貴君が忿然として座を立たれたとき、妾が止めるのも、肯かず、憤然として、お帰り遊ばす後姿を見たとき、この方こそ、何事をも真剣になさる方だと思いましたの! 何事をなさるにも手先や口先でなく、心をも身をも、打ち込む方だと思いましたの。妾が長い間、探ねあぐんでいた本当の男性だと思いましたの。
信一郎様!
貴方は妾の試に、立派に及第遊ばしたのよ。
今度は、妾が試される番ですわ、妾は進んで貴方に試されたいと思いますの。妾が、貴方のために、どんなことをしたか、どんなことをするか、それをお試しになるために、直ぐ此の自動車でいらしって下さい!瑠璃子』
手紙の文句を読んでいる
中に、
瑠璃子夫人の怪しきまでに、美しい記憶が、殺されそこなった蛇か何かのように、また
信一郎の頭の中に、ムク/\と動いて来た。
255/390
夫人の手紙を、読んで見ると、夫人の心持が、満更虚偽ばかりでもないように、思われた。あの美しい夫人は、彼女を囲む
阿諛【おべっか】や
追従【こびへつらい】や甘言や、戯恋に倦き/\しているのかも知れない。実際彼女は純真な男性を、心から求めているかも知れない。そう思っていると、夫人の真紅の唇や、白き透き通るような頬が、
信一郎の眼前に
髣髴した【よみがえった】。
が、次ぎの瞬間には
青木淳の紫色の死顔や、今先刻見たばかりの、
青木淳の弟の姿などが、アリアリと浮んで来た。
二
手紙を読んだ
刹那の
陶酔から、
醒めるに従って、夫人に対する
憤ろしい心持が、また
信一郎の心に
甦って来た。こうした、人の心に喰い込んで行くような誘惑で、
青木淳を
深淵へ誘ったのだ。
否青木淳ばかりではない、
青木淳の弟も、あの海軍
大尉も、否彼女の周囲に
蒐まる
凡ての男性を、人生の
真面目な行路から踏み外させているのだ。彼女を早くも嫌って恐れて、逃れて来た自分にさえ、
尚執念深く、その
蜘蛛の糸を投げようとしている。恐ろしい
妖婦だ! 男性の血を吸う
吸血鬼だ。そう思って来ると、
信一郎の心に、半面血に
塗れながら、
『時計を返して
呉れ。』
と絶叫した青年の面影が、又
歴々と浮かんで来た。そうだ! あの時計は、不得要領に
捲上げらるべき性質の時計ではなかったのだ! 青年の恨みを、十分に
籠めて
叩き返さなければならぬ時計だったのだ!
殊に、青年の手記の
中の彼女が、
瑠璃子夫人であることが、ハッキリと分ってしまった以上、自分にその責任が、
儼として存在しているのだ。
256/390
恐ろしいものだからと言って、
面を背けて逃げてはならないのだ! 青年に代って、彼が綿々の恨みを、代言してやる必要があるのだ! 青年に代って、彼女の
僅かしか残っていぬかも知れぬ良心を恥かしめてやる必要があるのだ! そうだ! 一身の安全ばかりを計って逃げてばかりいる時ではないのだ! そうだ! 彼女がもう一度の面会を望むのこそ、
勿怪の幸である。その機会を利用して、青年の魂を慰めるために、青年の弟を、彼女の危険から救うために、否
凡ての男性を彼女の危険から救うために、彼女の高慢な心を、取りひしいでやる必要があるのだ。
信一郎の心が、こうした義憤【怒り】的な興奮で、
充された時だった。妻の
静子は、――神の
如く何事をも疑わない
静子は、
信一郎を促すように言った。
「急な御用でしたら、
直ぐいらしっては、
如何でございます。」
妻のそうした純な、少しの疑惑をも、
挟まない言葉に、接するに付けても、
信一郎は夫人に叩き返したいものが、もう一つ殖えたことに気が付いた。それは、夫人から受けた
此の誘惑の手紙である。妻に対する自分の愛を、陰ながら、妻に誓うため、夫人の
面に、この誘惑の手紙を、投げ返してやらねばならない。
信一郎の心は、今最後の決心に到達した。彼は、その白い
面を、薄赤く興奮させながら、妻に言うともなく、運転手に命ずるともなく叫んだ。
「じゃ直ぐ引返すことにしよう。早くやってお呉れ!」
彼は、自分自身興奮のために、身体が軽く
顫えるのを感じた。
「
畏まりました。七分もかゝりません。」
そう言いながら、運転手と助手とは、軽快に飛び乗った。
「じゃ、
静子、行って来るからね。ホンの
一寸だ! 直ぐ帰って来るからね。」
信一郎は、小声で言い訳のように言いながら、妻の顔を、なるべく見ないように、車中の人となった。
が、ガソリンが爆発を始めて、
将に動き出そうとする時だった。
257/390
信一郎は、
周章て窓から、首を出した。
「おい!
静子! おれの本箱の下の引き出しの、確か右だったと思うが、ノートが入ってる。それを持って来ておくれ!」
「はい。」と言って気軽に、立ち上った妻は、二階から大急ぎで、そのノートを持って降りて来た。
『これが、武器だ!』
信一郎は、妻の手からそれを受けとりながら、心の中でそう叫んだ。
爪黒の
鹿の血と、
疑着の相ある女の生血とを塗った横笛が、
入鹿を
亡ぼす手段の一つである【
怨霊・呪術によって
暴虐の入鹿(藤原入鹿)を討つために用いられる、いわくつきの横笛】ように、
瑠璃子夫人の急所を突くものは、
青木淳の残した
此のノートの外にはないと、
信一郎は思った。
三
五番町までは、一瞬の間だった。
こうした行動に出たことが、いゝか悪いか迷う暇さえなかった。
信一郎の頭の中には、
瑠璃子夫人の顔や、妻の
静子の顔や、
非業に死んだその男の顔や、今日
客間で見たいろ/\な人々の顔が、
嵐のように渦巻いている
丈だった。が、その渦巻の中で彼は自ら強く決心した。『彼女の誘惑を粉砕せよ!』と。
もう再びは
潜るまいと決心した
花崗岩の石門に、自動車は速力を
僅に緩めながら進み入った。もう再びは、足を踏むまいと思った車寄せの石段を、彼は再び昇った。が、先刻は夫人に対する
賛美と
憧れの心で、胸を躍らしながら、が、今は夫人に対する反感と
憤怒とで、心を狂わせながら。
取次ぎに出たものは、あの
可愛い少年の代りに、十七ばかりの少女だった。
「奥様がお待ちかねでございます。さあ、どうかお上り下さいませ。」
信一郎は、それに
会釈する
丈の心の余裕もなかった。彼は黙々として、少女の後に従った。
少女は先刻の
客間の方へ導かないで、玄関の
広間から、
直ぐ二階へ導く階段を上って行った。
「あの、お部屋の方にお通し申すように
仰しゃっていましたから。」
258/390
信一郎が
一寸躊躇するのを見ると、少女は振り返ってそう言った。
階段を昇り切った取っ付きの部屋が、夫人の居間だった。少女は軽く
叩したが、内から応ずる
気勢がしなかった。
「あら! いらっしゃらないのかしら。それではどうか、お入りになって、お待ち下さいませ。
屹度、お化粧部屋の方にいらっしゃるのですから。」
そう言って、少女は
扉を開けた。
信一郎は、おそる/\その華麗な室内に足を踏み入れた。部屋の中には、夫人の
繊細な
洗練された趣味が、隅から隅まで、行き渡っていた。敷詰めてある薄桃色の
絨毯にも、水色の窓
掩いにも、ピアノの上に載せてある一輪挿の花瓶にも、
桃花心木の小さい書架【本棚】に、並べてある美しい
装幀の
仏蘭西の小説にも、雪のように白い絹で張りつめられた壁にかゝっている
クールベエらしい風景画にも
炉棚の上の少女の
青銅像にも、夫人の高雅な趣味が光っていた。
凡ての装飾が、金で光っている
丈ではなく、その洗練された趣味で光っているのだった。
信一郎は、部屋の装飾に、現われている夫人の教養と趣味とに、接すると、
昂めよう/\としている反感が、
何時の間にか、その鋭さを減じて行くような危険を、感ぜずにはいられなかった。
が、こうした美しい部屋も、彼女の毒の花園なのだ。彼女が、異性を惑わす魅力の一つなのだ。
信一郎は、そう言う風に考え直しながら、青色の
羽蒲団の敷いてある
籐椅子に、腰をおろしていた。窓からは、
広大な庭園が、七月の太陽に輝いているのが見えた。
夫人は、なか/\姿を見せなかった。小間使が氷の入った
果実汁を持って来た後も、なか/\姿を見せなかった。
彼は、所在なさ【手持ち無沙汰】に、室内の装飾をあれからこれへと、見直していた。その
裡に、ふと三尺とは離れていない
卓の上に、眼が付いた。
259/390
其処には、先刻
信一郎が受け取ったのと同じ色のレタアペイパアと、金飾の華やかな婦人持の万年筆とが、置かれていた。先刻の手紙は、恐らくこの
桃花心木の小さい卓で書いたのに違いない。そう思って見ている中に、ふと一枚のレタアペイパアに、英語か仏蘭西語かが書かれているのに気が付いた。彼の好奇心は、動いた。彼は、少し上体を、その方に延ばしながら、それを読んだ。
(Shinichiro)
彼は、自分の名前が書かれているのに驚いた。が、その次ぎの二字を見たときに、彼の
駭きは十倍した。
(Shinichiro, my love!)
『
信一郎、わが
恋人よ!』
而も、その同じ句がそのレタアペイパアの上に、鮮かな筆触で幾つも/\走り書きされているのだった。
四
『
信一郎、わが
恋人よ!』
信一郎の頭は、この短い文句でスッカリ掻き
擾されてしまった。彼は十七八の少年か何かのように、我にも
非ず、頬が熱くほてるのを感じた。夫人に対して、張り詰めていた心持が、ともすれば揺ぎ始めようとする。
彼は、心の中で幾度も叫んだ。夫人の技巧の一つだ。誘惑の技巧の一つだ。自分の眼に入るように、わざとこんな文句を、書き散して置いたのだ。見え透いた技巧なのだ! が、そう言う考えの後から、又別な考えが浮んで来た。あの
利口な
聡明な夫人が、こんな露骨な趣味の悪い技巧を
弄する訳はない! やっぱり、夫人の本心から出た自然の書き散しに違いない。
信一郎の心の中の男性に共通な
自惚が、ムク/\と頭を
擡げようとする。あの先刻受け取った手紙も、こうして見ると、夫人の本心を語っているのかも知れない。夫人を
妖婦のように思うのも、みんな自分の
邪推【ひがんで悪く想像】かも知れない。彼女は、男性との恋愛
ごっこに飽き/\しているのだ。彼女の周囲に、
蒐まる
胡蝶のような戯恋者に、飽き/\しているのだ。
260/390
本当に、心をも身をも捨てゝかゝる、真剣な異性の愛に飢えているのかも知れない。
世馴れた
色男風の男性に、
慊たらない【満足しない】彼女は、自分のような
初心な
生真面目な男性を求めていたのかも知れない。
夫人に対する
信一郎の敵意がもう
半崩れかけている時だった。
「御免下さいまし。」
銀鈴に触れるような
爽かな声と共に、夫人は静かに扉をあけて入って来た。
湯上りらしく、その顔は、白絹か何かのように
艶々しく輝いていた。
縮緬の
桔梗の模様の
浴衣が、そのスッキリとした身体の
輪郭を、
艶美に描き出していた。
わずか四五尺の間隔で、じっとその美しい
眸を投げられると、
信一郎の心は、催眠術にでもかゝったような、陶酔を感ずるのを、
何うともすることが出来なかった。
「まあ! 本当によくいらっしゃいましたこと。
妾、もうあれ切りかと思いましたの。もう、あれ切り来て下さらないのかと思っていましたよ。」
信一郎が、彼女の入って来たのを見て、立ち上ろうとするのを、制しながら、
信一郎と向きあって小さい卓を隔てながら、腰を下した。
信一郎は、ともすれば
後退りしそうな自分の決心に、
頻りに拍車を与えながら、それでも最初の目的
通、夫人と戦って見ようと決心した。
「先刻は大変失礼しましたこと。あの方達を帰してしまった後で、ゆっくり
貴君とお話がしたかったのよ。差し上げました御手紙御覧下すって?」
「見ました。」
信一郎は、自分の決心を、動かすまいと、しっかりと言い放った。
「
何うお考え遊ばして?」
夫人は、
追窮するように、美しく笑いながら
訊いた。
信一郎は、可なりハッキリした口調で言った。
「
貴女の本当のお心持が、分らないものですから、
何うお答えしてよいか当惑する
丈です。」
「あれでお分りにならないの。あれで、十分分って下すってもいゝと思いますの。
妾が、
貴君のことを
何う考えていますか。」
261/390
夫人の顔に可なり、真剣な色が動いた。
信一郎も、ある
丈の力を
以て言った。
「奥さん!
何うか記憶して置いて下さい! 僕には妻がありますから、家庭がありますから、
貴女の危険なお
戯れのお相手は出来ませんから。」
信一郎は、妻の
静子の面影や、
青木淳の死相を心の味方として、この強敵に向ってハッキリと断言した。
五
その
刹那、夫人の顔が、
遉に鋭く緊張した。
「あら、
貴君までが、そんなことを考えていらっしゃるの。
妾が
貴君の家庭を
擾すような女だと思っていらっしゃるの。
貴君にも、やっぱり
妾の真意が分って下さらないのですわね。
妾が、何を求めているかが、やっぱり分って下さらないのですわね。
妾は、
妾の周囲の戯恋者には飽き/\したと申しているではありませんか。
妾は戯恋の相手ではなく、本当のお友達が欲しいのです。本当の男性らしい男性のお友達が欲しいのです。
妾が、この方こそと思ってお選みした
貴君からそんな誤解を受けるなんて、
妾には忍びがたい
恥辱ですわ。」
そう言っている夫人の顔には、もうあの美しい微笑は浮んでいなかった。少しく、
忿怒を帯びた顔は、振い付きたいような美しさで、輝いていた。
美しい夫人の顔に、
忿怒の色が浮ぶのを見ると、
信一郎は心の中で、可なりタジ/\となった。が、彼は自分のため、
青木淳のため、また夫人その人のためにも、夫人の
妖婦的な魂と、戦わねばならぬと決心した。彼は、夫人の美しい顔から、出来るだけ
面を背けながら言った。
「いや!
貴女のお心が、分らないのではありません。僕を、真のお友達として、多くの男性から選んで下さる。それは僕として、光栄です。が、奥さん! 僕は
貴女から選まれると言うことが可なり危険なことであるような気がするのです。僕は、
安穏な家庭の幸福で、満足している平凡な人間です。
262/390
何うか僕を、このままに残して置いて下さい!」
信一郎の語気は、可なり強かった。
「まあ! 何と言うことを
仰しゃるのです。
妾を、爆弾か何かのように、触ることさえ、お嫌いだと言うのですね。」
夫人は、半ば冗談のように、言おうとしたが、
信一郎の心の中の敵意を、アリ/\と感じたと見え、先刻までの夫人とは、丸切違ったような鋭さが、その美しさの裏に、
潜み初めていた。
「いや! 奥さん、こんなことを申し上げては、失礼かも知れませんが、僕は
貴女に選まれて飛んだ目にあったある男性のことを知っているのです。その男も、
真面目な
初心な男でしたから、僕が
貴女に選まれたのと、同じような意味で、
貴女に選まれたのではないかと思うのです。
若し、同じような意味で選まれたとすると、その男が飛んだ目に
逢ったように、僕も
何時かは、飛んだ目に逢いそうです。はゝゝゝ。」
信一郎は、懸命な勇気を
以て、言い終ると調子外れの笑い方をした。彼は
烈しい興奮のために、妙に上ずッてしまっていたのである。
夫人の顔色が、
一寸変った。が、少しも取り
擾す容子はなかった。彼女は、
信一郎の顔を、じっと見詰めていたが、
憫笑する【あわれみさげすむ】ような笑いを、頬の辺に浮べると、
一寸腰を浮かして、傍の卓の上の呼鈴を押しながら言った。
「
貴君と
妾とは、やっぱり縁なき
衆生だったのですわね。やっぱりあれっ切りにして置けばよかったのですわね。
妾の思い違いよ。
貴君を、スッカリ見損っていたのですわね。
貴君の
躊躇や、
臆病を、
妾反対に解釈していたのですわ。
妾男性の中で臆病な方が、一等嫌いなのですわ。差し出された女の唇に、
接吻を与えるほどの勇気さえないような男性が、一等嫌いなのでございますよ。おほゝゝゝゝ。
妾自身、御覧の通のお
転婆でございますから、やっぱり強い男性の方が、一等好きなのでございますよ。」
263/390
信一郎の攻撃に対する夫人の反撃は、烈しかった。
信一郎は夫人の真向からの侮辱に、目が
眩んだ。彼は屈辱と
忿怒とのために、胸がくらくらするように煮えた。
信一郎が
口籠りながら何か言おうとしたときに、呼鈴に応じて先刻の小間使が顔を出した。夫人は冷静な口調で、ハッキリと言った。
「お客様がお帰りになるそうだから、自動車の支度をするように。」
六
西洋では、
嫌な来客を追い帰すとき、又 来客と
喧嘩したとき、『
扉を指さし示す』ことが、習慣である。直ぐ出て行って
呉れと言う意味である。客に対する絶大の侮辱であり、挑戦である。
が、来客の前で、勝手に帰り支度を、整えてやることも、『扉を指さし示す』ことと同じ程度の侮辱に違いない。
夫人は、自分の好意を、相手が跳ね返したと知ると、それを十倍もの
烈しさで、跳ね返し得る女であった。
信一郎は、平手で真向から顔を、ピシャリと、
叩かれたような侮辱を感じた。もし、相手が女性でなかったら、立ち上りざま殴り付けてでもやりたいような
激怒を感じた。それと同時に、突き放されたような
淋しさが、激怒の陰に潜んでいることをも、感ぜずにはいられなかった。
信一郎の顔が、激怒のために、真赤に興奮しているのにも
拘わらず、夫人はその白い
面が、心持
蒼んでいる
丈で、冷然として彫像か何かのように動かなかった。
信一郎も、相手から受けた、余りに思いがけない侮辱の
為に、
暫らくは、口さえ
利けなかった。
夫人も、黙々として一語も
洩らさなかった。その中に、バタ/\と廊下に軽い足音がしたかと思うと、先刻の女中が、顔を出した。
「あの、お支度が出来ましてございます。」
「そう。」と、夫人は軽く
会釈して、女中を去らせると、静かに
信一郎の方を振向きながら、彼女の最後の
通牒を送った。
「それでは、どうかお帰り下さいませ。
264/390
妾がお呼び立ていたした罪は、幾重にもお
詫いたしますわ。でも、お互に理解しない者同士が、
何時まで向い会っていても、全く無意味だとも思いますわ。
何うか安穏な御家庭で何時までも平和にお暮し遊ばせ!」
夫人は、
一寸皮肉な微笑を浮べると、静に立って
信一郎に、扉の方を指さし示した。
信一郎の心は、激しい
恥辱のために、裂けんばかりに、張り詰めていた。このまゝ、帰ってしまえば、
徹頭徹尾全敗である。どんなに、相手が美しい夫人であるとは言え、男性たるものが、こうも手軽に、人形か何かのように
翻弄せられることは、
何うにも
堪らないことだと思った。今こそ全力を尽して彼女と、戦うべき日であると思った。激怒のために、波立つ胸を、彼はじっと抑え付けながら言った。
「奥さん! 折角ですが、僕にはまだ帰られない用事があります。」
信一郎の言葉は、可なり
顫えを帯びていた。
「おや! 御用事。それじゃ
直ぐ承わろうじゃありませんか。
妾、またこんな部屋には、一刻もお
止まりになるお心は なくなったのだろう と思っていました。」
夫人は、
凄いほどに、落着いていた。
信一郎は、
蒼白になりながら、懸命に冷静な態度を失うまいとした。
「奥さん! 帰るときが来れば、お指図を待たなくっても帰ります。が、
只今伺ったのは、
貴女のお手紙の
為ばかりじゃないのです。僕がどんなに軽薄な人間でも、一度席を
蹴って帰った以上、
貴女のお召状
丈で、ノメ/\とやっては来ません。」
「おや! それでは、
妾はその点でも飛んだ思違いをしていましたのね。」
夫人は、針のような皮肉を含みながら、冷やかに笑った。
信一郎はいらだった。
「
貴女に申し上ぐべきこと、当然お願いすべき用事があればこそ参ったのです。それが済むまでは、
貴女が幾ら帰れと
仰しゃったって、帰れません。
265/390
貴女も一度僕と会った以上、自分の用事
丈が、済んだと言って、そう手軽に僕を追い返す権利はありません。」
「大変
御尤もな
仰せです。それではその用事とかを承わろうじゃありませんか。」
夫人の皮肉な態度は突き刺すようなトゲ/\しさを帯び初めた。
七
夫人の皮肉なトゲに、突き刺されながらも、
信一郎は、やっと自分自身を支えることが出来た。
「用事と言って、
外ではありませんが、いつか
貴女にお預けして置いたあの
白金の時計を、返していたゞきたいと思うのです。死んだ
青木君から
遺託を受けたあの時計をです。」
信一郎は、一生懸命だった。彼は、身体が激高のために、わなゝこうとするのをやっと、抑えながら
喋べった。が、その声は変に
咽喉にからんでしまった。
夫人の冷たさは、
愈々加わった。その美しい
面は、
象牙で
彫んだ仮面か何かのように、冷たく光っていた。『何を!』と言ったような
利かぬ気の表情が、その小さい真赤な唇のあたりに動いていた。
「あら、あれは
妾にお預けして下さったのじゃないのですか。
一旦お預けして下さった以上、男らしくもないじゃありませんか。また返せなどと
仰しゃるのは。」
信一郎を
揶揄っているように、冷かしているように、夫人の語気は、ます/\
辛辣になって行った。
「いや、お預けしたことは、お預けしました。が、それは返すべき相手が分らなかったからです。また、
何う言う心持で返すのかが、分らなかったからです。今こそ、返すべき女性がハッキリと分ったのです。また、
何う言う態度で、あの時計を返すべきかも、ハッキリと分ったのです。僕は、あの時計を
貴女から返していたゞいて、その本当の持主に、一番適当な態度で、返さねばならぬ責任を
青木君に対して、感じているのです。どうか
直ぐお返しを願いたいと思います。」
夫人の顔は、
遉に少しく動揺した。
266/390
が、
信一郎が予想していたように、
狼狽の容子は露ほども見せなかった。
「そんなに、面倒臭い時計なのですか、それじゃ、お預りするのではなかったわ。それじゃ
只今直ぐお返しいたしますわ。」
夫人は、手軽に、借りていたマッチをでも返すように、手近の
呼鈴を押した。
二人は、黙々として、
暫らく相対している
裡に、以前の小間使が、扉を静に開けた。
「あのね。応接室の、確か
炉棚の上の手文庫の中だったと思うのだがね。壊れた時計がある
筈だから持って来て下さいね。
若し手文庫の中になかったら、あの辺を探して御覧! 確かあの近所に放り散かして置いた筈だから。」
信一郎が、あれほどまでに、心を労していた時計を、夫人は壊れた玩具か何かのように、放りぱなしにしていたのだった。
青木淳が臨終にあれほどの
恨を
籠めた筈の時計は、夫人に
依って、意味のない一個の壊れ時計として、炉棚の上に、
信一郎から預かった時以来忘れられていたのである。
夫人から、そんなにまで手軽く扱われている品物に就いて、返すとか返さないとか、躍起になっていることが、
信一郎には
一寸気恥しいことのように思われた。
が、夫人のあゝした言葉や態度は、心にもない豪語であり、
擬勢である、口先でこそあんなことを言いながらも、彼女にも人間らしい心が、少しでも残っている以上、心の中では可なり良心の
苛責を受けているのに違ない。
信一郎は、やっとそう思い返した。
小間使は、探すのに手間が取れたと見え、暫らくしてから帰って来た。そのふっくらとした小さい手の
裡には、
信一郎には忘れられない時計が、薄気味のわるい光を放っていた。
夫人は小間使から、無造作にそれを受取ると、
信一郎の卓の上に軽く置きながら、
「さあ! どうぞ。よく
検ためてお受取り下さいませ! お預りしたときと、寸分違っていない筈ですから。」
267/390
夫人は、毒を
喰わば皿までと言ったように、飽くまでも皮肉であり冷淡であった。
八
信一郎は、差し出されたその時計を見たときに、その時計の胴にうすく残っている
血痕を見たときに、
弄ばれて
非業の死方をした青年に対する義憤の情が、
旺然として【勢いさかんに】胸に
湧いた。それと同時に、青年を
弄んで、間接に彼を殺しながら
而も平然として彼の死を冷視している――神聖な
遺品の時計をさえ、
蔑み切っている夫人に対して、燃ゆるような憎しみを、感ぜずにはいられなかった。
信一郎は、かすかに
顫える手で、その時計を拾い上げながら、夫人の
面を真向から見詰めた。
「いや、確にお受取りしました。お預けした品物に相違ありません。」
彼の言葉も、いつの間にか、敵意のある切口上に変っていた。
「ところが、奥さん!」
信一郎は、満身の勇気を振いながら言った。
「
一旦お返し下さった
此時計を――改めて、そうです、
青木君の意志として――私は、改めて
貴女に受取っていたゞきたいのです。」
そう言って、
信一郎は、夫人の顔をじっと見た。どんなに厚顔な夫人でも、少しは
狼狽するだろうと予期しながら。が、夫人の顔は、やゝ
殺気を帯びているものゝ、その整った顔の筋肉一つさえ動かさなかった。
「何だか手数のかゝるお話でございますのね。子供のお客様
ごっこじゃありますまいし、お返ししたものを、また返していただくなんて、もう一度お預かりした
丈で、
懲々いたしましたわ。」
夫人は
噛んで捨てるように言った。
信一郎は、夫人の白々しい態度に、心の底まで、
憎みと
憤怒とで、煮え立っていた。
「いや、
此度はお預けするのではないのです。いや、最初から
此の時計は
貴女にお預けすべきでなくお返ししなければならぬ時計だったのです。時計の元の持主として、
貴女に受取っていたゞくのです。
268/390
貴女は、
此の品物を当然受取るべきお心覚えがあるでしょう。ないとは、まさか
仰しゃれないでしょう。」
信一郎も、女性に対する
凡ての遠慮を捨てゝいた。二人は男女の性別を超えて、格闘者として、相対していた。
信一郎に、そう言い切られると、夫人は
暫らく黙っていた。白い
瓢の種のような
綺麗な歯で、下唇を二三度噛んだがやがて気を換えたように、
「それでは、
貴君は
此時計の元の持主を、
妾だと仰しゃるのですか。」
「そうです。それを確信してもよい理由があるのです。」
信一郎は
凜としてそう言い放った。
「おやそう!」夫人は事もなげに
応けながら、「
貴君が、そうお考えになりたければ、そうお考えになっても、別に
差支はございませんよ。それでは、この時計もお受取りして置こうじゃありませんか。どうせ一度は、お預かりした品物ですもの。」
夫人の態度は、
愈逆になり、愈々毒を含んでいた。
「それで、御用事と仰しゃるのはこれ
丈!」
夫人は
信一郎と一刻でも長く同席することが不快で
堪らないように
急き立てるように附け加えた。
信一郎は、夫人の自分に対する
烈しい
憎悪に傷きながら、しかも勇敢に彼の陣地を支えた。
「いや、大変お手間を取らして相済みません。が、もう一言、そうです、
青木君の
言伝があるのです。時計の元の持主にこう伝えて
呉れと頼まれたのです。」
信一郎は、そう言って言葉を切った。
夫人は
遉に、緊張した。やさしく
烟っている
眉を、
一寸顰めながら、
信一郎が何を言い出すかを待っているようだった。
彼女の云分
一
遺言と言っても、
信一郎は
青木淳の口ずから受けているのではない。が、彼は
青木淳の死前の
恨の
籠ったノートを受け継いでいる。
『彼女の
僅かに残っている良心を恥かしめてやる』べき、以心伝心の遺託を、受けているのだった。
269/390
「いや、遺言と言っても、外ではありません。この時計を返すときに元の持主にこう言って
呉れと頼まれたのです。
青木君が
瀕死の重傷に苦しみながら、途切れ/\に言ったことですから、ハッキリとは分りませんが、何でもこう言う意味だったと思うのです。純真な男性の感情を
弄ぶことがどんなに危険であるかを伝えて呉れ。
弄ぶ女に取っては、それは一時の
戯れであるかも知れぬが、
弄ばれる男に取っては、それが死であると。奥さん!
貴女は、こう言う話を御存じですか。池の中に多くの
蛙が浮んでいると、子供達が来て石を投げ付ける、その時に蛙が何て言ったか御存じですか。蛙はこう言ったのです。
貴君方に取って遊戯であることが、我々に取っては死である、と。
青木君の
死際の云分も、つまりそれなのです。
貴女は、
青木君の死を単なる
奇禍【思いがけない災難】だと思ってはいけません。形は
奇禍ですが、心持に
於いては立派な自殺です。たゞ自動車の偶然の衝突があの人の死を、二三日早めたのに過ぎないのです。
貴女は
青木君の死を
奇禍だと考えることに
依って、
貴女の良心を
欺いてはなりません。正しく自殺です。
而も池の中の蛙が、子供が戯れに投げた石に当って死んだように、
貴女が戯れに与えた
白金の時計に
依って死んだのです。蛙が
若し人間としての働きがあったならば、その石を子供に投げ返すように、僕は
青木君に代って、
此の時計を
貴女に投げ返すのです。そうです、
貴女の良心に向って投げ返すのです。
貴女の心に僅かにでも、良心が残っているのなら、
貴女はそれで
此の時計を受け止めて下さい。そうしてその受け止めた痛みに
依って、
貴女の心を
浄めていたゞきたいと思うのです。そうして、男性に対する
貴女の危険な戯れを、今日限り
廃していたゞきたいと思うのです。それが
青木君の死に対する
貴女のせめてもの
償いです。僕が、先刻
貴女のお戯れの相手をするのは危険だと言ったのはこう言う意味です。
270/390
青木君の場合はまだ独身ですから、
貴女の戯れの犠牲になるものは一人で済むのですが、僕のような既婚者の場合は被害者が複数ですからね。」
信一郎の興奮は、彼を可なりな雄弁家にしてしまった。夫人はと見ると、
遉に彼の言葉が一々
肺腑【心の奥底】を
衝いていると見えて、うなだれ気味に、黙々と聴いていた。
信一郎は、自分の心が、少しでも夫人の心を悔い改めしめているかと思うと、内心ある感激を感ぜずにはいられなかった。そうだ!
此の美しき女性をたゞ恥かしめる
丈が、能ではない。自分の言葉に
依って、夫人の心を、少しでも
浄くし改めてやりたいと思った。
「いや! 奥さん。僕は何も
貴女に
恩怨があるのではありません。恩怨がないばかりでなく、ある点では
貴女を
敬慕【尊敬して人柄を慕う】しているものです。
貴女のその
秀れた美しさと、
貴女の教養や趣味に対して、心から敬慕しているものです。が、僕は
貴女がそうした天分や教養を邪道に使っているのを見ると、本当に心が暗くなるのです。僕は
青木君の
為にばかりでなく、
貴女自身のために、僕の言ったことをよく
玩味していたゞきたいと思うのです。」
こう
信一郎が、述べ
来った時、今まで傾聴しているような態度をしていた夫人は、つと頭を上げた。
「あの、お言葉中で恐れ入りますが、御忠告なら、御免を
蒙りたいと思います。御用事
丈を承わる
筈であったのでございますから。」
鋼鉄のような
凜とした冷たさが、その澄んだ声の内に響いていた。
二
『御忠告ならば、御免を蒙る。』と、夫人がきっぱりと言い放つのを聴くと、
信一郎は夫人に対して、最後の望みを絶った。
青木淳は、『
僅に残っている良心』と、書いている。が、僅に残っている良心どころか良心らしいものは、
片さえ残っていない。女らしい、つゝましい心の代りに、そこに翼を
拡げているものは、恐ろしい
吸血鬼である。
271/390
純真な男性の血を好んで
嗜なむ怪物である。夫人の良心に訴えて、少しでも彼女を、いゝ方に改めさせてやろうと思ったのは、悪魔に
基督の教を説くようなものであると思った。
信一郎は
外面如菩薩と言う古い言葉を、今更らしく感心しながら、
暫らくは夫人の顔を、じっと見詰めていたが、
「いや、これは飛んだ失礼をしました。
青木君の遺言
丈を伝えれば、僕の責任は尽きていたのでした。」
彼は、そう言って
潔く
此部屋から出ようとした。が、その時に、彼は
青木淳の弟の姿を思い浮べた。そうだ! あの青年を、夫人の危険から救ってやることは、自分の責任だと思った。
「だが、奥さん! 僕は僕の責任として、
貴女にもう一言言わなければならぬことがあるのです。これは
貴女に対するおせっかいな忠告じゃないのです。
青木君に対する僕の責任の一部として、申し上げるのです。
畢竟【つまるところ】は
青木君の遺言の延長として申上げるのです。それは、外でもありません。
貴女が
如何なる男性の感情を、どんなに
弄ぼうが、それは
貴女の御勝手です。いや御勝手と言うことにして置きましょう。だが、
青木君の弟の感情を、
弄ぶこと
丈は、僕が
青木君に代って、断然お断りして置きます。まさか、
貴女も少しでも、人情がお有りでしたら、兄を
深淵へ突き
陥した後で、その肉親の弟をも、同じ
処へ突き陥すような残酷なことはなさるまいとは思いますけれども、念のためにお願して置くのです。いやどうもお邪魔しました。」
夫人の顔が、
遉に
蒼白に転ずるのを
尻目にかけながら、
信一郎は、素早く部屋を出ようとした。が、それを見ると、夫人は
屹となって呼び止めた。
「
渥美さん! お待ちなさい!」
その
凜とした声には、女王のような
威厳が備わっていた。
「
貴君は、自分の
仰しゃることさえ仰しゃってしまえば、それでお帰りになってもいゝとお考えになるのですか。
272/390
貴君が、
妾に御用事がある
中は、
貴君に帰る権利が、
妾になかったように、
妾が
貴君に申上げることが残っている以上
貴君はお帰りになる権利はありません。
妾は一言
丈貴君に申上げることが残っています。」
美しい
眉は
吊り上り、黒い
眸は、血走っていた。
信一郎を、
屹と【険しく】見詰めて立っている姿は、『怒れる天女』と言ったような、美しさと
神々しさとがあった。
「
貴君は、今
青木さんの
遺言とやらを、長々しく仰しゃいましたが、それを
妾が受けると思っていらっしゃるのですか。時計こそ、お受けしましたが、そんな御遺言なんか、一言半句だって、お受けする覚えはありません。そんなお言伝を、
青木さんから承わるような覚えは、さら/\ありません。今承わったお言葉全部を、そのまゝ御返上します。」
夫人の声にも、憎みと怒りとが、燃えていた。が、
信一郎はたじろがなかった。
「死人に口がないと思って、そんなことを仰しゃっては困ります。
貴女を、今日訪問した客に
村上と言う海軍
大尉があった
筈です。まさか、ないとは仰しゃいますまいね。」
「よく御存じですね。」
夫人は、平然として答えた。
「それなら、
青木君の遺言を受ける責任と義務とがあります。
貴女に、もし少しでも良心が残っていらっしゃるのなら、今
貴女にお目にかけるものを、平然と読めるかどうか試して御覧なさい!」
そう言いながら、
信一郎はポケットに曲げて入れていたノートを夫人の
眼前に突き付けた。
三
信一郎が、眼の前に突き付けたノートを、夫人は事もなげに受取った。ノートの重さにも
堪えないような
華奢な手で、それを無造作に受け取った。
鋼鉄の
如き心と言うのは、恐らく今の場合の夫人の心を言うのだろう。鬼が出るか蛇が出るか分らないそのノートを、受け取りながら、一糸
紊れたところも、
怯んだところも見せなかった。
273/390
「おや、
青木さんのノートでございますのね。」
夫人は、平然と言いながら、最初の
頁から繰り初めた。繰っているその白い手は、落着きかえっている。
が、
信一郎は思った。今に見ろ、どんなに白々しい夫人でも、血で書いた
青木淳の
忿恨【腹を立てて恨む】の文字に接すると、
屹度良心の
苛責に打たれて、女らしい悲鳴を挙げる。彼女の
孔雀の
如き虚飾の
驕りを
擾されて、女らしい悔恨に打たれるに違いない。そう思いながら、頁を繰る夫人の
手許と、やゝ
蒼んでいる美しい
面から、一瞬も眼も放たず、じっと見詰めていた。
その
裡に、夫人はハタと、
青木淳が書き遺した文字を見付けたらしい。
遉に美しい
眸は、卓の上に開かれたノートの頁の上に、
釘付にされたように、止ってしまった。
美しい
面が、最初薄赤く興奮して行った。が、それがだん/\
蒼白になり、唇の辺りが軽く
痙攣するように動いていた。
夫人が、深い感動を受けたことは、明かだった。
信一郎は、今にも夫人が、ノートの上に
瓦破と泣き伏すことを予期していた。泣き伏しながら、
非業に死んだ青年の許しを
乞うことを想像した。彼女の美しい目から、真珠のような涙が、ハラ/\と
迸しることを待っていた。
悔恨と
懺悔との美しい涙が。
が、
信一郎の予期は途方もなく裏切られてしまった。一時動揺したらしい夫人の表情は、
直ぐ回復した。涙などは、一滴だって彼女の長い
睫をさえ
湿さなかった。
彼女は、一言も言わずに、ノートを
信一郎の方へ押しやった。
信一郎は、夫人の
必死的な態度に圧せられて、
此の上何か言う勇気をさえ
挫かれた。
二人は、二三分の間、黙々として相対していた。
信一郎は、その険しい重くるしい沈黙に堪えかねた。
「
如何です。
此のノートを読んで、
貴女は何ともお考えにならないのですか。」
信一郎の声の方が、
却ってあやしい
顫えをさえ帯びていた。
274/390
夫人は、黙して答えなかった。
信一郎は、畳みかけて
訊いた。
「
貴女は、
青木君が血を
以て書いた、
此のノートを読んで、何ともお考えにならないのですか。
青木君の言い草じゃないが、
貴女の少しでも残っている良心は、
此のノートを読んで、
顫い
戦かないのですか。
貴女の
戯れの作った恐ろしい結果に
戦慄しないのですか。」
信一郎は、可なり興奮して突きかゝった。
が、夫人は冷然として、氷の如く冷かに黙っていた。
「奥さん! 黙っていらしっては分りません。
貴女は!
貴女は
此ノートを読んで何ともお考えにならないのですか。」
信一郎は、いらだって叫んだ。
「考えないことはありませんわ。」
彼女の沈黙が冷かな如く言葉そのものも冷かであった。
「お考えになるのなら、そのお考えを承わろうじゃありませんか。」
信一郎は
益々いらだった。
「でも、死んだ方に悪いのですもの。」
「死んだ方に悪い!
貴女はまだ死者を
蔑もうとなさるのですか。死者を
誣いようとなさるのですか。」
信一郎は火の如く激高した。
その激高に、水を浴びせるように夫人は言った。
「でも、
妾、
此ノートを読んで考えましたことは、
青木さんも普通の男性と同じように、
自惚れが強くて
我ままであると言うこと
丈ですもの。」
四
夫人の言葉は、
信一郎を
唖然たらしめた。彼は呆気に取られて、夫人の美しい冷かな顔を見詰めていた。どんな
妖婦でも、昔の
毒婦伝に出て来るような恐ろしい女でも、自分を恨んで死んだ男の
遺書を、こうまで冷酷に評し去る勇気はないだろう。自分を恨んでいる、血に
滲んだ言葉を
自惚れと
我ままだと言って評し去る女はないだろう。
が、一時の驚きが去ると共に、
信一郎の心に残ったものは、夫人に対する激しい
憎悪だった。女ではない。人間ではない。女らしさと、人間らしさとを失った美しい怪物である。
275/390
その人を少しでも人間らしく考えた自分が、間違っていたのだ。彼は心の中の憎悪を吐き捨てるように言った。
「いやもう、なにも言いたくありません。
貴女は、
貴女のお考えで、男性を
弄ぶことをおつゞけなさい! その中に、純真な男性の怒が、
貴女を
粉微塵に砕く日が来るでしょう。」
信一郎は、床を踏み鳴らさんばかりに、激高しながら、叫んだ。
が、
信一郎が激すれば、激するほど、夫人は冷静になって行った。彼女は、冷たい冷笑をさえ頬の辺りに、浮べながら、落着き返って言った。
「男性を
弄ぶ!
貴君は、女性が男性を
弄ぶことを、そんなに恐ろしい罪悪のように考えていらっしゃるのですか。だから、
妾が男性の我ままだと言うのですわ。
若し、男性を
弄ぶ女性を、純真な男性の怒りが、粉微塵に砕くとしたなら、今の世間の大抵の男性は、純真な女性の怒りに
依って、粉微塵に砕かれる資格があるでしょう、
貴君だって、
貴君の純真な奥さんのお心の前に、少しも、恥かしいと思うことはありませんか、
貴君が
妾の良心にお訴えになったように、
妾も
貴君の良心に、それを伺いたいと思いますの。」
夫人の態度は、
明に熱していた。赤く熱すると言うよりも、白く冷たく
而も極度に熱していた。
「女性が男性を
弄ぶと
貴君方男性は、
直ぐ
妖婦だとか毒婦だとか、あらん限りの悪名を浴びせかける。
貴君などは、眼の色を変えてまで、
叱責なさろうとする。が、御覧なさい! 世間の男性がどんなに女性を
弄んでいるかを。女性が男性を
弄ぶに致しましたところで、それは男性の浮動し
易い心を、
弄ぶのに過ぎないじゃありませんか。男性が女性を
弄ぶ場合は、心も肉体も、名誉も節操も、
蹂躙し尽すじゃありませんか。眼にこそ見えませんが、この世間には男性に
弄ばれた女性の生きた
惨たらしい
死骸が、幾つ転がっているかも分りません。
276/390
貴君の眼の前にいる女性なども、案外にもそうした生きた死骸の一つだか分りませんよ。」
夫人の美しい
眸は
爛々と輝いた。その美しい声は、
烈しい熱のために、
顫えていた。
「男性は女性を
弄んでよいもの、女性は男性を
弄んでは悪いもの、そんな間違った男性本位の道徳に、
妾は一身を
賭しても、反抗したいと思っていますの。今の世の中では、国家までが、国家の法律までが、社会のいろ/\な組織までが、そうした間違った考え方を、助けているのでございますもの。御覧なさい! 世の中には、お女郎屋だとか待合だとかお茶屋だとか、男性が女性を公然と
弄ぶ機関が存在しているのですもの。そう言うものを国家が許し、法律が認めているのですもの。また、そう言うものが存在している世の中に、住みながら、教育家とか思想家などと言う人達が、
晏然【平然】として手を
拱いている【何もしない】のですもの。女性ばかりに、貞淑であれ! 節操を守れ! 男性を
弄ぶな! そんなことを、
幾何口を
酸くして説いても、
妾はそれを男性の得手勝手だと思いますの。男性の我ままだと思います。丁度
此の
青木さんのノートが、男性の我ままを示しているように。」
虐げられたる女性全体の、反抗の化身であるように、夫人の態度は、跳ね返る竹の
如き鋭さを持っていた。
五
夫人は、心の中に抑えに抑えていた女性としての平生の
鬱憤を、一時に晴してしまうように、烈しく
迸る火花のように
喋べり続けた。
「人が
虎を殺すと狩猟と言い、紳士的な高尚な娯楽としながら、虎が
偶々人を殺すと、
凶暴とか残酷とかあらゆる悪名を負わせるのは、人間の得手勝手です。
我ままです。
277/390
丁度それと同じように、男性が女性を
弄ぶことを、当然な普通なことにしながら、社会的にも
妾だとか、
芸妓だとか、女優だとか
娼婦だとか、
弄ぶための特殊な女性を作りながら、反対に
偶々一人か二人かの女性が男性を
弄ぶと
妖婦だとか毒婦だとか、あらゆる悪名を負わせようとする。それは男性の得手勝手です。我ままです。
妾は、そうした男性の我ままに、一身を
賭して反抗してやろうと思っていますの。」
彼女は、
一寸言葉を途切らせてから、
「
青木さんとの事だって、そうでございますわ。
貴君などは、
凡ての責任を
妾に負わせようと遊ばす。
妾が、
清浄無垢【汚れのない清らか】な
青木さんを迷わしたようなことをお言いになる。が、あの時計だって、
妾が
青木さんに、どうかお受け取りになって下さいと言って、差し出したものじゃあございませんわ。
青木さんが、幾度も
呉れ/\と
仰しゃったから差し上げたのよ。自分がおねだりなすったことなどは、ちっとも書いておありにならないのですもの。だから、
自惚れが強くって我ままだと申したのですわ。またあの方が、
幾何自殺をすると書いておありになっても、それはあの方の
詠嘆【感情表現】に過ぎませんわ。もし、自動車が転覆しなかったら、あの方は今日あたりは、
妾の
客間へお見えになったかも知れませんよ。また
縦令自殺の決心が、本当でおありになったとしても、それを
妾一人の責任のように、御解釈なさることは、御免
蒙りたいと思いますわ。だって、あの方の性格の弱さに対してまで、
妾は責任を持ちたくありませんもの。
妾との
戯恋の
一寸した幻滅で、自殺をなさるような方は、男子としての生存的意志を、持っていないと申上げてもいゝのですもの。
妾とのいきさつで、自殺なさらなくっても、又なにか別なことで、
直ぐ自殺してしまう方ですもの。」
278/390
信一郎は、夫人の言葉を聴いている中に、それを夫人の
捨鉢な
不貞腐の言葉ばかりだとは、聞きながされなかった。彼は、その美しい夫人の
裡に、
如何なる男性にも劣らないような、鋭い
理知と批判とを持った一個の新しい女性、如何なる男性とも、精神的に戦い得るような新しい強い女性を認めたのである。
彼の夫人に対する
憎悪は、三度四度目に、又ある尊敬に変っていた。旧道徳の殻を踏み
躙っている夫人を、古い道徳の立場から、非難していた自分が、可なり
馬鹿らしいことに気が付いた。
夫人の男性に対する態度は、彼女の
淫蕩【酒色などの享楽にふけること】な動機からでもなく、彼女の
妖婦的な性格からでもなく、もっと根本的な主義から思想から、
萌しているのだと思った。
「
妾、男性がしてもよいことは、女性がしてもよいと言うことを、男性に思い知らしてやりたいと思いますの。男性が平気で女性を
弄ぶのなら、女性も平気で男性を
弄び得ることを示してやりたいと思いますの。
妾一身を賭して男性の
暴虐と我ままとを
懲してやりたいと思いますの。男性に
弄ばれて、綿々の恨みを
懐いている女性の生きた
死骸のために
復讐をしてやりたいと思いますの。本当に
妾だって、生きた死骸のお仲間かも知れませんですもの。」
そう言いながら、夫人は
一寸頭をうなだれた。緊張し切っていた夫人の顔に、悲しみの色が、サッと流れた。
六
物凄いと言ってよいか、死身と言ってよいか、
兎に
角、烈々たる夫人の態度は、
信一郎の心を可なり
振盪した【激しくゆさぶった】。
これほどまで、深い根拠から根ざしている夫人の生活を、慣習的な道徳の立場から、非難しようとした自分の愚かさを、
信一郎はしみじみと悟ることが出来た。夫人をして彼女の道を行かしめる外はない。
縦令、その道が彼女を、どんな
深淵に導こうとも、それは彼女に取って覚悟の前の事に違いない。
279/390
多くの男性を
翻弄した報いのために、縦令彼女自身を
亡ぼすとも、それは、彼女としては、主義に殉ずることであり、男性に対する女性の反抗の犠牲となることなのだ。
「いや! 奥さん、僕は
貴女のお心が、始めて
解ったように思います。僕はそのお心に賛成することは出来ませんが、理解することは出来ます。
貴女に忠告がましいことを言ったのを、お
詫します。
貴女が、一身を
賭して、
貴女の思い通り、生活なさることを、
他から かれこれ言うことの愚さに気が付きました。が、奥さん、僕は、今お
暇する前に、たった一つ
丈お願いがあるのです。聴いて下さるでしょうか。」
「どんなお願いでございましょうか。
妾にも出来ることでございましたら。」
信一郎が夫人の本心を知ってから、可なり妥協的な心持になっているのにも
拘わらず、夫人の態度の険しさは、少しも
緩んでいなかった。
「外でもありません。先刻も申しました通り、
青木君の弟
丈を、
貴女の目指す男性から除外していたゞきたいと思うのです。
青木君の死をまざ/\と知っている
丈、あの方の弟までが、
貴女の客間に出入することは、僕の心を暗くするのです。
青木君の死の責任が
孰らにありましょうとも、
青木君が
貴女を恨んで死んだ以上、
青木君の弟に対して
丈は、慎んでいたゞきたいと思うのです。」
「
貴君は、御忠告をなさらないと言う口の下から、またそう言うことを
仰しゃっていらっしゃるのですね。」そう言いながら、
遉に夫人は
一寸苦笑ともなく微笑ともなく笑った。「自分の生活
丈を自分の思い
通にしようとするものは、利己主義ではない、他人の生活をまで、自分の思い通にしようとするものこそ、本当の利己主義だと、ある人が申しましたが、
貴君などこそ、本当の利己主義でいらっしゃいますわね。
青木さんの弟が
妾を
慕っていらっしゃるとする。
280/390
そう仮定したとしても、それがあの方としては、一番本当の生活じゃございませんでしょうかしら。それが、あの方として一番本当の生き方じゃございませんかしら。そう言う他人の真剣な生活を、
貴君が傍から心配なさることは少しもないと思いますわ。
妾のために、あの方が、一身を犠牲にするような事があったとしても、あの方としては一番本当の生き方をしたと言う事になりは致しませんでしょうか。」
夫人の考え方は、
凡ての妥協と慣習とを踏み
躙っていた。
「果してそんなものでしょうか。僕は断じてそうは思いません。」
信一郎は可なり激しく、抗議せずにはいられなかった。
「それは、銘々の考え方の違ですわ。
妾は、
妾の考え方に
依って生きる自由を持っています。」
夫人は、この長い激論を打ち切るように言った。
「そうです。それはそうかも知れません。が、
貴女が
貴女の考えに
依って生きる自由があるように、僕も僕の考えを実行する自由を主張するのです。奥さん!
青木君の弟を、あなたの
脅威から救うことに、僕は相当の力を尽すつもりです。それは死んだ
青木君に対する僕の神聖な義務だと思うのです。」
「どうか、御随意に。」夫人は、冷然と言った。
「
青木さんの弟に取っては、本当に有難迷惑だとは思いますが、
然し
止むを得ませんわ。
貴君が躍起になった御忠告が、あの方の
妾に対するお心を、どの位
醒させるか、ゆっくり拝見したいと思いますわ。」
夫人は、最後の
止めを刺すように、高飛車に冷然と笑いながら、言い放った。
初恋
一
瑠璃子夫人を、あの太陽に向って、豪然と咲き誇っている
向日葵に
譬えたならば、それとは全く反対に、鉢の中の尺寸の【ほんのわずかな】地の上に、
楚々として
慎やかに花を付けるあの
可憐な
雛罌粟の花のような女性が、夫人の手近にいることを、人々は忘れはしまい。
281/390
それは言うまでもなく、
彼の
美奈子である。
父の
勝平が死んだとき十七であった
美奈子は、今年十九になっていた。その丸顔の色白の
面は、
処女そのものの象徴のような、
浄さと
無邪気とを
以て輝いていた。

男性に対しては、何の真情をも残していないような
瑠璃子夫人ではあったが、彼女は
美奈子に対しては母のような慈愛と姉のような親しさとを持っていた。
美奈子も
亦、彼女の若き母を慕っていた。
殊に、兄の
勝彦が父に対する暴行の結果として、警察の注意のため、葉山の別荘の一室に閉じ込められた
為に、彼女の親しい肉親の人々を
凡て彼女の周囲から、奪われてしまった寂しい
美奈子の心は、自然若い義母に向っていた。若き母も、
美奈子を心の底から愛した。
二人は、過去の
苦い記憶を
悉く忘れて、本当の姉妹のように愛し合った。
瑠璃子が、
勝平の死んだ後も、
荘田家に
止まっているのは、一つは、
美奈子に対する愛のためであると言ってもよかった。この可憐な少女と、その少女の当然受け継ぐべき財産とを、守ってやろうと言う心も、無意識の
裡に働いていたと言ってもよかった。
従って
瑠璃子は、
美奈子を
処女らしく、女らしく
慎しやかに育てゝ行くために、可なり心を砕いていた。彼女は彼女自身の放縦な生活には、決して
美奈子を近づけなかった。
彼女を追う男性が、
蠅のように
蒐まって来る
客間には、決して
美奈子を近づけなかった。
従って、
美奈子は母の
客間に、どんな男性が
蒐まって来るのか、顔
丈も知らなかった。無論紹介されたことなどは、一度もなかった。たゞ門の出入などに、そうした男性と、擦れ違うことなどはあったが、たゞ軽い黙礼の外は口一つ
利かなかった。
282/390
母が日曜の午後を、華麗な客間で、多くの男性に囲まれて、女王のように振舞っているのを
外に、
美奈子は自分の離れの居間に、日本室の居間に、気に入りの女中を相手に、お琴や
挿花のお
復習に静かな半日を送るのが常だった。
時々は、客間に
於ける男性の華やかな笑い声が、遠く彼女の居間にまで、響いて来ることがあったが、彼女の心は、そのために微動だにもしなかった。そうした折など、女中達が、
瑠璃子夫人の奔放な、
放恣な【勝手きままで節度がない】生活を非難するように、
「まあ! 大変お
賑かでございますわね。奥様もお若くていらっしゃいますから。」
などと、
美奈子の心を察するように、忠勤【主君に忠義を尽くして励む】ぶった
蔭口を利く時などには、
美奈子は、その女中をそれとなく
窘めるのが常だった。
が、日曜の午後を、彼女はもっと有意義に過すこともあった。それは、青山に在る父と母とのお墓にお参りすることであった。
彼女は、女中を一人連れて、晴れた日曜の午後などを、わざと自動車などに乗らないで、青山に父母の墓を訪ねた。
彼女は夢のような幼い時の思出などに
耽りながら、一時間にも近い間、父母の墓石の辺に
低徊している【思いにふけりながら、ゆっくり歩きまわる】ことがあった。
六月の終りの日曜の午後だった。その日は死んだ母の命日に当っていた。彼女は、女中を伴って、
何時ものようにお墓参りをした。
墓地には、初夏の日光が、やゝ暑くるしいと思われるほど、輝かしく照っていた。墓地を
画っている
生籬の若葉が、スイ/\と勢いよく延びていた。
美奈子は裏の庭園で、切って来た美しい
白百合の花を、
右手に持ちながら、
懐しい人にでも会うような心持で、墓地の中の小道を幾度も折れながら、父母の墓の方へ近づいて行った。
283/390
二
晴れた日曜の午後の青山墓地は、
其処の墓石の辺にも、
彼処の
生籬の
裡にも、お墓
詣りの人影が、チラホラ見えた。
清々しく水が注がれて、線香の煙が、白くかすかに立ち昇っているお墓なども多かった。
小さい子供を連れて、
亡き夫のお墓に詣るらしい若い未亡人や、
珠数を手にかけた大家の老夫人らしい人にも、行き違った。
荘田家の墓地は、あの有名なN大将の墓から十間と離れていないところにあった。
美奈子の母が死んだ時、父は貧乏時代を
世帯の苦労に苦しみ抜いて、
碌々夫の栄華の日にも会わずに、死んで行った
糟糠の【貧しい時代を共に苦労した】妻に対する、せめてもの心やりとして、
此処に広大な墓地を営んだ。無論、自分自身も、妻の後を追うて、
直ぐ
其処に埋められると言うことは夢にも知らないで。
亡き父の
豪奢は、周囲を巡っている
鉄柵にも、
四辺の墓石を圧しているような、一丈に近い墓石にも
偲ばれた。
美奈子は、女中が水を
汲みに行っている間、父母の墓の前に、じっと
蹲りながら、心の
裡で父母の
懐しい面影を描き出していた。世間からは、いろ/\に悪評も立てられ、成金に対する攻撃を、一身に受けていたような父ではあったが、自分に対しては、世にかけ替のない優しい父であったことを思い出すと、
何時ものように、追慕の涙が、ホロ/\と止めどもなく、二つの頬を流れ落ちるのだった。
女中が、水を汲んで来ると、
美奈子は、その花筒の古い汚れた水を、
浚乾してから、新しい水を、なみなみと注ぎ入れて、
剪り取ったまゝに、まだ香の高い
白百合の花を、挿入れた。こうしたことをしていると、何時の間にか、心が
清浄に澄んで来て、父母の霊が、遠い/\天の一角から、自分のしていることを、
微笑みながら、見ていて
呉れるような、頼もしいような懐しいような、清々しい気持になっていた。
284/390
美奈子は、花を供えた後も、じっと
蹲まったまゝ、心の中で父母の
冥福を祈っていた。微風が、そよ/\と、向うの杉垣の間から吹いて来た。
「ほんとうに、よく晴れた日ね。」
美奈子は、やっと立ち上りながら、女中を見返ってそう言った。
「左様でございます。ほんとうに、雲の
片一つだってございませんわ。」
そう言いながら、女中は
眩しそうに、晴れ渡った夏の大空を仰いでいた。
「そんなことないわ。ほら、
彼処にかすったような白い雲があるでしょう。」
美奈子も、空を仰ぎながら、晴々しい気持になってそう言った。が、
美奈子の見付けたその白いかすかな雲の一片を除いた外は、空はほがらかに
何処までも晴れ続いていた。
「今日は
余りいゝお天気だから直ぐ帰るのは惜しいわ。ぶら/\散歩しながら、帰りましょう。」
そう言いながら、
美奈子は女中を
促して、懐しい父母の墓を離れた。
何時もは、歩き
馴れた道を、青山三丁目の停留場に出るのであったが、
其日は清い墓地内を、
当もなくぶら/\歩くために、わざと道を別な方向に選んだ。
自分の家の墓地から、三十間ばかり来たときに、
美奈子はふと、美しく刈り込まれた
生籬に囲まれた墓地の中に、若い二人の
兄妹らしい男女が、お詣りしているのに気が付いた。
美奈子は、軽い好奇心から、二人の容子を可なり注意して見た。兄の方は、二十三四だろう。
銘仙らしい白い
飛白に、
袴を
穿いて
麦藁の帽子を
被った、スラリとした姿が、何処となく上品な気品を持っていた。妹はと見ると、まだ十五か十六だろう、青味がかった
棒縞のお召にカシミヤの
袴を
穿いた姿が、質素な周囲と反映してあざやかに美しかった。
美奈子達が、段々近づいてその墓地の前を通り過ぎようとしたとき、ふと振り返った妹は、
美奈子の顔を見ると、微笑を含みながら軽く
会釈した。
285/390
2/3分割、前へ、次へ